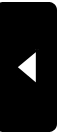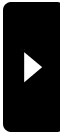2024年03月08日
2024年3月1日以降 アトレー・ハイゼットカーゴ 他(S300系)アイズ-ブロッカー取付説明書
アトレーワゴン, ハイゼット カーゴ (S300系) アイズ-ブロッカー取付説明書
(特許第6862023)
アトレーワゴン, ハイゼット カーゴ (S300系) ハイルーフ用
2024年3月1日以降に出荷した製品の装着方法となります。
※2024年08月23日以降に出荷した製品から、付属の「磁石アンカー」の仕様が変更になっています。
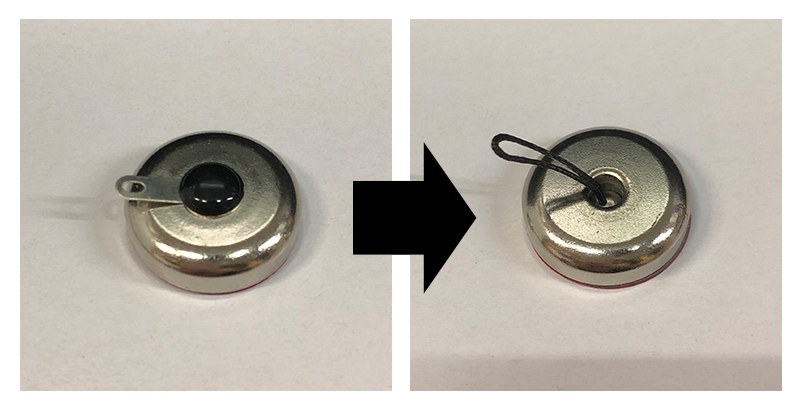

===================
【必要工具類】
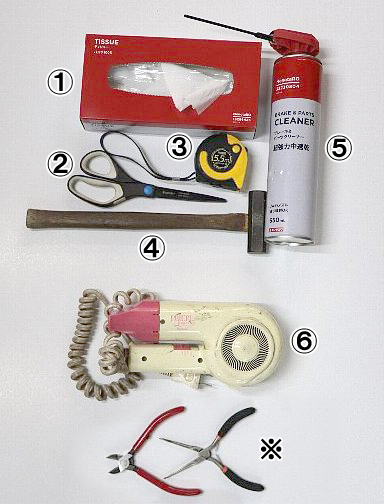
①:テッシュ
②:ハサミ
③:メジャー
④:ハンマーの類(フツーのトンカチでokです)
⑤:パーツクリーナーの類(脱脂処理に使用します。ベンジンなどの石油系溶剤がお勧めです。シンナーなどの溶剤は塗装面を痛めます)
⑥:ドライヤー(寒冷時や多湿の場合に使用)
※先の細いプライヤーやペンチの類
※水性ペン
※踏み台
があると便利です。
===================
【商品内容】を ご確認ください。

①:アイズ-ブロッカー本体タープ布:左右2枚(ショックコード付き)
※運転席側のタープ布には、緑色の「Aizuのタグ」が縫い付けています。助手席側にはタグはありません。
②:バックドア側ホールドテープ:2本
③:脱脂確認用 ためし貼りテープ:2枚
④:バックドア側アンカー(磁石タイプ):2個
⑤:バックドア側ホールドテープ用プライマー液:1 個
⑥:ボディー側ホールドテープ
長いテープ:2本(ボディー上側に使用)
短いテープ:2本(ボディー下側に使用・切り込み付き)
⑦:ボディー側ホールドテープ固定用 爪付きクリップ:10個
⑧:ボディー側アンカー
紐付きの短いテープ状のもの:2個 + 爪付きクリップ 小2個付き
以上、8点です
===================
【各部の名称】です。
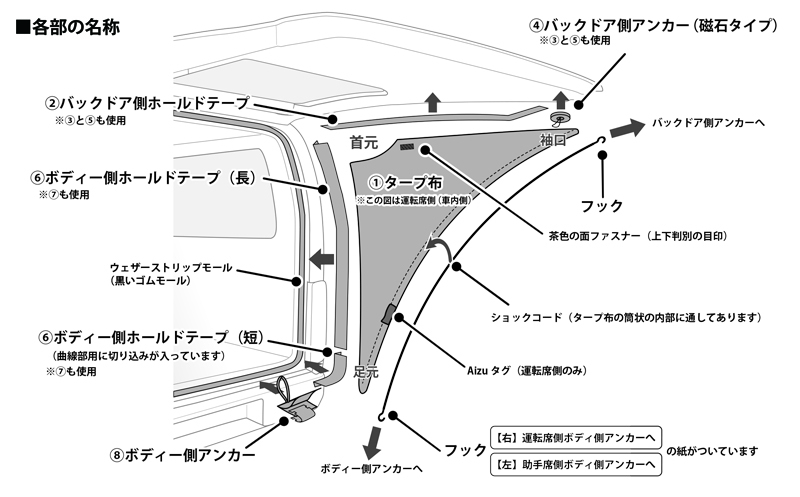
【作業時間】
作業自体は約1時間ほどですが、粘着材貼付け後に最低1時間(できれば3時間)以上、養生時間をおいてください。
【作業環境について】
粘着材貼付け作業には、気温が20℃以上、乾燥した状況下が望ましいです。寒冷時や雨天等の多湿時等は、ドライヤー(家庭用のものでOKです)を使用しながら作業をしてください。
気温が15℃以下の気温下では、十分な貼り付け強度が実現しない可能性があります。
家庭用のヘアードライヤーでOKですので、粘着面と貼り付け面との両方を40℃くらいに温めながらの作業をお勧めします。ヘアードライヤーなどが使えない作業環境の場合には、 車のリヤヒーターを稼働させてバックドアの貼り付け面をできるだけ温めておき、テープ自体も温めた状態にしておいてからの貼り付け作業が よろしいかと存じます。
【装着作業の流れ】
■1.バックドアの脱脂(コーティング剤の磨き落とし処理が必要な場合もあります)と プライマー塗布を行う
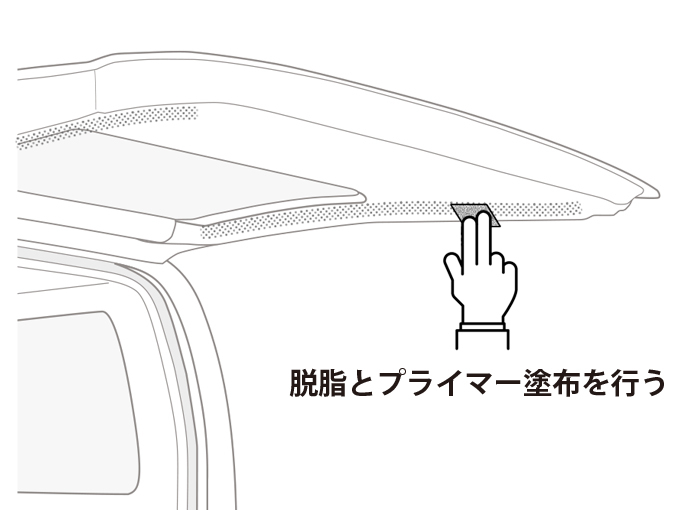
■2.バックドアにアンカー(磁石タイプ)とホールドテープを貼り付ける
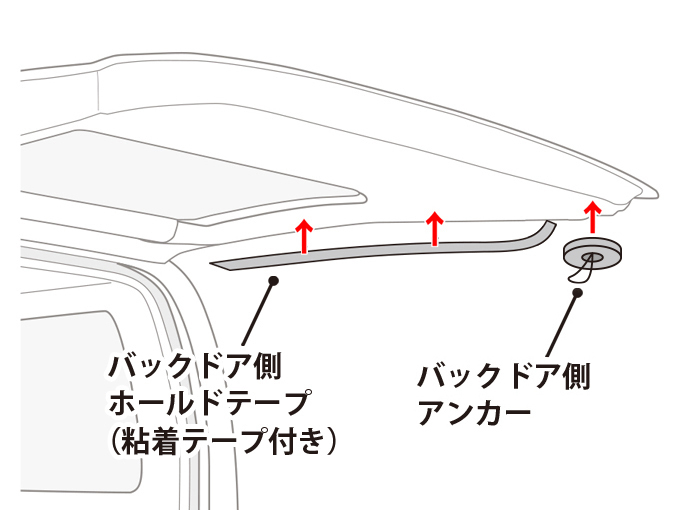
■3.ボディーにアンカーとホールドテープを装着する。
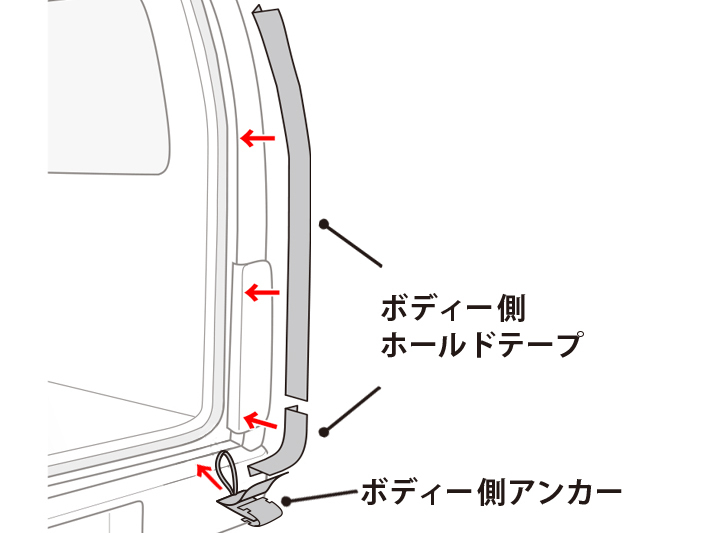
※次のタープ布を取り付ける前に、最低1時間(できれば3時間)以上、養生時間をおいてください。養生中に粘着材の接着力が増します。
■4.タープ布を取り付ける。
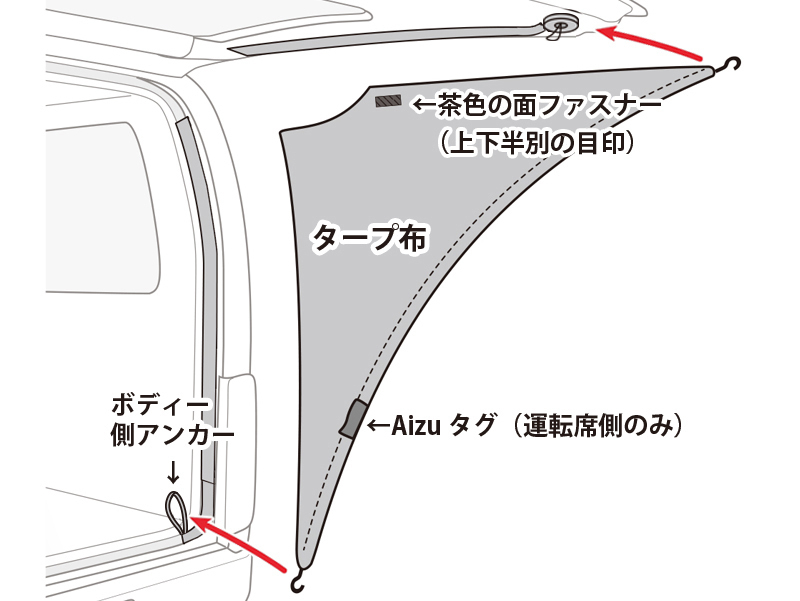
■5.タープ布の貼り具合を調整して、ドアの閉まり具合を確認する。
このブログや取付け説明書を、最後までお読みいただいたうえで作業を開始してください。
以下、取り付けの詳細手順です。
==========================
1.バックドアのアンカーやホールドテープの貼り付ける面をしっかりと脱脂処理する
ウェザーストリップモールがバックドア側に当たる部分の内側にテープとアンカーを貼り付けますので、それらを貼り付ける場所の周辺を広めにしっかりと脱脂処理してください。
(ウェザーストリップモールについては、上で記載した【各部名称】や 4-1.ウェザーストリップモールの取り外し を参照ください)
脱脂処理する場所は下画像の赤で記したあたりです。



1-1.脱脂処理をする
貼り付ける部分に、カーワックスの成分などが残っていると、粘着材はしっかりと貼りつきません。パーツクリーナーやベンジンなどを使って、しっかりと脱脂処理してください。
バックドアの左右とも脱脂処理をしてください。



1-2.脱脂状態を確認する
脱脂作業が終りましたら、ホールドテープを貼る前に脱脂が十分にできているかの確認をしてください。脱脂作業をした箇所に、テストピース(小さな試し貼りテープ)を貼ってみてください。
▼貼った上から強く指圧をするくらいの力で数秒間加圧してください。

5分ほど経過させたのち剥がそうとしてみてください。
▼ガムテープを貼ったときのように、剥がすのに抵抗感があるようでしたらOKです。

▼さほどの抵抗感なく剥がれてくるようですと、脱脂が十分にできていませんので、再度脱脂作業を行ってください。

2. 貼り付け面にプライマー処理をする
貼り付け部周辺に付属のプライマーを必ず塗ってください。
プライマーによる下地処理をすることで、テープをより強固に接着させることができます。
下画像の車は別の車種ですが、作業内容は同じです。ご了承ください。
小さく折りたたんだ(3~4cm四方)テッシュに、小瓶に入っているプライマー液を浸み込ませながら、塗装面を拭くようにしていただければOKです。




プライマー液は十分な量が入っていますが少量ですので こぼさないようにご注意ください。
続けて反対側(助手席側)にもプライマーを塗ってください。10分ほど乾燥させたのちに次の「手順3」へ進んでください。

3.バックドア側アンカーとバックドア側ホールドテープを貼り付ける
作業の前準備として、テープやアンカーを貼り付ける位置を今一度ご確認ください。
テープの貼り直しはできませんのでご注意ください。

3-1.バックドア側アンカーを貼り付ける
まず、バックドア下部に、バックドア側アンカーを貼り付けます。アンカーの貼り付け強度はとても重要です。
この部分だけでもドライヤーで、貼り付け面と粘着材の両方を十分に暖めながら貼り付けるようにしてください。
貼り付け位置は、下の図を参考にしてください。位置は厳密でなくとも、おおむね画像と同じような位置でかまいません。
下画像は全て運転席側です。助手席側も同様に貼ってください。
下画像の「× 印」をつけたあたりを向く角度にアンカーを傾けて貼ります。
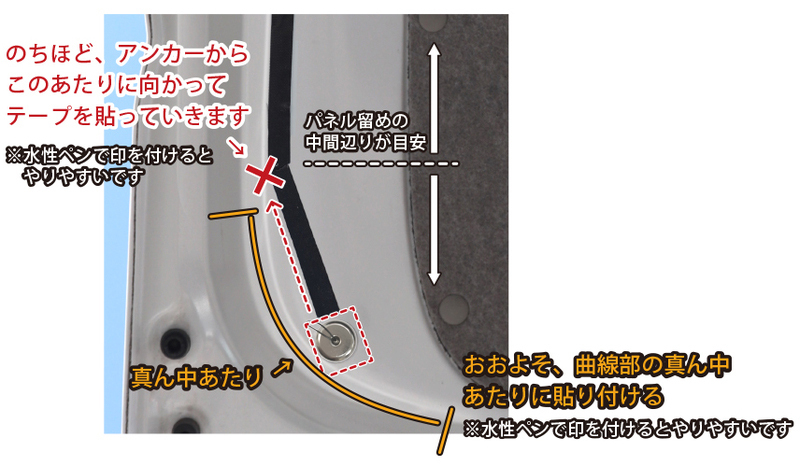
↓2024年8月23日出荷以前の「磁石タイプアンカー」の注意点です

貼り付けた後で、空気を抜くようにシッカリと圧着させてください。指圧をするイメージです。
画像は全て運転席側です。助手席側も同様に貼ってください。
3-2.バックドア側ホールドテープを貼り付ける
テープは、ウェザーストリップモールがバックドア側に当たる部分の内側に貼り付けます。※手順1をご参照下さい。
テープも貼り直しはできません、ほぼ一発勝負ですので貼り付け作業の前準備として、テープを貼り付ける位置を 今一度確認したうえで貼り始めてください。
貼り付けてから、数秒経過すると まともには剥がせませんので ご注意ください もし、貼り直しをせざるを得ない場合には、元の粘着材は、使えない状態になっているかと思います。その場合は、いったん使えない状態部分の粘着材をはがし取っていただき(石油系溶剤を用いると剥がしやすいです)市販の両面テープ(高耐熱仕様のテープが少量で販売されています)を貼り直してから、再度貼り付けていただくか、弊社ホームページで販売中の補修用のテープをお使いください。https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/168
ホールドテープは、バックドア側アンカーのすぐそばから貼り始めます。曲線部分はシワ(ひだ)になっても問題ありません。(テープの上にタープ布が接合されるのでシワは隠れます)

プレスラインの内側に沿って貼り進めていきます

テープの長さ分、全部を貼ってください。あとから 余った部分をハサミで切り落とすこともできます。なお、切らずにそのまま残しても機能的には問題ありません。
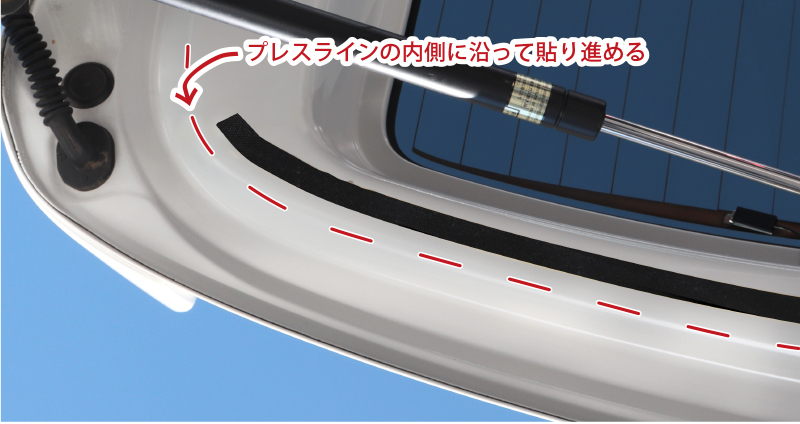
貼り終えた全体図です↓
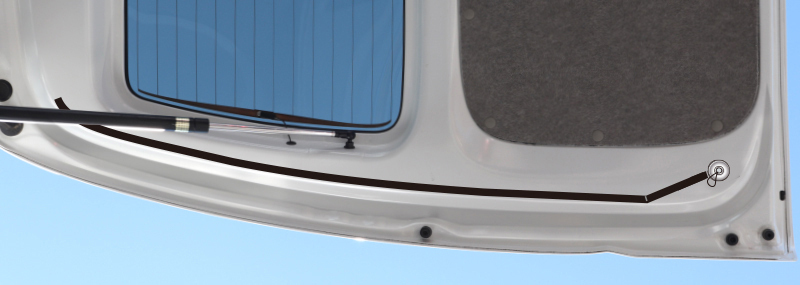
3-3 十分に加圧する
上から しっかりとテープを押し付けてください。
「貼り付けたテープが剥がれてきてしまった・・・」 の原因には、この加圧が 不十分だった ことによる場合が 少なくありません。業者さんでも、「貼り付けて おしまい」 にしてしまう場合もあります・・・粘着テープは「感圧接着剤」とも呼ばれていて、圧力を加えないと 十分な接着力(粘着力)を発揮しません。高性能なテープほど しっかりと圧力を加える必要があります。テープの上から 1㎝ごとに 指圧をするつもりで加圧していってください。特に アンカーと、ホールドテープの一番下側のアンカー付近と、一番上側の端部付近は、入念に押し付けてください。
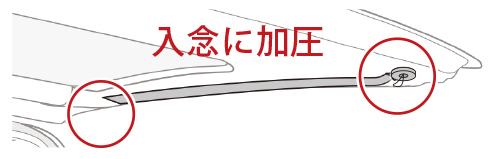

繰り返しになりますが、「テープを単に貼っただけでは、剥がれてきてしまいます。しっかりと押し付けてください」


4.ボディー側アンカーを取り付ける

4-1.ウェザーストリップモールの取り外し
まず、ウェザーストリップモールを後方に引き出して外します。


下部はこの辺りから、上部はこの辺りまで外しておきます。

4-2.取り付け位置の確認
次に、車体中央を基準にボディー側アンカーを取り付けますので位置を確認してください。ドアロック金具の中央から、爪付きクリップの内側までが56cmあたりの位置に取り付けます。

4-3.アンカーの打ち込み
※画像は違う車種のものですが、行う作業内容と手順は同じです。
ループ紐の付いた短いテープを、爪付きクリップを使って鉄板に固定します。テープの端と鉄板の端を合わせるようにします。

先に、テープを爪付きクリップに差し込んでから
この時アンカーの端を、車外側へ5ミリほどはみ出させて固定してください↓

ハンマーを使って奥までしっかりと打ち込みます。引っ張っても抜けてこなければOKです。

5. ボディー側ホールドテープを装着する
まず動画をご覧いただき、装着イメージをつかんでください。
下の動画では、キャンピング架装されている車に、付属の「爪付きクリップ」を利用ながら、ホールドテープと網戸も一緒に装着しています。ホールドテープだけを装着する場合にありましても、付属の「爪付きクリップ」を利用することで、確実な装着ができます。
その1、
その2、下側付近は、引き出されようとする力がより強く働きます。「爪付きクリップ」を細かく打ち込んで、入念に固定しています
その3 市販されている、網戸のファスナーを開閉する際に、網戸の下部が モールから抜け出さないように「爪付きクリップ」で補強しています。
動画内で使っている「爪付きアンカー」は、製品に10個 付属させています。追加でお求めいただくこともできます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport
↑
アイズ-ブロッカーのタブをクリックし、表示されたメーカー一覧から車種をご選択ください
作業前に ウェザーストリップの鉄芯の状態を確認してください。
それでは、ボディ側ホールドテープを装着していきます。テープは長さが異なる2種類のテープが付属されています。
5-1.長いホールドテープを取り付ける起点を決める
まず長いテープから装着を行います。装着は装着は、上側曲線部の中央付近から装着し始めます。厳密でなくても、おおよそで大丈夫です。

テープの装着始点部分に 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定します。

5-2.下側に向かってホールドテープを装着していく
■ 装着要領■
①ウェザーストリップモールの溝にボディー側ホールドテープの幅の狭いほうを差し込みます。

②テープを差し込んだ状態のまま、元通りにボディーの鉄板へ はめ込みます。

この作業をすこしずつ繰り返して装着していきます。
※所々に、テープの装着始点部分で使った 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定することで、テープがズレるのを防いで装着がしやすくなります。
上の動画でも使っていますので ご確認ください。
下側へ向かってテープ全てを装着していってください。
差し込んだら…

しっかりと手のひらで叩き込む

ウェザーストリップモールを車外側から見てみると、シッカリ奥まで入っているかの判断がつきます。
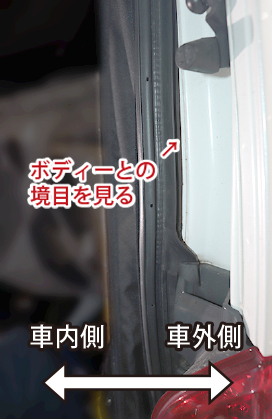
画像のようにベロ(ひだ)が付いている場合はめくって確認します。

↓ 隙間があるので、モールが奥まで入っておらずダメです。モールがシッカリ奥まで入っていれば隙間はありません。

5-3.長いテープにつなげて、短いホールドテープを取り付ける
※以下の画像は違う車種のものですが、行う作業内容と手順は同じです。
長いテープの下端に、短いテープの端を5ミリほど重ねてから、


重ねた部分を「爪付きクリップ」で固定します。


短いテープの中間あたりも「爪付きクリップ」で固定します

ボディー側アンカーに5ミリほど重なるようにカットし…


重ねた付近を「爪付きクリップ」で固定します

5-4.ウェザーストリップモールをハンマーで打ち込む
ウェザーストリップモールの上から ハンマーで 奥いっぱいまで打ちこみます。この作業が大事です。
軽い力で奥まで打ち込めるのですが、一部でも打ち込みが甘いと、ウェザーストリップモールが浮き上がっていることで バックドアの閉まりが悪くなってしまいます。
しっかりと打ち込まれているかの判断は、目視では難しいので 打ち込んでいるときに出る音や、感触で判断します。
★鈍い音・柔らかな感触 → 高い音・硬い感触 になっていればOKです

アイズ-ブロッカーを装着後「バックドアの閉まりが固くなった」感じがする場合には上記のウェザーストリップモールの浮き上がりを再度確認してください。
※特に上側あたりに浮き上がりがあると 閉まり具合への影響が大きいですので、上側は入念にチェックしてください。
6. タープ布を取り付ける
=================================
養生時間を経過させてください。
ホールドテープを装着後、1時間以上、できれば3時間ほど養生時間が経過していることを確認してください。その間に バックドア側に貼ったテープの接着力が増し、本来の性能の80%ほどの接着力になります。
夏場の晴れた日の作業でしたら、テープを貼って シッカリと加圧ができていれば 1時間後には大丈夫な接着強度になっていたりしますが、できるだけ上記の養生時間を経てから タープ布を装着してください。特に寒冷時や雨の日の作業では 十分な養生時間を経過させてください。
=================================
6-1.タープ布の判別
タープ布の車外側になる面には撥水加工処理を行っていますので、以下の方法で車外側を判別し、間違えないように装着してください。
▼タープ布の 運転席側/助手席側 の判別方法▼
運転席側の車内側だけに緑色のAizuのタグがついています。

※最新のタグはコチラ

▼装着時の目印▼
左右のタープ布とも、車内側になる面には薄茶色の面ファスナーが付いています。
これがバックドアの上部(首元)へ来るように装着してください。
(装着終了後は取り外してください)

6-2.ショックコードの接合
タープ布の「袖口(上側)」と「足元(下側)」から出ているショックコードの端部に付いているフックをバックドア側アンカーとボディー側アンカーのそれぞれに接合します。
▼ボディー側アンカーへ▼
アンカーから出ている紐をループ状に広げておき、接合します。接合後はフックの開きを閉じ、タグを取り外してください。先の細いプライヤーで作業するとつなげやすいです。


▼バックドア側アンカーへ▼
☆2024年8月23日以降に出荷した製品の場合
さきほどの反対側から出ているフックを、紐につなげてからフックの開きを閉じてください。


☆2024年8月23日以前に出荷した製品の場合
さきほどの反対側から出ているフックを、リップ(薄い板)の穴につなげてからフックの開きを閉じてください。


ショックコードを接合し終えバックドアを全開にすると、このような状態になり ます。

6-3.タープ布の接合
タープ布をホールドテープに接合していきます。①~⑩の順に取り付けを行ってください。
▼まず①~⑤です▼
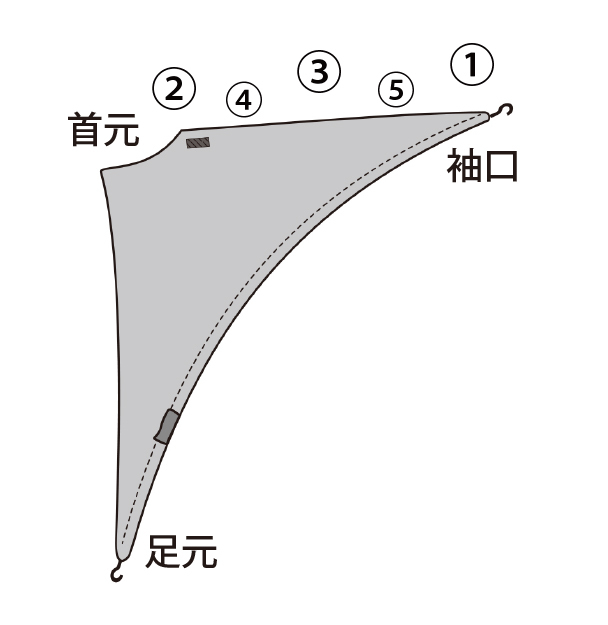
①.アンカー側端部(袖口)を接合します。
端部から15cmほど接合します。

②.反対側の端部(首元)を接合します。
15cmほど接合します。タープ布は伸縮性の高い生地ですので1.2倍ほどに伸びます。
強く引き伸ばしていただいても大丈夫です。

③.次に真ん中あたりを接合します。
5cmほど接合します。この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの④と⑤の辺りを、シワが無いように接合します。
▼次に⑥~⑩です▼

⑥.ボディー側の端部(首元)を接合します。
15cmほど接合します。
バックドア側と同様に、生地を引き伸ばして接合します。
その際に、首元ありのタープ布に張り感が出るように、なおかつあまり張りすぎない程度に接合してください。
ホールドテープの終端部とタープ布の終端部は、一致しません。テープの方が少し(1~2cm)余り気味になるはずです。余ったテープはのちほど切り取れますし、そのまま残しても問題ありません。

この辺りに適度な張り感
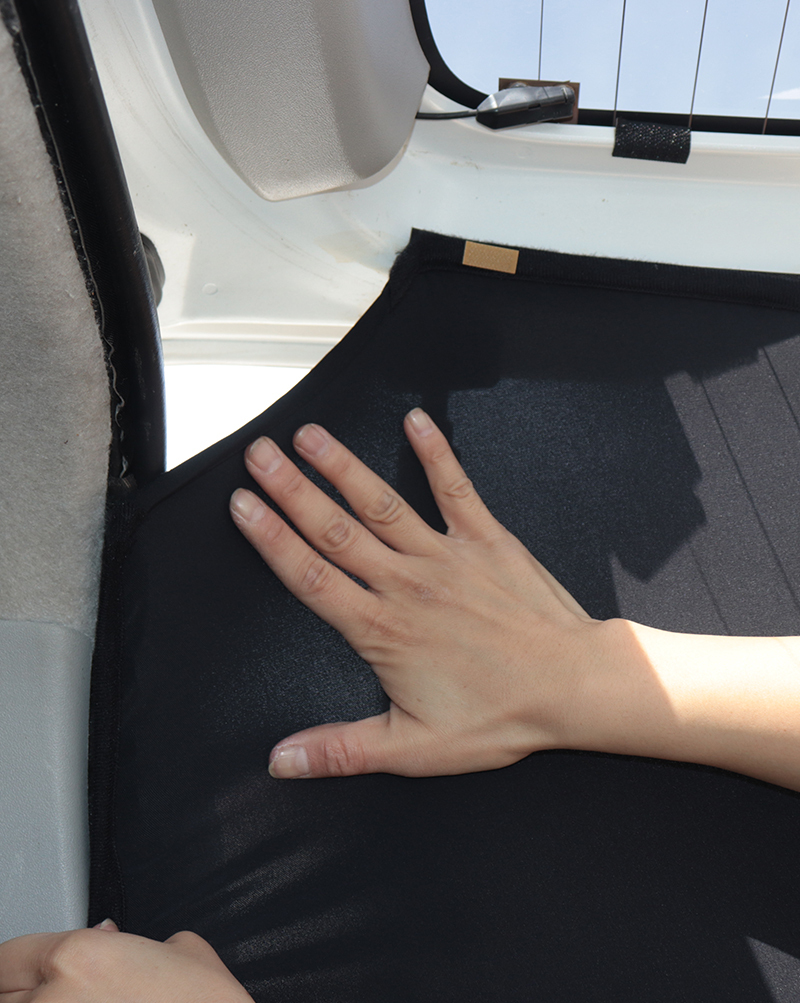
↑※この部分の張りが強すぎますと、バックドアを引き下げる力が強く働き ドアが全開位置に保持しずらくなります。張りが強すぎる場合には、上側方向に装着位置をずらしていく(ボディ側とバックドア側との距離を縮める)ことで 張り具合を 弱めることができます。
⑦.下側端部(足元)を接合します。
端部から15cmほど接合します。

⑧.次に真ん中あたりを接合します。
5cmほど接合します。
この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの⑨と⑩の辺りを、シワが無いように接合します。
※もしこの時点でシワが無くキレイに張れていれば、次の「手順7-1」は飛ばしてもらっても構いません※
7. 貼り具合を調整します
7-1.タープ布の調整
シワっ気が 残るようでしたら、何度も 剥がしては接合を繰り返して 貼り直してみてください。

テープ接合を剥がすには、タープ布の内側と外側の両方から 行うとやりやすいです。


シワが出ないようにするコツとしては、生地の一部に たるみが出ないように タープ布の接合部全体にわたって、 同じような引っ張り加減にすることです。
おおむね シワが取れました。

7-2.タープ布を強く接合する
具合よく張っている状態が確認できたら、タープ布とバックドア側、タープ布とボディー側の 各ホールドテープとの接合部を しっかりと押さえて、接合を強くします


7-3.はみ出しているテープの処理
もし 上側端部のホールドテープが余っているようでしたら、ハサミで切り取って整えて下さい。なお、切らなくても機能的には問題ありません。
↓バックドア側(まっすぐ切ります)

↓ボディー側(角の部分は丸く切っておくと安全です)

8. バックドアの閉まり具合をご確認ください
バックドアを閉めてみてください。
閉まり具合が 装着前よりも固く感じるようでしたら、5-4 の「ウェザーストリップモールの浮き上がり」を 再度 確認してください。
パッと見では浮き上がりがないように見えても、ハンマーでたたいてみると 鈍い音がする場合もあります。
特に上部はわずかな浮きでも閉まり具合に影響します。(下部はさほどの影響はありません)

タープ布が はさまれないか を ご確認ください。
バックドアを勢いよく閉めようとすると、車内の空気が車外側へと流される際にタープ布も外側に出されてしまい、タープ布がドアに挟まれやすくなります。特に、バックドアに網戸を装着していたり、キャンピング架装車などで 後端部に収納棚等が装備されていたりすると、車内空気を排出する為のダクトの通気量が少なくなっている(あるいはなくなっている)ことで その作用が出やすいです。バックドアをゆっくり閉めるようにしてみてください。あるいは 少しご面倒ですが、スライドドアや小窓等を開けた状態でバックドアを閉めると、空気の逃げ道ができることでタープ布が挟まれにくいだけでなく、バックドアの閉まり具合が劇的に軽くなります。ぜひ お試しください。


バックドアが元通りの全開状態になるかどうかを、ご確認ください。
・バックドアダンパーが経年劣化で反力が弱まっていると、アイズ-ブロッカーを装着されたことで、ドアが全開しなくなる場合もありますし、もし「強化ダンパー」などに交換されていると、ドアの開口具合が純正状態よりも、より開く仕様になっている場合もあります。
・バックドアを開けた後端の高さが、純正状態よりも10cmほどの高さまでは、タープ布は追随できるようになっていますが、張りが強すぎる部分があると、全開にならなかったり、ウェザーストリップモールが引き出される場合があります。
★タープ布に、張りすぎ感があるようでしたら、タープ布の上部付近を上側方向に移動させてみて下さい。
取り付け方法のご案内は、以上となります。
============================
■バックドア側のホールドテープが剥がれてきてしまう場合について
バックドア側のホールドテープは 最下部の曲線部が一番 剥がれようとする力が働きます。 「この部分だけが剥がれてしまった・・・」場合には、剥がれた部分だけを貼り直すことで補修ができます。20cm+20cm(合計40cm)の長さのホールドテープ と、下地処理用のプライマーを、補修用品として用意しています。
他にも、各種補修部品を下記ページにて ご購入いただけます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/168
============================
■そのほかの ご使用上のご注意につきましては こちら をご確認ください。
============================
最後になりますが、
ご使用上で 気になることが ございましたら ご報告いただけますと
今後の改良などへと つなげることができて、ありがたく存じます。
弊社レビュー投稿ページはコチラにあります。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/reviewlist
どうぞ よろしくお願いいたします。
株式会社 アイズ
アイズ-ブロッカー 開発・製作担当者 一同
TEL 053-422-7608
FAX 053-422-7178
info@aizu-rv.co.jp
============================
アイズ-ブロッカーは、 特許取得済です(特許第6862023)
また、上記説明書の営利目的利用はご遠慮下さい。(©aizu2021)
よろしくお願いいたします。
(特許第6862023)
アトレーワゴン, ハイゼット カーゴ (S300系) ハイルーフ用
2024年3月1日以降に出荷した製品の装着方法となります。
※2024年08月23日以降に出荷した製品から、付属の「磁石アンカー」の仕様が変更になっています。
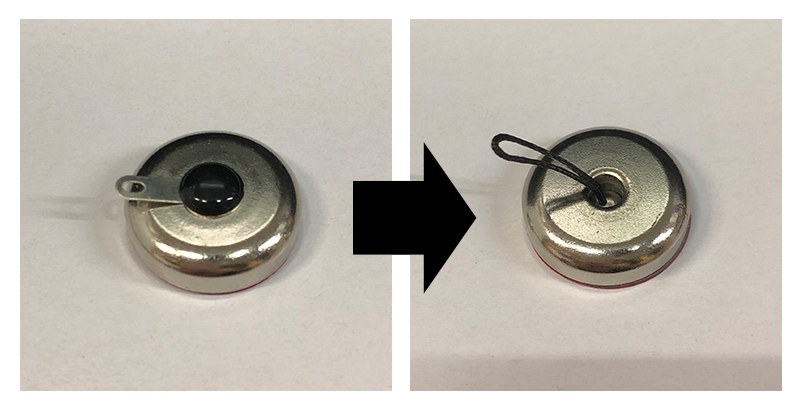

===================
【必要工具類】
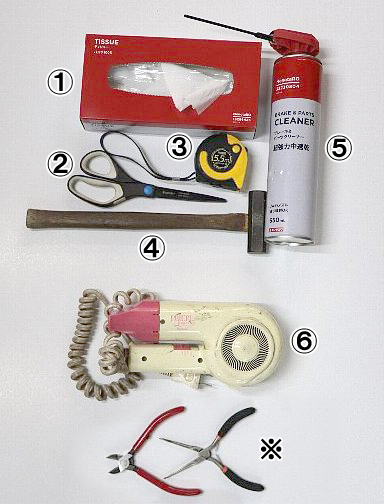
①:テッシュ
②:ハサミ
③:メジャー
④:ハンマーの類(フツーのトンカチでokです)
⑤:パーツクリーナーの類(脱脂処理に使用します。ベンジンなどの石油系溶剤がお勧めです。シンナーなどの溶剤は塗装面を痛めます)
⑥:ドライヤー(寒冷時や多湿の場合に使用)
※先の細いプライヤーやペンチの類
※水性ペン
※踏み台
があると便利です。
===================
【商品内容】を ご確認ください。

①:アイズ-ブロッカー本体タープ布:左右2枚(ショックコード付き)
※運転席側のタープ布には、緑色の「Aizuのタグ」が縫い付けています。助手席側にはタグはありません。
②:バックドア側ホールドテープ:2本
③:脱脂確認用 ためし貼りテープ:2枚
④:バックドア側アンカー(磁石タイプ):2個
⑤:バックドア側ホールドテープ用プライマー液:1 個
⑥:ボディー側ホールドテープ
長いテープ:2本(ボディー上側に使用)
短いテープ:2本(ボディー下側に使用・切り込み付き)
⑦:ボディー側ホールドテープ固定用 爪付きクリップ:10個
⑧:ボディー側アンカー
紐付きの短いテープ状のもの:2個 + 爪付きクリップ 小2個付き
以上、8点です
===================
【各部の名称】です。
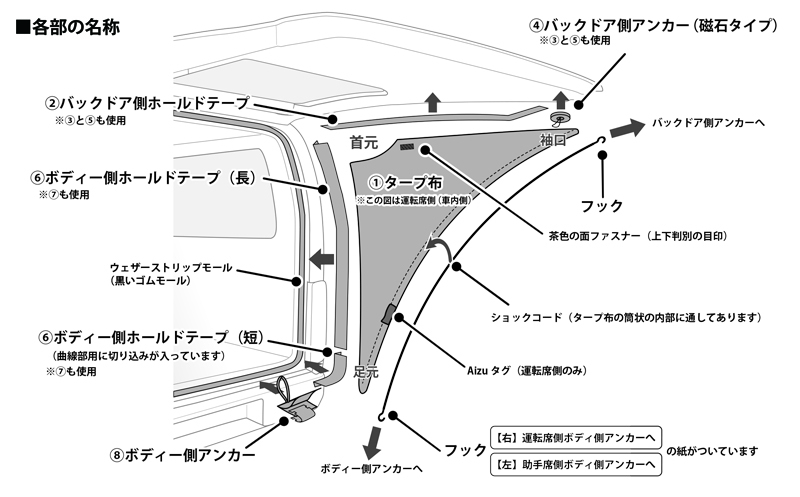
【作業時間】
作業自体は約1時間ほどですが、粘着材貼付け後に最低1時間(できれば3時間)以上、養生時間をおいてください。
【作業環境について】
粘着材貼付け作業には、気温が20℃以上、乾燥した状況下が望ましいです。寒冷時や雨天等の多湿時等は、ドライヤー(家庭用のものでOKです)を使用しながら作業をしてください。
気温が15℃以下の気温下では、十分な貼り付け強度が実現しない可能性があります。
家庭用のヘアードライヤーでOKですので、粘着面と貼り付け面との両方を40℃くらいに温めながらの作業をお勧めします。ヘアードライヤーなどが使えない作業環境の場合には、 車のリヤヒーターを稼働させてバックドアの貼り付け面をできるだけ温めておき、テープ自体も温めた状態にしておいてからの貼り付け作業が よろしいかと存じます。
【装着作業の流れ】
■1.バックドアの脱脂(コーティング剤の磨き落とし処理が必要な場合もあります)と プライマー塗布を行う
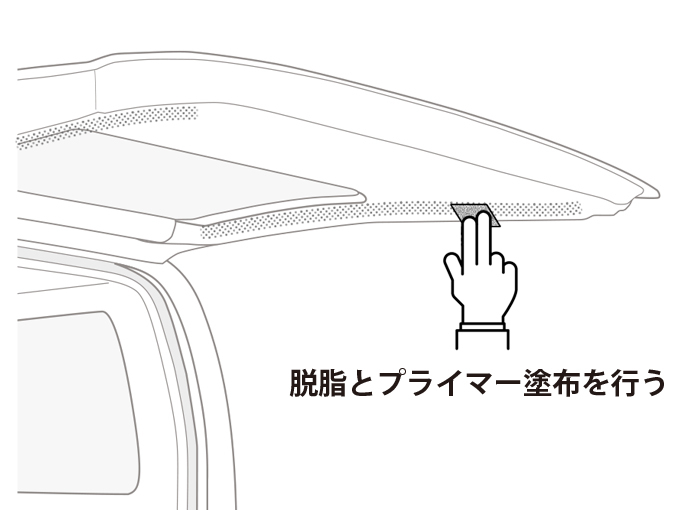
■2.バックドアにアンカー(磁石タイプ)とホールドテープを貼り付ける
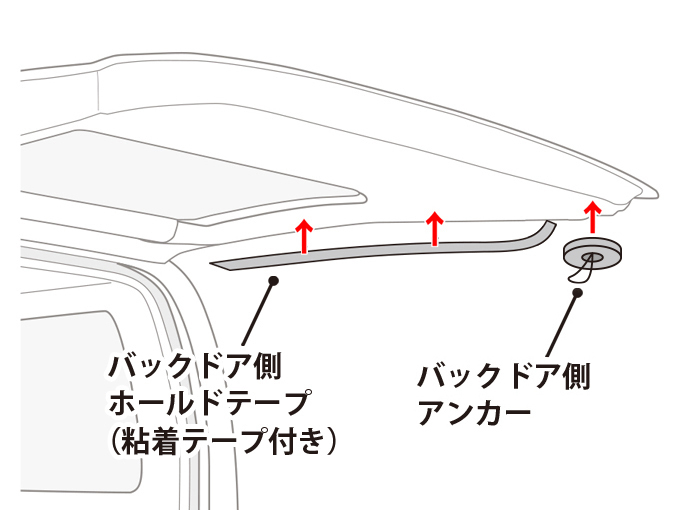
■3.ボディーにアンカーとホールドテープを装着する。
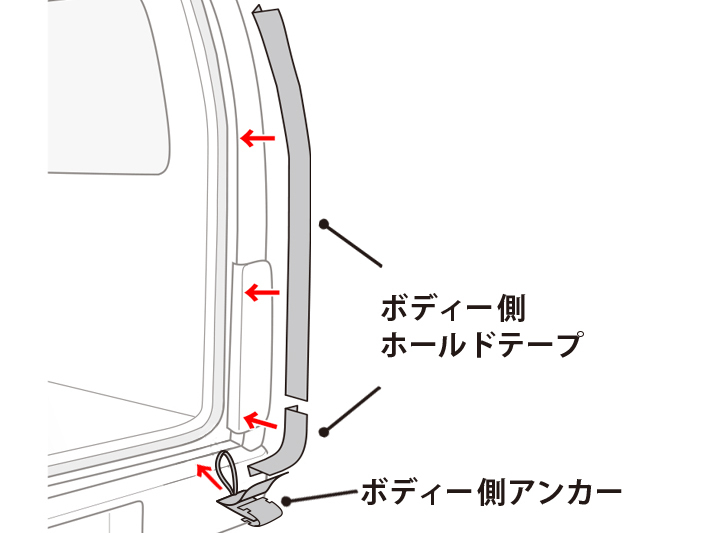
※次のタープ布を取り付ける前に、最低1時間(できれば3時間)以上、養生時間をおいてください。養生中に粘着材の接着力が増します。
■4.タープ布を取り付ける。
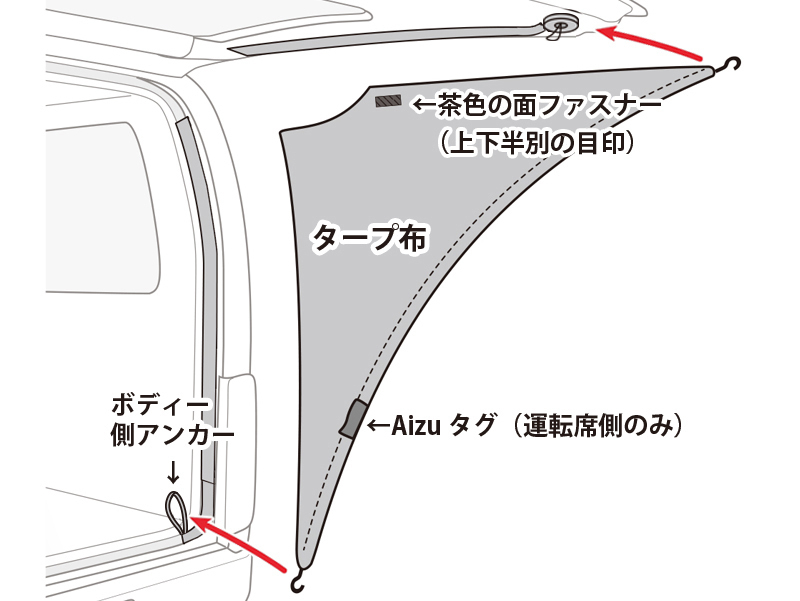
■5.タープ布の貼り具合を調整して、ドアの閉まり具合を確認する。
このブログや取付け説明書を、最後までお読みいただいたうえで作業を開始してください。
以下、取り付けの詳細手順です。
==========================
重要!!
▼作業時の温度・湿度について
気温が20℃以上あり、乾燥した状況下での作業が望ましいです。
寒冷時や多湿時等は、ドライヤー(家庭用のものでOKです)を使用してください。
↓↓
ドライヤーを使い、貼り付ける箇所とテープの粘着面を温めながら(50℃程度)貼り付けることで、強力に貼り付けることができます。
雨天時はどうしても、貼り付け面が湿ってしまいます。ドライヤーを使用できない場合は、晴れた日に作業を行ってください。
寒冷時にドライヤーをお使いになれない環境の場合には、バックドアを閉めた状態で車のヒーターを稼働させて、バックドアの表面温度が、できれば20℃以上になっている状態にしてから 作業されることをお勧めします。
▼使用している粘着テープについて
バックドア側アンカーとホールドテープの粘着材は、高性能な粘着テープですが、その性能を発揮させるには、
・接着する面へのしっかりとした脱脂
・十分な加圧(5kgf/㎠) → 強い指圧をするくらいの押し付け力
・十分な養生時間
が必要です。
スリーエムジャパン株式会社様が公開している
「3M VHB 接着マニュアル」
をできればご一読ください。
気温が20℃以上あり、乾燥した状況下での作業が望ましいです。
寒冷時や多湿時等は、ドライヤー(家庭用のものでOKです)を使用してください。
↓↓
ドライヤーを使い、貼り付ける箇所とテープの粘着面を温めながら(50℃程度)貼り付けることで、強力に貼り付けることができます。
雨天時はどうしても、貼り付け面が湿ってしまいます。ドライヤーを使用できない場合は、晴れた日に作業を行ってください。
寒冷時にドライヤーをお使いになれない環境の場合には、バックドアを閉めた状態で車のヒーターを稼働させて、バックドアの表面温度が、できれば20℃以上になっている状態にしてから 作業されることをお勧めします。
▼使用している粘着テープについて
バックドア側アンカーとホールドテープの粘着材は、高性能な粘着テープですが、その性能を発揮させるには、
・接着する面へのしっかりとした脱脂
・十分な加圧(5kgf/㎠) → 強い指圧をするくらいの押し付け力
・十分な養生時間
が必要です。
スリーエムジャパン株式会社様が公開している
「3M VHB 接着マニュアル」
をできればご一読ください。
1.バックドアのアンカーやホールドテープの貼り付ける面をしっかりと脱脂処理する
ウェザーストリップモールがバックドア側に当たる部分の内側にテープとアンカーを貼り付けますので、それらを貼り付ける場所の周辺を広めにしっかりと脱脂処理してください。
(ウェザーストリップモールについては、上で記載した【各部名称】や 4-1.ウェザーストリップモールの取り外し を参照ください)
脱脂処理する場所は下画像の赤で記したあたりです。



1-1.脱脂処理をする
貼り付ける部分に、カーワックスの成分などが残っていると、粘着材はしっかりと貼りつきません。パーツクリーナーやベンジンなどを使って、しっかりと脱脂処理してください。
バックドアの左右とも脱脂処理をしてください。
脱脂作業のコツ
※ パーツクリーナーなどで濡らしながら、ティッシュで ”磨くイメージ” で拭く。
(1枚の布で前端だけ溶剤を含ませ、後半分は乾いた状態で、一方向に拭くのは良い方法です。)
※ 拭き取り方は一方向とし、往復や丸く拭かない。
※ 拭き取る紙や布は汚れの無い物を使用し、常に新しい面で拭う拭う。(汚れた面で拭くと、汚れをただのばしているだけになってしまします。)
(1枚の布で前端だけ溶剤を含ませ、後半分は乾いた状態で、一方向に拭くのは良い方法です。)
※ 拭き取り方は一方向とし、往復や丸く拭かない。
※ 拭き取る紙や布は汚れの無い物を使用し、常に新しい面で拭う拭う。(汚れた面で拭くと、汚れをただのばしているだけになってしまします。)
ご注意下さい
ボディコーティングがされている場合
ボディコーティングされていると、上述の脱脂処理では不十分で、粘着材がしっかりと貼り付きません。コーティング被膜を研摩材で磨き落とすなどの作業が必要となります。 また、最近の洗車用シャンプーの中には、ワックス成分やコーティング成分が配合されていて、汚れを落とすのと同時にボディに艶を出してくれる製品があります。ワックス成分やコーティング成分が残っておりますと、しっかりとテープが貼り付きません。貼り付け面を確実に下処理するために、コンパウンド(ノンシリコンタイプがお勧めです)や1200~1500番くらいの耐水ペーパーや 研磨スポンジで磨き落とします。貼り付け面だけを磨き落とせるように、貼り付け面以外の箇所をマスキング処理をしてから磨き作業をされることをお勧めします。
下画像では ガムテープでマスキングをしておいて、研磨スポンジ(3M マイクロファイン)で 貼り付け面を 軽く磨いています。

各種のクリーナーを使って作業する場合
ガラスクリーナーやプラスチッククリーナーなどには、汚れを落とす成分の他に、汚れが再度付着することを防止する成分が含まれている場合が多いです。この汚れ付着防止成分(シリコンやワックス等)が表面に残っていると粘着材がしっかりと貼り付いてくれません。また 汚れ付着防止成分(シリコンやワックスなど)が残っている部分に一度貼り付けてしまいますと、汚れ付着防止成分が粘着材側にも移行しますので、再使用することができません。新しい粘着テープを使う必要があります。各種のクリーナーなどを使って作業をされた場合には 汚れ付着防止成分が表面に残らないよう、クリーナーを使用後に入念な脱脂処理してください。
ボディコーティングされていると、上述の脱脂処理では不十分で、粘着材がしっかりと貼り付きません。コーティング被膜を研摩材で磨き落とすなどの作業が必要となります。 また、最近の洗車用シャンプーの中には、ワックス成分やコーティング成分が配合されていて、汚れを落とすのと同時にボディに艶を出してくれる製品があります。ワックス成分やコーティング成分が残っておりますと、しっかりとテープが貼り付きません。貼り付け面を確実に下処理するために、コンパウンド(ノンシリコンタイプがお勧めです)や1200~1500番くらいの耐水ペーパーや 研磨スポンジで磨き落とします。貼り付け面だけを磨き落とせるように、貼り付け面以外の箇所をマスキング処理をしてから磨き作業をされることをお勧めします。
下画像では ガムテープでマスキングをしておいて、研磨スポンジ(3M マイクロファイン)で 貼り付け面を 軽く磨いています。

各種のクリーナーを使って作業する場合
ガラスクリーナーやプラスチッククリーナーなどには、汚れを落とす成分の他に、汚れが再度付着することを防止する成分が含まれている場合が多いです。この汚れ付着防止成分(シリコンやワックス等)が表面に残っていると粘着材がしっかりと貼り付いてくれません。また 汚れ付着防止成分(シリコンやワックスなど)が残っている部分に一度貼り付けてしまいますと、汚れ付着防止成分が粘着材側にも移行しますので、再使用することができません。新しい粘着テープを使う必要があります。各種のクリーナーなどを使って作業をされた場合には 汚れ付着防止成分が表面に残らないよう、クリーナーを使用後に入念な脱脂処理してください。
1-2.脱脂状態を確認する
脱脂作業が終りましたら、ホールドテープを貼る前に脱脂が十分にできているかの確認をしてください。脱脂作業をした箇所に、テストピース(小さな試し貼りテープ)を貼ってみてください。
▼貼った上から強く指圧をするくらいの力で数秒間加圧してください。
5分ほど経過させたのち剥がそうとしてみてください。
▼ガムテープを貼ったときのように、剥がすのに抵抗感があるようでしたらOKです。
▼さほどの抵抗感なく剥がれてくるようですと、脱脂が十分にできていませんので、再度脱脂作業を行ってください。
2. 貼り付け面にプライマー処理をする
貼り付け部周辺に付属のプライマーを必ず塗ってください。
プライマーによる下地処理をすることで、テープをより強固に接着させることができます。
下画像の車は別の車種ですが、作業内容は同じです。ご了承ください。
小さく折りたたんだ(3~4cm四方)テッシュに、小瓶に入っているプライマー液を浸み込ませながら、塗装面を拭くようにしていただければOKです。




プライマー液は十分な量が入っていますが少量ですので こぼさないようにご注意ください。
続けて反対側(助手席側)にもプライマーを塗ってください。10分ほど乾燥させたのちに次の「手順3」へ進んでください。

3.バックドア側アンカーとバックドア側ホールドテープを貼り付ける
作業の前準備として、テープやアンカーを貼り付ける位置を今一度ご確認ください。
テープの貼り直しはできませんのでご注意ください。

3-1.バックドア側アンカーを貼り付ける
まず、バックドア下部に、バックドア側アンカーを貼り付けます。アンカーの貼り付け強度はとても重要です。
この部分だけでもドライヤーで、貼り付け面と粘着材の両方を十分に暖めながら貼り付けるようにしてください。
貼り付け位置は、下の図を参考にしてください。位置は厳密でなくとも、おおむね画像と同じような位置でかまいません。
下画像は全て運転席側です。助手席側も同様に貼ってください。
下画像の「× 印」をつけたあたりを向く角度にアンカーを傾けて貼ります。
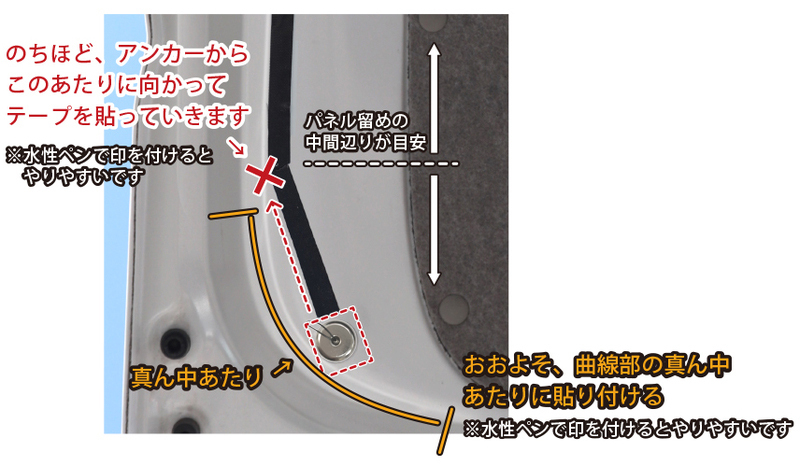
↓2024年8月23日出荷以前の「磁石タイプアンカー」の注意点です

貼り付けた後で、空気を抜くようにシッカリと圧着させてください。指圧をするイメージです。
画像は全て運転席側です。助手席側も同様に貼ってください。
失敗してしまった場合の対処方法
貼り付け後、数秒~数十秒経過すると まともには剥がせません。
※貼り直しをする場合、貼り付けたテープは とても強力に接着されていて剥がしとるにも大変ですが、石油系溶剤を用いると剥がしやすいです。下記blogを参考にしてください。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9665705.html
鉄板にアンカーをビス止めする方法もあります。
磁石真ん中の黒色部品を外すとクリップ金具が外せますので、ビス止めができます。
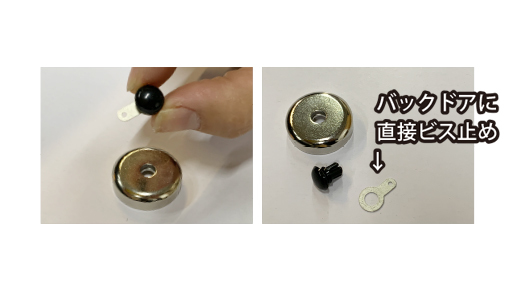
ビス止めの際は、こちらのブログを参考にしてください
↓↓↓
https://aizurv2.hamazo.tv/e9815961.html
※貼り直しをする場合、貼り付けたテープは とても強力に接着されていて剥がしとるにも大変ですが、石油系溶剤を用いると剥がしやすいです。下記blogを参考にしてください。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9665705.html
鉄板にアンカーをビス止めする方法もあります。
磁石真ん中の黒色部品を外すとクリップ金具が外せますので、ビス止めができます。
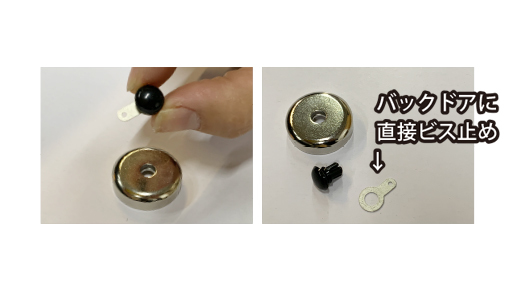
ビス止めの際は、こちらのブログを参考にしてください
↓↓↓
https://aizurv2.hamazo.tv/e9815961.html
3-2.バックドア側ホールドテープを貼り付ける
テープは、ウェザーストリップモールがバックドア側に当たる部分の内側に貼り付けます。※手順1をご参照下さい。
テープも貼り直しはできません、ほぼ一発勝負ですので貼り付け作業の前準備として、テープを貼り付ける位置を 今一度確認したうえで貼り始めてください。
貼り付けてから、数秒経過すると まともには剥がせませんので ご注意ください もし、貼り直しをせざるを得ない場合には、元の粘着材は、使えない状態になっているかと思います。その場合は、いったん使えない状態部分の粘着材をはがし取っていただき(石油系溶剤を用いると剥がしやすいです)市販の両面テープ(高耐熱仕様のテープが少量で販売されています)を貼り直してから、再度貼り付けていただくか、弊社ホームページで販売中の補修用のテープをお使いください。https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/168
作業のポイント
寒い日や、雨の日には ドライヤーを使いながらの作業をお勧めします。貼り付け面と粘着材の両方を温めながら(40~50℃)貼り付けていきます。


ホールドテープは、バックドア側アンカーのすぐそばから貼り始めます。曲線部分はシワ(ひだ)になっても問題ありません。(テープの上にタープ布が接合されるのでシワは隠れます)

プレスラインの内側に沿って貼り進めていきます

テープの長さ分、全部を貼ってください。あとから 余った部分をハサミで切り落とすこともできます。なお、切らずにそのまま残しても機能的には問題ありません。
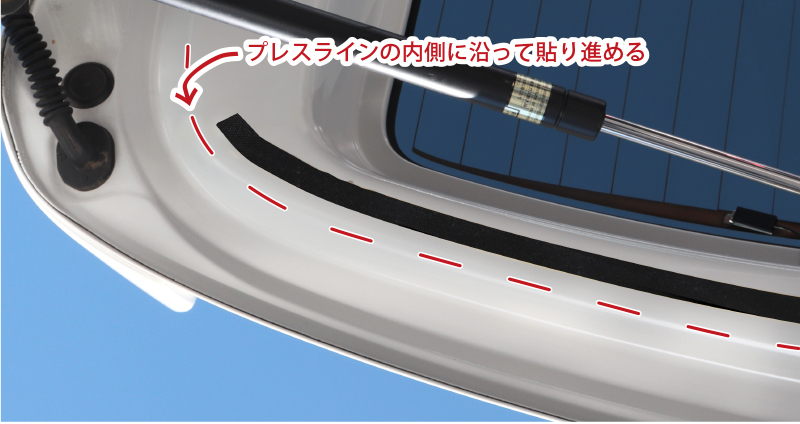
貼り終えた全体図です↓
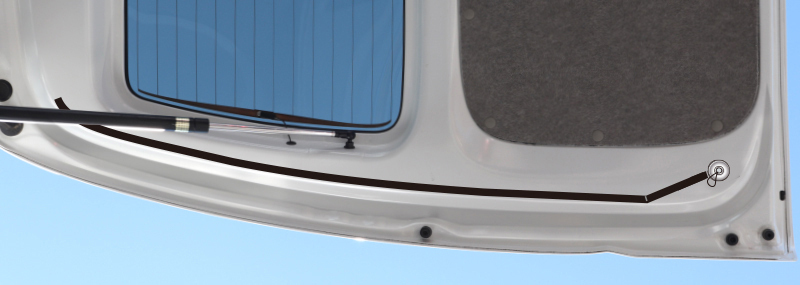
3-3 十分に加圧する
上から しっかりとテープを押し付けてください。
「貼り付けたテープが剥がれてきてしまった・・・」 の原因には、この加圧が 不十分だった ことによる場合が 少なくありません。業者さんでも、「貼り付けて おしまい」 にしてしまう場合もあります・・・粘着テープは「感圧接着剤」とも呼ばれていて、圧力を加えないと 十分な接着力(粘着力)を発揮しません。高性能なテープほど しっかりと圧力を加える必要があります。テープの上から 1㎝ごとに 指圧をするつもりで加圧していってください。特に アンカーと、ホールドテープの一番下側のアンカー付近と、一番上側の端部付近は、入念に押し付けてください。
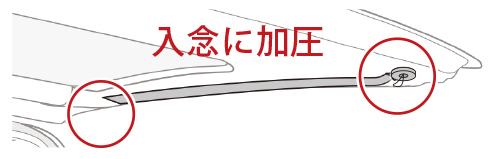

繰り返しになりますが、「テープを単に貼っただけでは、剥がれてきてしまいます。しっかりと押し付けてください」
4.ボディー側アンカーを取り付ける

4-1.ウェザーストリップモールの取り外し
まず、ウェザーストリップモールを後方に引き出して外します。


下部はこの辺りから、上部はこの辺りまで外しておきます。

4-2.取り付け位置の確認
次に、車体中央を基準にボディー側アンカーを取り付けますので位置を確認してください。ドアロック金具の中央から、爪付きクリップの内側までが56cmあたりの位置に取り付けます。

4-3.アンカーの打ち込み
※画像は違う車種のものですが、行う作業内容と手順は同じです。
ループ紐の付いた短いテープを、爪付きクリップを使って鉄板に固定します。テープの端と鉄板の端を合わせるようにします。

先に、テープを爪付きクリップに差し込んでから
この時アンカーの端を、車外側へ5ミリほどはみ出させて固定してください↓

ハンマーを使って奥までしっかりと打ち込みます。引っ張っても抜けてこなければOKです。

5. ボディー側ホールドテープを装着する
まず動画をご覧いただき、装着イメージをつかんでください。
下の動画では、キャンピング架装されている車に、付属の「爪付きクリップ」を利用ながら、ホールドテープと網戸も一緒に装着しています。ホールドテープだけを装着する場合にありましても、付属の「爪付きクリップ」を利用することで、確実な装着ができます。
その1、
その2、下側付近は、引き出されようとする力がより強く働きます。「爪付きクリップ」を細かく打ち込んで、入念に固定しています
その3 市販されている、網戸のファスナーを開閉する際に、網戸の下部が モールから抜け出さないように「爪付きクリップ」で補強しています。
動画内で使っている「爪付きアンカー」は、製品に10個 付属させています。追加でお求めいただくこともできます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport
↑
アイズ-ブロッカーのタブをクリックし、表示されたメーカー一覧から車種をご選択ください
作業前に ウェザーストリップの鉄芯の状態を確認してください。
CHECK!
ウェザーストリップの鉄芯が開いている(溝に隙間ができている状態)場合は(布地を内張りしているキャンピングカーや、バックドアに網戸を付けている車などに 多く見受けられます)
手で鉄芯を閉じて、溝に隙間がない状態にしてから、ボディ側ホールドテープを差し込んでください。鉄芯(溝)が開いたままだと、ウェザーストリップモールが外れやすいです。
特に、ボディー側アンカー付近は、ウェザーストリップモールが外れる方向に力が、他の部位よりも加わりますので、しっかりと鉄芯が閉じている状態(溝の隙間がない状態)で 元通りに戻し入れてください。
◎ 鉄芯が閉じている(溝の隙間がない状態)

✖ 鉄芯が開いている(溝に隙間ができている状態)

鉄芯を手で閉じて、溝に隙間がない状態にしてから 装着してください。

なお、布地を内張りしているキャンピングカーなどでは、鉄芯(溝)を閉じた状態で、戻し入れるのが困難だったりします。その場合には、鉄芯(溝)を開いた状態で ホールドテープを差し入れながら ウェザーストリップモールをボディ側に元通りに戻し入れ、戻し入れた後から、プライヤーなどを使って しっかりと鉄芯を締めて、ウェザーストリップモールが抜けてこないようにします。
手で鉄芯を閉じて、溝に隙間がない状態にしてから、ボディ側ホールドテープを差し込んでください。鉄芯(溝)が開いたままだと、ウェザーストリップモールが外れやすいです。
特に、ボディー側アンカー付近は、ウェザーストリップモールが外れる方向に力が、他の部位よりも加わりますので、しっかりと鉄芯が閉じている状態(溝の隙間がない状態)で 元通りに戻し入れてください。
◎ 鉄芯が閉じている(溝の隙間がない状態)

✖ 鉄芯が開いている(溝に隙間ができている状態)

鉄芯を手で閉じて、溝に隙間がない状態にしてから 装着してください。

なお、布地を内張りしているキャンピングカーなどでは、鉄芯(溝)を閉じた状態で、戻し入れるのが困難だったりします。その場合には、鉄芯(溝)を開いた状態で ホールドテープを差し入れながら ウェザーストリップモールをボディ側に元通りに戻し入れ、戻し入れた後から、プライヤーなどを使って しっかりと鉄芯を締めて、ウェザーストリップモールが抜けてこないようにします。
それでは、ボディ側ホールドテープを装着していきます。テープは長さが異なる2種類のテープが付属されています。
5-1.長いホールドテープを取り付ける起点を決める
まず長いテープから装着を行います。装着は装着は、上側曲線部の中央付近から装着し始めます。厳密でなくても、おおよそで大丈夫です。

テープの装着始点部分に 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定します。

5-2.下側に向かってホールドテープを装着していく
■ 装着要領■
①ウェザーストリップモールの溝にボディー側ホールドテープの幅の狭いほうを差し込みます。

②テープを差し込んだ状態のまま、元通りにボディーの鉄板へ はめ込みます。

この作業をすこしずつ繰り返して装着していきます。
※所々に、テープの装着始点部分で使った 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定することで、テープがズレるのを防いで装着がしやすくなります。
上の動画でも使っていますので ご確認ください。
お間違いのないように注意
※注意1:テープはV字に折ってあり、折り幅の狭い方をウェザーストリップモールの溝に差し込みます
※注意2:テープを差し込む場所を間違えないように気を付けてください ↓

※注意2:テープを差し込む場所を間違えないように気を付けてください ↓

下側へ向かってテープ全てを装着していってください。
差し込んだら…

しっかりと手のひらで叩き込む

ウェザーストリップモールを車外側から見てみると、シッカリ奥まで入っているかの判断がつきます。
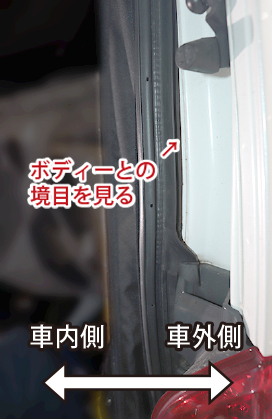
画像のようにベロ(ひだ)が付いている場合はめくって確認します。

↓ 隙間があるので、モールが奥まで入っておらずダメです。モールがシッカリ奥まで入っていれば隙間はありません。

5-3.長いテープにつなげて、短いホールドテープを取り付ける
※以下の画像は違う車種のものですが、行う作業内容と手順は同じです。
長いテープの下端に、短いテープの端を5ミリほど重ねてから、


重ねた部分を「爪付きクリップ」で固定します。


短いテープの中間あたりも「爪付きクリップ」で固定します

ボディー側アンカーに5ミリほど重なるようにカットし…


重ねた付近を「爪付きクリップ」で固定します

5-4.ウェザーストリップモールをハンマーで打ち込む
ウェザーストリップモールの上から ハンマーで 奥いっぱいまで打ちこみます。この作業が大事です。
軽い力で奥まで打ち込めるのですが、一部でも打ち込みが甘いと、ウェザーストリップモールが浮き上がっていることで バックドアの閉まりが悪くなってしまいます。
しっかりと打ち込まれているかの判断は、目視では難しいので 打ち込んでいるときに出る音や、感触で判断します。
★鈍い音・柔らかな感触 → 高い音・硬い感触 になっていればOKです
アイズ-ブロッカーを装着後「バックドアの閉まりが固くなった」感じがする場合には上記のウェザーストリップモールの浮き上がりを再度確認してください。
※特に上側あたりに浮き上がりがあると 閉まり具合への影響が大きいですので、上側は入念にチェックしてください。
6. タープ布を取り付ける
=================================
養生時間を経過させてください。
ホールドテープを装着後、1時間以上、できれば3時間ほど養生時間が経過していることを確認してください。その間に バックドア側に貼ったテープの接着力が増し、本来の性能の80%ほどの接着力になります。
夏場の晴れた日の作業でしたら、テープを貼って シッカリと加圧ができていれば 1時間後には大丈夫な接着強度になっていたりしますが、できるだけ上記の養生時間を経てから タープ布を装着してください。特に寒冷時や雨の日の作業では 十分な養生時間を経過させてください。
=================================
6-1.タープ布の判別
タープ布の車外側になる面には撥水加工処理を行っていますので、以下の方法で車外側を判別し、間違えないように装着してください。
▼タープ布の 運転席側/助手席側 の判別方法▼
運転席側の車内側だけに緑色のAizuのタグがついています。

※最新のタグはコチラ

▼装着時の目印▼
左右のタープ布とも、車内側になる面には薄茶色の面ファスナーが付いています。
これがバックドアの上部(首元)へ来るように装着してください。
(装着終了後は取り外してください)

6-2.ショックコードの接合
タープ布の「袖口(上側)」と「足元(下側)」から出ているショックコードの端部に付いているフックをバックドア側アンカーとボディー側アンカーのそれぞれに接合します。
▼ボディー側アンカーへ▼
アンカーから出ている紐をループ状に広げておき、接合します。接合後はフックの開きを閉じ、タグを取り外してください。先の細いプライヤーで作業するとつなげやすいです。


▼バックドア側アンカーへ▼
☆2024年8月23日以降に出荷した製品の場合
さきほどの反対側から出ているフックを、紐につなげてからフックの開きを閉じてください。


☆2024年8月23日以前に出荷した製品の場合
さきほどの反対側から出ているフックを、リップ(薄い板)の穴につなげてからフックの開きを閉じてください。


ショックコードを接合し終えバックドアを全開にすると、このような状態になり ます。

6-3.タープ布の接合
タープ布をホールドテープに接合していきます。①~⑩の順に取り付けを行ってください。
▼まず①~⑤です▼
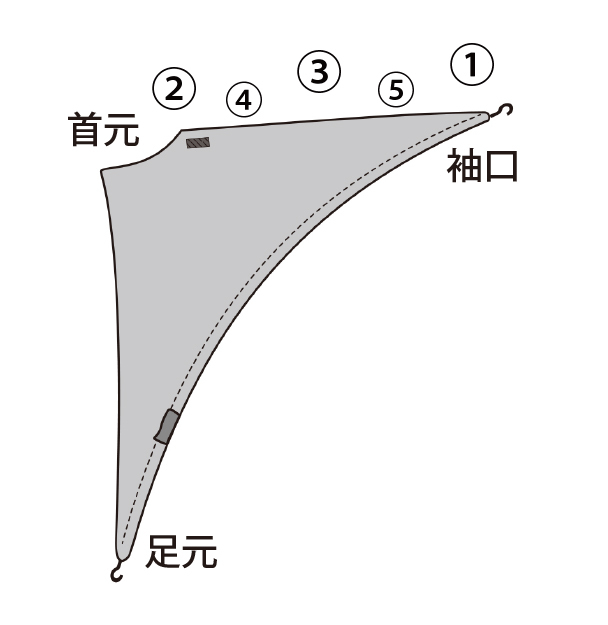
①.アンカー側端部(袖口)を接合します。
端部から15cmほど接合します。

②.反対側の端部(首元)を接合します。
15cmほど接合します。タープ布は伸縮性の高い生地ですので1.2倍ほどに伸びます。
強く引き伸ばしていただいても大丈夫です。

③.次に真ん中あたりを接合します。
5cmほど接合します。この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの④と⑤の辺りを、シワが無いように接合します。
▼次に⑥~⑩です▼

⑥.ボディー側の端部(首元)を接合します。
15cmほど接合します。
バックドア側と同様に、生地を引き伸ばして接合します。
その際に、首元ありのタープ布に張り感が出るように、なおかつあまり張りすぎない程度に接合してください。
ホールドテープの終端部とタープ布の終端部は、一致しません。テープの方が少し(1~2cm)余り気味になるはずです。余ったテープはのちほど切り取れますし、そのまま残しても問題ありません。

この辺りに適度な張り感
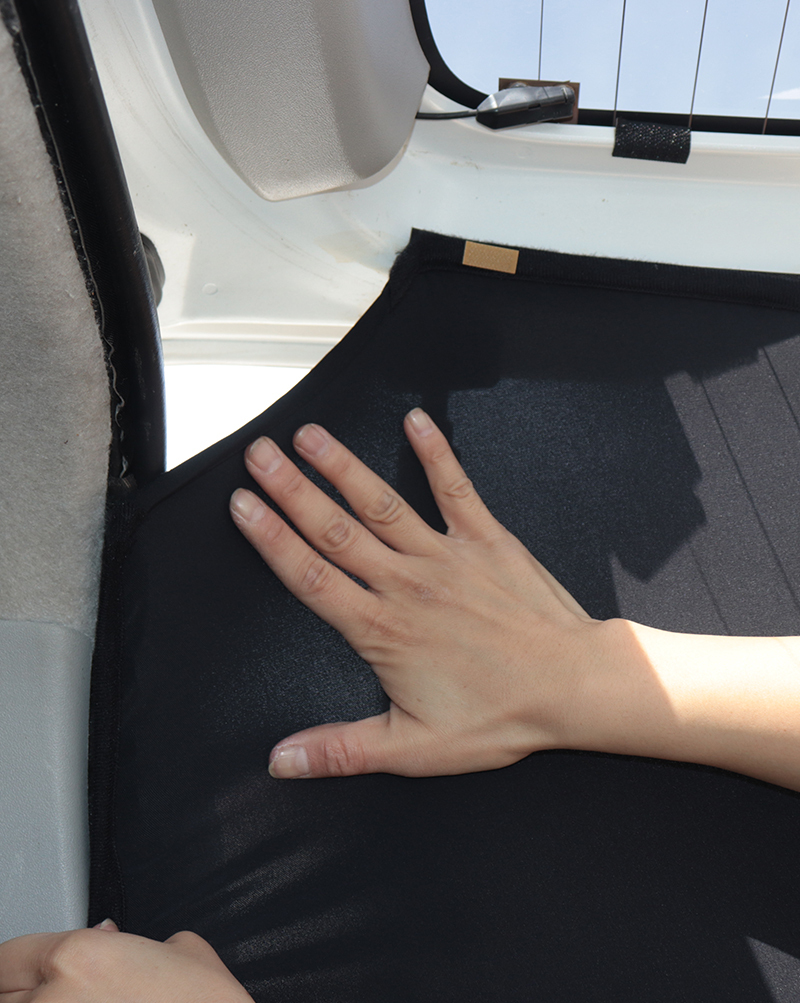
↑※この部分の張りが強すぎますと、バックドアを引き下げる力が強く働き ドアが全開位置に保持しずらくなります。張りが強すぎる場合には、上側方向に装着位置をずらしていく(ボディ側とバックドア側との距離を縮める)ことで 張り具合を 弱めることができます。
⑦.下側端部(足元)を接合します。
端部から15cmほど接合します。

⑧.次に真ん中あたりを接合します。
5cmほど接合します。
この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの⑨と⑩の辺りを、シワが無いように接合します。
※もしこの時点でシワが無くキレイに張れていれば、次の「手順7-1」は飛ばしてもらっても構いません※
7. 貼り具合を調整します
7-1.タープ布の調整
シワっ気が 残るようでしたら、何度も 剥がしては接合を繰り返して 貼り直してみてください。
テープ接合を剥がすには、タープ布の内側と外側の両方から 行うとやりやすいです。
シワが出ないようにするコツとしては、生地の一部に たるみが出ないように タープ布の接合部全体にわたって、 同じような引っ張り加減にすることです。
おおむね シワが取れました。
7-2.タープ布を強く接合する
具合よく張っている状態が確認できたら、タープ布とバックドア側、タープ布とボディー側の 各ホールドテープとの接合部を しっかりと押さえて、接合を強くします


7-3.はみ出しているテープの処理
もし 上側端部のホールドテープが余っているようでしたら、ハサミで切り取って整えて下さい。なお、切らなくても機能的には問題ありません。
↓バックドア側(まっすぐ切ります)

↓ボディー側(角の部分は丸く切っておくと安全です)

8. バックドアの閉まり具合をご確認ください
バックドアを閉めてみてください。
閉まり具合が 装着前よりも固く感じるようでしたら、5-4 の「ウェザーストリップモールの浮き上がり」を 再度 確認してください。
パッと見では浮き上がりがないように見えても、ハンマーでたたいてみると 鈍い音がする場合もあります。
特に上部はわずかな浮きでも閉まり具合に影響します。(下部はさほどの影響はありません)
タープ布が はさまれないか を ご確認ください。
バックドアを勢いよく閉めようとすると、車内の空気が車外側へと流される際にタープ布も外側に出されてしまい、タープ布がドアに挟まれやすくなります。特に、バックドアに網戸を装着していたり、キャンピング架装車などで 後端部に収納棚等が装備されていたりすると、車内空気を排出する為のダクトの通気量が少なくなっている(あるいはなくなっている)ことで その作用が出やすいです。バックドアをゆっくり閉めるようにしてみてください。あるいは 少しご面倒ですが、スライドドアや小窓等を開けた状態でバックドアを閉めると、空気の逃げ道ができることでタープ布が挟まれにくいだけでなく、バックドアの閉まり具合が劇的に軽くなります。ぜひ お試しください。
バックドアが元通りの全開状態になるかどうかを、ご確認ください。
・バックドアダンパーが経年劣化で反力が弱まっていると、アイズ-ブロッカーを装着されたことで、ドアが全開しなくなる場合もありますし、もし「強化ダンパー」などに交換されていると、ドアの開口具合が純正状態よりも、より開く仕様になっている場合もあります。
・バックドアを開けた後端の高さが、純正状態よりも10cmほどの高さまでは、タープ布は追随できるようになっていますが、張りが強すぎる部分があると、全開にならなかったり、ウェザーストリップモールが引き出される場合があります。
★タープ布に、張りすぎ感があるようでしたら、タープ布の上部付近を上側方向に移動させてみて下さい。
取り付け方法のご案内は、以上となります。
============================
■バックドア側のホールドテープが剥がれてきてしまう場合について
バックドア側のホールドテープは 最下部の曲線部が一番 剥がれようとする力が働きます。 「この部分だけが剥がれてしまった・・・」場合には、剥がれた部分だけを貼り直すことで補修ができます。20cm+20cm(合計40cm)の長さのホールドテープ と、下地処理用のプライマーを、補修用品として用意しています。
他にも、各種補修部品を下記ページにて ご購入いただけます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/168
============================
■そのほかの ご使用上のご注意につきましては こちら をご確認ください。
============================
最後になりますが、
ご使用上で 気になることが ございましたら ご報告いただけますと
今後の改良などへと つなげることができて、ありがたく存じます。
弊社レビュー投稿ページはコチラにあります。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/reviewlist
どうぞ よろしくお願いいたします。
株式会社 アイズ
アイズ-ブロッカー 開発・製作担当者 一同
TEL 053-422-7608
FAX 053-422-7178
info@aizu-rv.co.jp
============================
アイズ-ブロッカーは、 特許取得済です(特許第6862023)
また、上記説明書の営利目的利用はご遠慮下さい。(©aizu2021)
よろしくお願いいたします。
2024年03月08日
2024年3月1日以降 アトレー・ハイゼットカーゴ 他(S700系)アイズ-ブロッカー取付説明書
アトレーワゴン, ハイゼット カーゴ (S700系) アイズ-ブロッカー取付説明書
(特許第6862023)
2024年3月1日以降に出荷した製品の装着方法となります。
※2024年08月23日以降に出荷した製品から、付属の「磁石アンカー」の仕様が変更になっています。
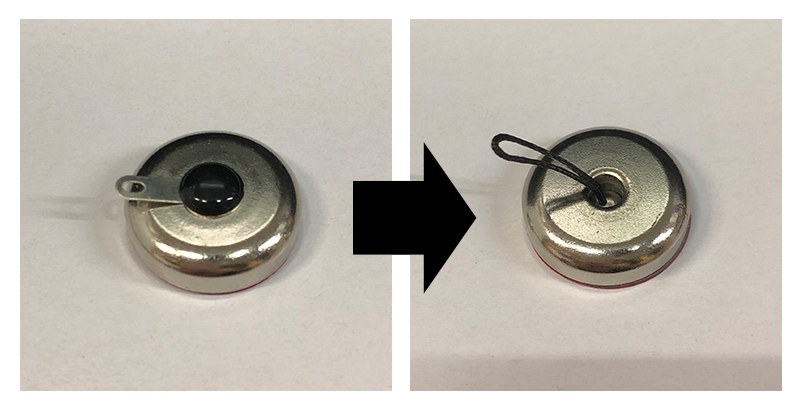


===================
【必要工具類】
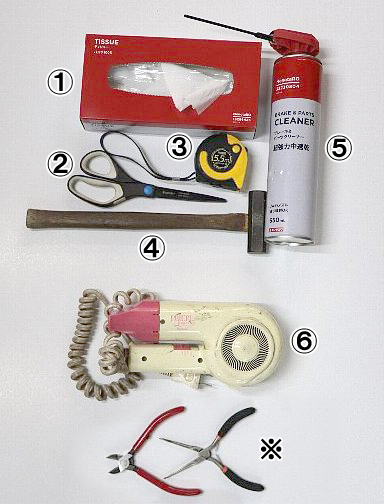
①:テッシュ
②:ハサミ
③:メジャー
④:ハンマーの類(フツーのトンカチでokです)
⑤:パーツクリーナーの類(脱脂処理に使用します。ベンジンなどの石油系溶剤がお勧めです。シンナーなどの溶剤は塗装面を痛めます)
⑥:ドライヤー(寒冷時や多湿の場合に使用)
※先の細いプライヤーやペンチの類
※水性ペン
※踏み台
があると便利です。
===================
【商品内容】を ご確認ください。

①:アイズ-ブロッカー本体タープ布:左右2枚(ショックコード付き)
※運転席側のタープ布には、緑色の「Aizuのタグ」が縫い付けています。助手席側にはタグはありません。
②:バックドア側ホールドテープ:2本
③:脱脂確認用 ためし貼りテープ:2枚
④:バックドア側アンカー(磁石タイプ):2個
⑤:バックドア側ホールドテープ用プライマー液:1 個
⑥:ボディー側ホールドテープ
長いテープ:2本(ボディー上側に使用)
短いテープ:2本(ボディー下側に使用・切り込み付き)
⑦:ボディー側ホールドテープ固定用 爪付きクリップ:10個
⑧:ボディー側アンカー
紐付きの短いテープ状のもの:2個 + 爪付きクリップ 小2個付き
以上、8点です
===================
【各部の名称】です。
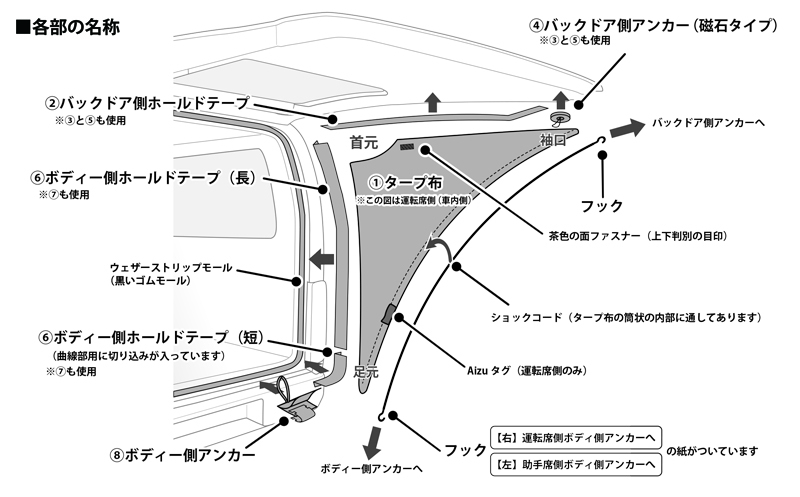
【作業時間】
作業自体は約1時間ほどですが、粘着材貼付け後に最低1時間(できれば3時間)以上、養生時間をおいてください。
【作業環境について】
粘着材貼付け作業には、気温が20℃以上、乾燥した状況下が望ましいです。寒冷時や雨天等の多湿時等は、ドライヤー(家庭用のものでOKです)を使用しながら作業をしてください。
気温が15℃以下の気温下では、十分な貼り付け強度が実現しない可能性があります。
家庭用のヘアードライヤーでOKですので、粘着面と貼り付け面との両方を40℃くらいに温めながらの作業をお勧めします。ヘアードライヤーなどが使えない作業環境の場合には、 車のリヤヒーターを稼働させてバックドアの貼り付け面をできるだけ温めておき、テープ自体も温めた状態にしておいてからの貼り付け作業が よろしいかと存じます。
【装着作業の流れ】
■1.バックドアの脱脂(コーティング剤の磨き落とし処理が必要な場合もあります)と プライマー塗布を行う
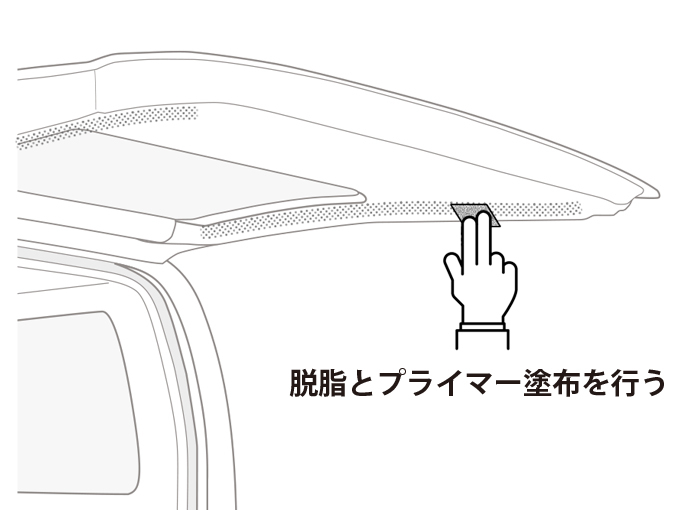
■2.バックドアにアンカー(磁石タイプ)とホールドテープを貼り付ける

■3.ボディーにアンカーとホールドテープを装着する。
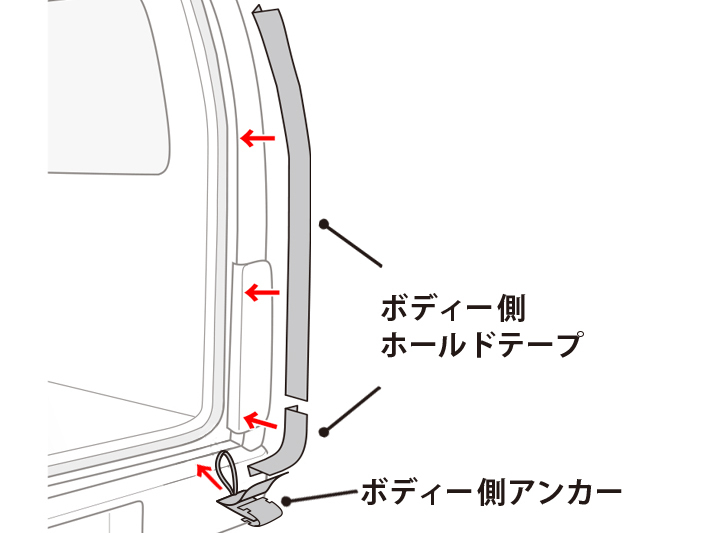
※次のタープ布を取り付ける前に、最低1時間(できれば3時間)以上、養生時間をおいてください。養生中に粘着材の接着力が増します。
■4.タープ布を取り付ける。

■5.タープ布の貼り具合を調整して、ドアの閉まり具合を確認する。
このブログや取付け説明書を、最後までお読みいただいたうえで作業を開始してください。
以下、取り付けの詳細手順です。
==========================
1.バックドアのアンカーやホールドテープの貼り付ける面をしっかりと脱脂処理する
ウェザーストリップモールがバックドア側に当たる部分の内側にテープとアンカーを貼り付けますので、それらを貼り付ける場所の周辺を広めにしっかりと脱脂処理してください。
(ウェザーストリップモールについては、上で記載した【各部名称】や 4-1.ウェザーストリップモールの取り外し を参照ください)
脱脂処理する場所は下画像の赤で記したあたりです。


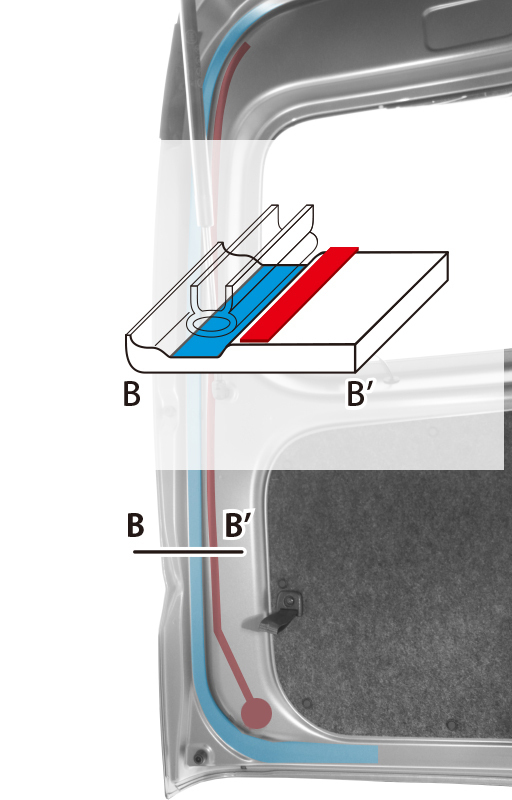
1-1.脱脂処理をする
貼り付ける部分に、カーワックスの成分などが残っていると、粘着材はしっかりと貼りつきません。パーツクリーナーやベンジンなどを使って、しっかりと脱脂処理してください。
バックドアの左右とも脱脂処理をしてください。



1-2.脱脂状態を確認する
脱脂作業が終りましたら、ホールドテープを貼る前に脱脂が十分にできているかの確認をしてください。脱脂作業をした箇所に、テストピース(小さな試し貼りテープ)を貼ってみてください。
▼貼った上から強く指圧をするくらいの力で数秒間加圧してください。

5分ほど経過させたのち剥がそうとしてみてください。
▼ガムテープを貼ったときのように、剥がすのに抵抗感があるようでしたらOKです。

▼さほどの抵抗感なく剥がれてくるようですと、脱脂が十分にできていませんので、再度脱脂作業を行ってください。

2. 貼り付け面にプライマー処理をする
貼り付け部周辺に付属のプライマーを必ず塗ってください。
プライマーによる下地処理をすることで、テープをより強固に接着させることができます。
下画像の車は別車種ですが、作業内容は同じです。ご了承ください。
小さく折りたたんだ(3~4cm四方)テッシュに、小瓶に入っているプライマー液を浸み込ませながら、

脱脂済みの貼り付け面を拭くようにして プライマー液を塗布します。

プライマー液を こぼさないようにご注意ください。


続けて反対側(助手席側)にもプライマーを塗ってください。10分ほど乾燥させたのちに次の「手順3」へ進んでください。

3.バックドア側アンカーとバックドア側ホールドテープを貼り付ける
作業の前準備として、テープやアンカーを貼り付ける位置を今一度ご確認ください。
テープの貼り直しはできませんのでご注意ください。

3-1.バックドア側アンカーを貼り付ける
まず、バックドア下部に、バックドア側アンカーを貼り付けます。アンカーの貼り付け強度はとても重要です。
この部分だけでもドライヤーで、貼り付け面と粘着材の両方を十分に暖めながら貼り付けるようにしてください。
貼り付け位置は、下の図を参考にしてください。位置は厳密でなくとも、おおむね画像と同じような位置でかまいません。
下画像は全て運転席側です。助手席側も同様に貼ってください。
下画像の「× 印」をつけたあたりを向く角度にアンカーを傾けて貼ります。


↓2024年8月23日出荷以前の「磁石タイプアンカー」の注意点です

貼り付けた後で、空気を抜くようにシッカリと圧着させてください。指圧をするイメージです。
画像は全て運転席側です。助手席側も同様に貼ってください。
3-2.バックドア側ホールドテープを貼り付ける
テープは、ウェザーストリップモールがバックドア側に当たる部分の内側に貼り付けます。※手順1をご参照下さい。
テープも貼り直しはできません、ほぼ一発勝負ですので貼り付け作業の前準備として、テープを貼り付ける位置を 今一度確認したうえで貼り始めてください。
貼り付けてから、数秒経過すると まともには剥がせませんので ご注意ください もし、貼り直しをせざるを得ない場合には、元の粘着材は、使えない状態になっているかと思います。その場合は、いったん使えない状態部分の粘着材をはがし取っていただき(石油系溶剤を用いると剥がしやすいです)市販の両面テープ(高耐熱仕様のテープが少量で販売されています)を貼り直してから、再度貼り付けていただくか、弊社ホームページで販売中の補修用のテープをお使いください。https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/653
ホールドテープは、バックドア側アンカーのすぐそばから貼り始めます。曲線部分はシワ(ひだ)になっても問題ありません。(テープの上にタープ布が接合されるのでシワは隠れます)

プレスラインの内側に沿って貼り進めていきます

テープの長さ分、全部を貼ってください。あとから 余った部分をハサミで切り落とすこともできます。なお、切らずにそのまま残しても機能的には問題ありません。
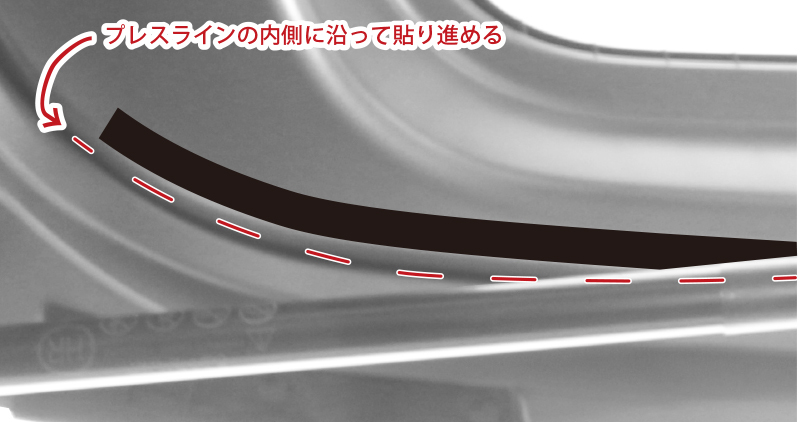
貼り終えた全体図です↓

3-3 十分に加圧する
上から しっかりとテープを押し付けてください。
「貼り付けたテープが剥がれてきてしまった・・・」 の原因には、この加圧が 不十分だった ことによる場合が 少なくありません。業者さんでも、「貼り付けて おしまい」 にしてしまう場合もあります・・・粘着テープは「感圧接着剤」とも呼ばれていて、圧力を加えないと 十分な接着力(粘着力)を発揮しません。高性能なテープほど しっかりと圧力を加える必要があります。テープの上から 1㎝ごとに 指圧をするつもりで加圧していってください。特に アンカーと、ホールドテープの一番下側のアンカー付近と、一番上側の端部付近は、入念に押し付けてください。
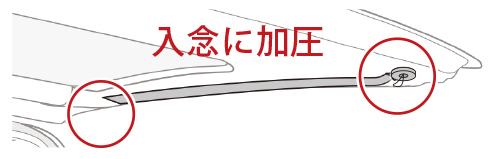

繰り返しになりますが、「テープを単に貼っただけでは、剥がれてきてしまいます。しっかりと押し付けてください」


4.ボディー側アンカーを取り付ける

4-1.ウェザーストリップモールの取り外し
まず、ウェザーストリップモールを後方に引き出して外します。

下部はこの辺りから

上部はこの辺りまで外しておきます。

4-2.取り付け位置の確認
次に、車体中央を基準にボディー側アンカーを取り付けますので位置を確認してください。ドアロック金具の中央から、爪付きクリップの内側までが57cmあたりの位置に取り付けます。


4-3.アンカーの打ち込み
※画像は違う車種のものですが、行う作業内容と手順は同じです。
ループ紐の付いた短いテープを、爪付きクリップを使って鉄板に固定します。テープの端と鉄板の端を合わせるようにします。

先に、テープを爪付きクリップに差し込んでから
この時アンカーの端を、車外側へ5ミリほどはみ出させて固定してください↓

ハンマーを使って奥までしっかりと打ち込みます。引っ張っても抜けてこなければOKです。

5. ボディー側ホールドテープを装着する
まず動画をご覧いただき、装着イメージをつかんでください。
下の動画では、キャンピング架装されている車に、付属の「爪付きクリップ」を利用ながら、ホールドテープと網戸も一緒に装着しています。ホールドテープだけを装着する場合にありましても、付属の「爪付きクリップ」を利用することで、確実な装着ができます。
その1、
その2、下側付近は、引き出されようとする力がより強く働きます。「爪付きクリップ」を細かく打ち込んで、入念に固定しています
その3 市販されている、網戸のファスナーを開閉する際に、網戸の下部が モールから抜け出さないように「爪付きクリップ」で補強しています。
動画内で使っている「爪付きアンカー」は、製品に10個 付属させています。追加でお求めいただくこともできます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport
↑
アイズ-ブロッカーのタブをクリックし、表示されたメーカー一覧から車種をご選択ください
作業前に ウェザーストリップの鉄芯の状態を確認してください。
それでは、ボディ側ホールドテープを装着していきます。テープは長さが異なる2種類のテープが付属されています。
5-1.長いホールドテープを取り付ける起点を決める
まず長いテープから装着を行います。装着は装着は、上側曲線部の中央付近から装着し始めます。厳密でなくても、おおよそで大丈夫です。

テープの装着始点部分に 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定します。

5-2.下側に向かってホールドテープを装着していく
■ 装着要領■
①ウェザーストリップモールの溝にボディー側ホールドテープの幅の狭いほうを差し込みます。

②テープを差し込んだ状態のまま、元通りにボディーの鉄板へ はめ込みます。

この作業をすこしずつ繰り返して装着していきます。
※所々に、テープの装着始点部分で使った 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定することで、テープがズレるのを防いで装着がしやすくなります。
上の動画でも使っていますので ご確認ください。
下側へ向かってテープ全てを装着していってください。
差し込んだら…

しっかりと手のひらで叩き込む

ウェザーストリップモールを車外側から見てみると、シッカリ奥まで入っているかの判断がつきます。
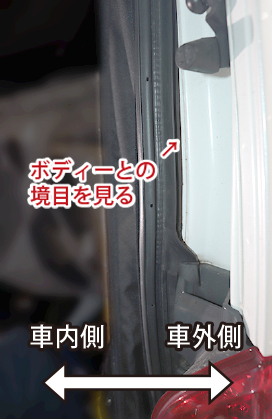
画像のようにベロ(ひだ)が付いている場合はめくって確認します。

↓ 隙間があるので、モールが奥まで入っておらずダメです。モールがシッカリ奥まで入っていれば隙間はありません。

5-3.長いテープにつなげて、短いホールドテープを取り付ける
※以下の画像は違う車種のものですが、行う作業内容と手順は同じです。
長いテープの下端に、短いテープの端を5ミリほど重ねてから、


重ねた部分を「爪付きクリップ」で固定します。


短いテープの中間あたりも「爪付きクリップ」で固定します

ボディー側アンカーに5ミリほど重なるようにカットし…


重ねた付近を「爪付きクリップ」で固定します

5-4.ウェザーストリップモールをハンマーで打ち込む
ウェザーストリップモールの上から ハンマーで 奥いっぱいまで打ちこみます。この作業が大事です。
軽い力で奥まで打ち込めるのですが、一部でも打ち込みが甘いと、ウェザーストリップモールが浮き上がっていることで バックドアの閉まりが悪くなってしまいます。
しっかりと打ち込まれているかの判断は、目視では難しいので 打ち込んでいるときに出る音や、感触で判断します。
★鈍い音・柔らかな感触 → 高い音・硬い感触 になっていればOKです

アイズ-ブロッカーを装着後「バックドアの閉まりが固くなった」感じがする場合には上記のウェザーストリップモールの浮き上がりを再度確認してください。
※特に上側あたりに浮き上がりがあると 閉まり具合への影響が大きいですので、上側は入念にチェックしてください。
6. タープ布を取り付ける
=================================
養生時間を経過させてください。
ホールドテープを装着後、1時間以上、できれば3時間ほど養生時間が経過していることを確認してください。その間に バックドア側に貼ったテープの接着力が増し、本来の性能の80%ほどの接着力になります。
夏場の晴れた日の作業でしたら、テープを貼って シッカリと加圧ができていれば 1時間後には大丈夫な接着強度になっていたりしますが、できるだけ上記の養生時間を経てから タープ布を装着してください。特に寒冷時や雨の日の作業では 十分な養生時間を経過させてください。
=================================
6-1.タープ布の判別
タープ布の車外側になる面には撥水加工処理を行っていますので、以下の方法で車外側を判別し、間違えないように装着してください。
▼タープ布の 運転席側/助手席側 の判別方法▼
運転席側の車内側だけに緑色のAizuのタグがついています。

※最新のタグはコチラ

▼装着時の目印▼
左右のタープ布とも、車内側になる面には薄茶色の面ファスナーが付いています。
これがバックドアの上部(首元)へ来るように装着してください。
(装着終了後は取り外してください)

6-2.ショックコードの接合
タープ布の「袖口(上側)」と「足元(下側)」から出ているショックコードの端部に付いているフックをバックドア側アンカーとボディー側アンカーのそれぞれに接合します。
▼ボディー側アンカーへ▼
アンカーから出ている紐をループ状に広げておき、接合します。接合後はフックの開きを閉じ、タグを取り外してください。先の細いプライヤーで作業するとつなげやすいです。


▼バックドア側アンカーへ▼
☆2024年8月23日以降に出荷した製品の場合
さきほどの反対側から出ているフックを、紐につなげてからフックの開きを閉じてください。


☆2024年8月23日以前に出荷した製品の場合
さきほどの反対側から出ているフックを、リップ(薄い板)の穴につなげてからフックの開きを閉じてください。


ショックコードを接合し終えバックドアを全開にすると、このような状態になり ます。

6-3.タープ布の接合
タープ布をホールドテープに接合していきます。①~⑩の順に取り付けを行ってください。
▼まず①~⑤です▼
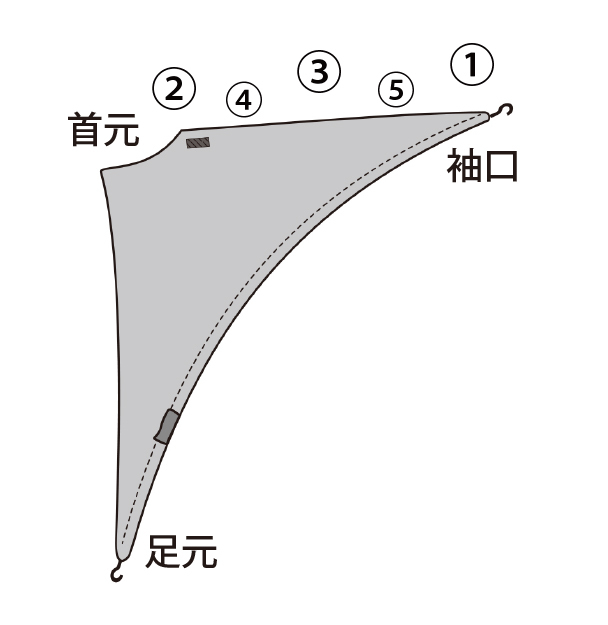
①.アンカー側端部(袖口)を接合します。
端部から15cmほど接合します。

②.反対側の端部(首元)を接合します。
15cmほど接合します。タープ布は伸縮性の高い生地ですので1.2倍ほどに伸びます。
強く引き伸ばしていただいても大丈夫です。

③.次に真ん中あたりを接合します。
5cmほど接合します。この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの④と⑤の辺りを、シワが無いように接合します。
▼次に⑥~⑩です▼

⑥.ボディー側の端部(首元)を接合します。
15cmほど接合します。
バックドア側と同様に、生地を引き伸ばして接合します。
その際に、首元ありのタープ布に張り感が出るように、なおかつあまり張りすぎない程度に接合してください。
ホールドテープの終端部とタープ布の終端部は、一致しません。テープの方が少し(1~2cm)余り気味になるはずです。余ったテープはのちほど切り取れますし、そのまま残しても問題ありません。

この辺りに適度な張り感
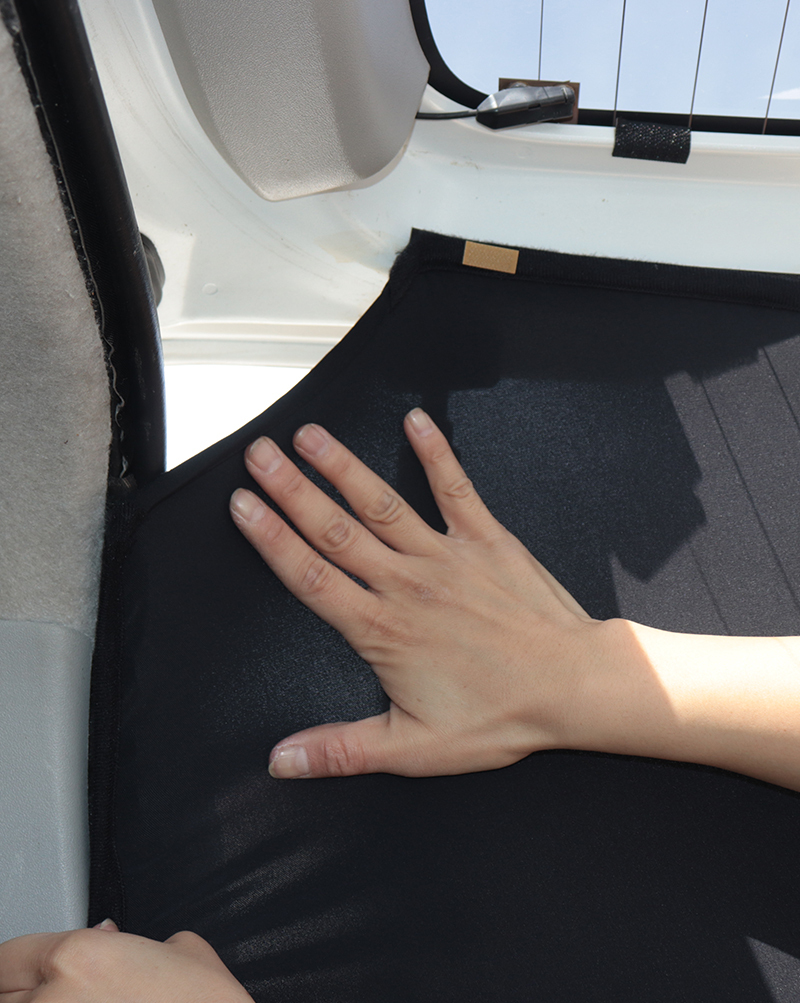
↑※この部分の張りが強すぎますと、バックドアを引き下げる力が強く働き ドアが全開位置に保持しずらくなります。張りが強すぎる場合には、上側方向に装着位置をずらしていく(ボディ側とバックドア側との距離を縮める)ことで 張り具合を 弱めることができます。
⑦.下側端部(足元)を接合します。
端部から15cmほど接合します。

⑧.次に真ん中あたりを接合します。
5cmほど接合します。
この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの⑨と⑩の辺りを、シワが無いように接合します。
※もしこの時点でシワが無くキレイに張れていれば、次の「手順7-1」は飛ばしてもらっても構いません※
7. 貼り具合を調整します
7-1.タープ布の調整
装着シワが出ないようにするコツとしては、生地の一部分だけに たるみが出ないように タープ布の接合部全体にわたって、 同じような引っ張り加減にすることです。
シワっ気が 残るようでしたら、何度も 剥がしては接合を繰り返して 貼り直してみてください。

テープ接合を剥がすには、タープ布の内側と外側の両方から 行うとやりやすいです。


おおむね シワが取れました。


7-2.タープ布を強く接合する
具合よく張っている状態が確認できたら、タープ布とバックドア側、タープ布とボディー側の 各ホールドテープとの接合部を しっかりと押さえて、接合を強くします


7-3.はみ出しているテープの処理
もし 上側端部のホールドテープが余っているようでしたら、ハサミで切り取って整えて下さい。なお、切らなくても機能的には問題ありません。
↓バックドア側(まっすぐ切ります)

↓ボディー側(角の部分は丸く切っておくと安全です)

8. バックドアの閉まり具合をご確認ください
バックドアを閉めてみてください。
閉まり具合が 装着前よりも固く感じるようでしたら、5-4 の「ウェザーストリップモールの浮き上がり」を 再度 確認してください。
パッと見では浮き上がりがないように見えても、ハンマーでたたいてみると 鈍い音がする場合もあります。
特に上部はわずかな浮きでも閉まり具合に影響します。(下部はさほどの影響はありません)

タープ布が はさまれないか を ご確認ください。
バックドアを勢いよく閉めようとすると、車内の空気が車外側へと流される際にタープ布も外側に出されてしまい、タープ布がドアに挟まれやすくなります。特に、バックドアに網戸を装着していたり、キャンピング架装車などで 後端部に収納棚等が装備されていたりすると、車内空気を排出する為のダクトの通気量が少なくなっている(あるいはなくなっている)ことで その作用が出やすいです。バックドアをゆっくり閉めるようにしてみてください。あるいは 少しご面倒ですが、スライドドアや小窓等を開けた状態でバックドアを閉めると、空気の逃げ道ができることでタープ布が挟まれにくいだけでなく、バックドアの閉まり具合が劇的に軽くなります。ぜひ お試しください。


バックドアが元通りの全開状態になるかどうかを、ご確認ください。
・バックドアダンパーが経年劣化で反力が弱まっていると、アイズ-ブロッカーを装着されたことで、ドアが全開しなくなる場合もありますし、もし「強化ダンパー」などに交換されていると、ドアの開口具合が純正状態よりも、より開く仕様になっている場合もあります。
・バックドアを開けた後端の高さが、純正状態よりも10cmほどの高さまでは、タープ布は追随できるようになっていますが、張りが強すぎる部分があると、全開にならなかったり、ウェザーストリップモールが引き出される場合があります。
★タープ布に、張りすぎ感があるようでしたら、タープ布の上部付近を上側方向に移動させてみて下さい。
取り付け方法のご案内は、以上となります。
============================
■バックドア側のホールドテープが剥がれてきてしまう場合について
バックドア側のホールドテープは 最下部の曲線部が一番 剥がれようとする力が働きます。 「この部分だけが剥がれてしまった・・・」場合には、剥がれた部分だけを貼り直すことで補修ができます。20cm+20cm(合計40cm)の長さのホールドテープ と、下地処理用のプライマーを、補修用品として用意しています。
他にも、各種補修部品を下記ページにて ご購入いただけます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/653
============================
■そのほかの ご使用上のご注意につきましては こちら をご確認ください。
============================
最後になりますが、
ご使用上で 気になることが ございましたら ご報告いただけますと
今後の改良などへと つなげることができて、ありがたく存じます。
弊社レビュー投稿ページはコチラにあります。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/reviewlist
どうぞ よろしくお願いいたします。
株式会社 アイズ
アイズ-ブロッカー 開発・製作担当者 一同
TEL 053-422-7608
FAX 053-422-7178
info@aizu-rv.co.jp
============================
アイズ-ブロッカーは、 特許取得済です(特許第6862023)
また、上記説明書の営利目的利用はご遠慮下さい。(©aizu2021)
よろしくお願いいたします。
(特許第6862023)
2024年3月1日以降に出荷した製品の装着方法となります。
※2024年08月23日以降に出荷した製品から、付属の「磁石アンカー」の仕様が変更になっています。
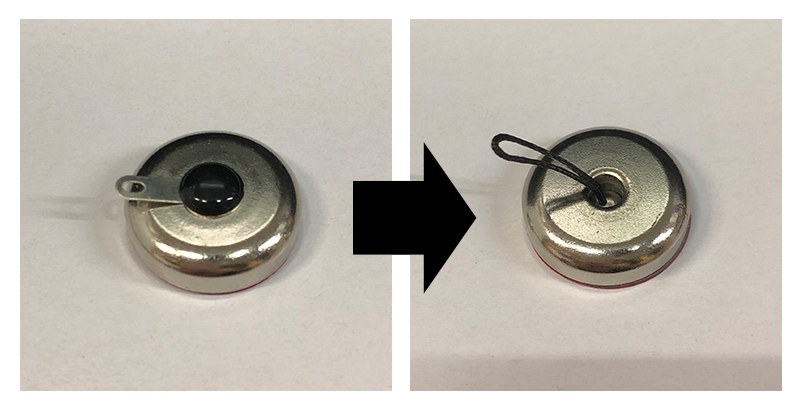
===================
【必要工具類】
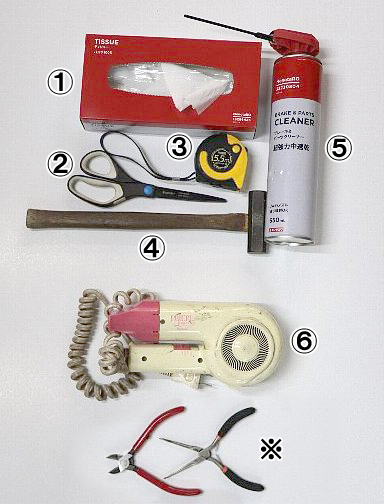
①:テッシュ
②:ハサミ
③:メジャー
④:ハンマーの類(フツーのトンカチでokです)
⑤:パーツクリーナーの類(脱脂処理に使用します。ベンジンなどの石油系溶剤がお勧めです。シンナーなどの溶剤は塗装面を痛めます)
⑥:ドライヤー(寒冷時や多湿の場合に使用)
※先の細いプライヤーやペンチの類
※水性ペン
※踏み台
があると便利です。
===================
【商品内容】を ご確認ください。

①:アイズ-ブロッカー本体タープ布:左右2枚(ショックコード付き)
※運転席側のタープ布には、緑色の「Aizuのタグ」が縫い付けています。助手席側にはタグはありません。
②:バックドア側ホールドテープ:2本
③:脱脂確認用 ためし貼りテープ:2枚
④:バックドア側アンカー(磁石タイプ):2個
⑤:バックドア側ホールドテープ用プライマー液:1 個
⑥:ボディー側ホールドテープ
長いテープ:2本(ボディー上側に使用)
短いテープ:2本(ボディー下側に使用・切り込み付き)
⑦:ボディー側ホールドテープ固定用 爪付きクリップ:10個
⑧:ボディー側アンカー
紐付きの短いテープ状のもの:2個 + 爪付きクリップ 小2個付き
以上、8点です
===================
【各部の名称】です。
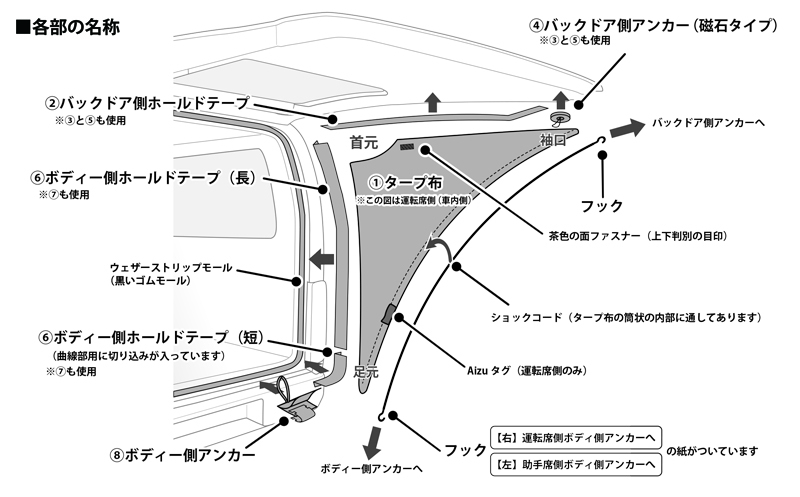
【作業時間】
作業自体は約1時間ほどですが、粘着材貼付け後に最低1時間(できれば3時間)以上、養生時間をおいてください。
【作業環境について】
粘着材貼付け作業には、気温が20℃以上、乾燥した状況下が望ましいです。寒冷時や雨天等の多湿時等は、ドライヤー(家庭用のものでOKです)を使用しながら作業をしてください。
気温が15℃以下の気温下では、十分な貼り付け強度が実現しない可能性があります。
家庭用のヘアードライヤーでOKですので、粘着面と貼り付け面との両方を40℃くらいに温めながらの作業をお勧めします。ヘアードライヤーなどが使えない作業環境の場合には、 車のリヤヒーターを稼働させてバックドアの貼り付け面をできるだけ温めておき、テープ自体も温めた状態にしておいてからの貼り付け作業が よろしいかと存じます。
【装着作業の流れ】
■1.バックドアの脱脂(コーティング剤の磨き落とし処理が必要な場合もあります)と プライマー塗布を行う
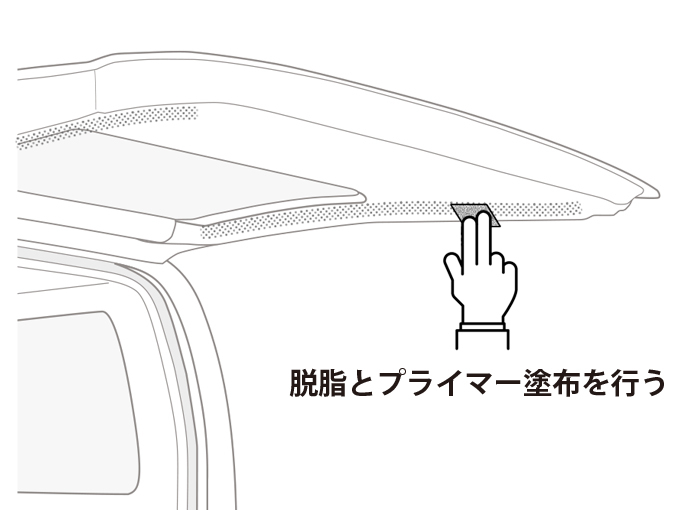
■2.バックドアにアンカー(磁石タイプ)とホールドテープを貼り付ける

■3.ボディーにアンカーとホールドテープを装着する。
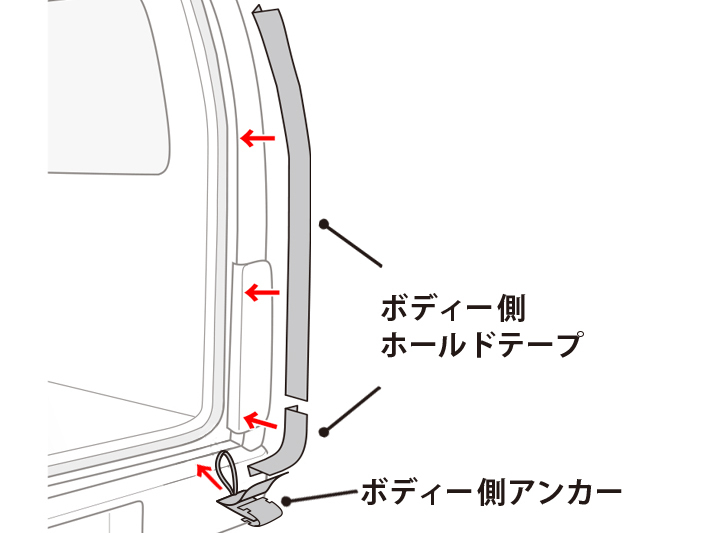
※次のタープ布を取り付ける前に、最低1時間(できれば3時間)以上、養生時間をおいてください。養生中に粘着材の接着力が増します。
■4.タープ布を取り付ける。

■5.タープ布の貼り具合を調整して、ドアの閉まり具合を確認する。
このブログや取付け説明書を、最後までお読みいただいたうえで作業を開始してください。
以下、取り付けの詳細手順です。
==========================
重要!!
▼作業時の温度・湿度について
気温が20℃以上あり、乾燥した状況下での作業が望ましいです。
寒冷時や多湿時等は、ドライヤー(家庭用のものでOKです)を使用してください。
↓↓
ドライヤーを使い、貼り付ける箇所とテープの粘着面を温めながら(50℃程度)貼り付けることで、強力に貼り付けることができます。
雨天時はどうしても、貼り付け面が湿ってしまいます。ドライヤーを使用できない場合は、晴れた日に作業を行ってください。
寒冷時にドライヤーをお使いになれない環境の場合には、バックドアを閉めた状態で車のヒーターを稼働させて、バックドアの表面温度が、できれば20℃以上になっている状態にしてから 作業されることをお勧めします。
▼使用している粘着テープについて
バックドア側アンカーとホールドテープの粘着材は、高性能な粘着テープですが、その性能を発揮させるには、
・接着する面へのしっかりとした脱脂
・十分な加圧(5kgf/㎠) → 強い指圧をするくらいの押し付け力
・十分な養生時間
が必要です。
スリーエムジャパン株式会社様が公開している
「3M VHB 接着マニュアル」
をできればご一読ください。
気温が20℃以上あり、乾燥した状況下での作業が望ましいです。
寒冷時や多湿時等は、ドライヤー(家庭用のものでOKです)を使用してください。
↓↓
ドライヤーを使い、貼り付ける箇所とテープの粘着面を温めながら(50℃程度)貼り付けることで、強力に貼り付けることができます。
雨天時はどうしても、貼り付け面が湿ってしまいます。ドライヤーを使用できない場合は、晴れた日に作業を行ってください。
寒冷時にドライヤーをお使いになれない環境の場合には、バックドアを閉めた状態で車のヒーターを稼働させて、バックドアの表面温度が、できれば20℃以上になっている状態にしてから 作業されることをお勧めします。
▼使用している粘着テープについて
バックドア側アンカーとホールドテープの粘着材は、高性能な粘着テープですが、その性能を発揮させるには、
・接着する面へのしっかりとした脱脂
・十分な加圧(5kgf/㎠) → 強い指圧をするくらいの押し付け力
・十分な養生時間
が必要です。
スリーエムジャパン株式会社様が公開している
「3M VHB 接着マニュアル」
をできればご一読ください。
1.バックドアのアンカーやホールドテープの貼り付ける面をしっかりと脱脂処理する
ウェザーストリップモールがバックドア側に当たる部分の内側にテープとアンカーを貼り付けますので、それらを貼り付ける場所の周辺を広めにしっかりと脱脂処理してください。
(ウェザーストリップモールについては、上で記載した【各部名称】や 4-1.ウェザーストリップモールの取り外し を参照ください)
脱脂処理する場所は下画像の赤で記したあたりです。


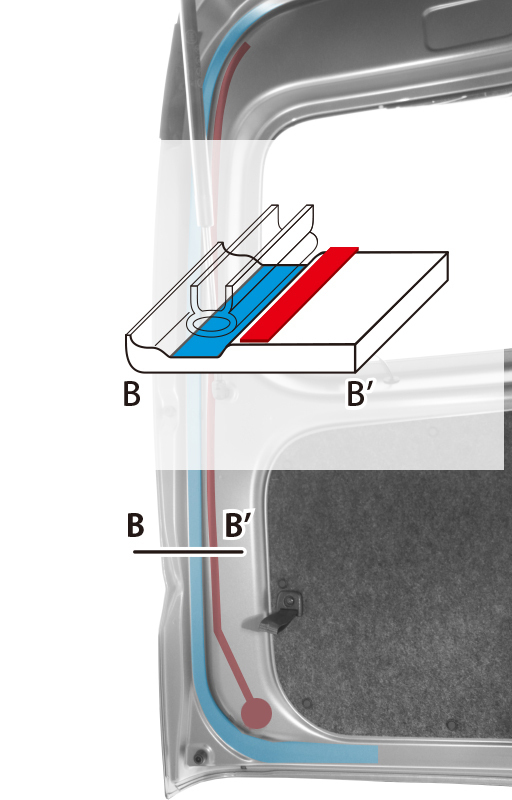
1-1.脱脂処理をする
貼り付ける部分に、カーワックスの成分などが残っていると、粘着材はしっかりと貼りつきません。パーツクリーナーやベンジンなどを使って、しっかりと脱脂処理してください。
バックドアの左右とも脱脂処理をしてください。
脱脂作業のコツ
※ パーツクリーナーなどで濡らしながら、ティッシュで ”磨くイメージ” で拭く。
(1枚の布で前端だけ溶剤を含ませ、後半分は乾いた状態で、一方向に拭くのは良い方法です。)
※ 拭き取り方は一方向とし、往復や丸く拭かない。
※ 拭き取る紙や布は汚れの無い物を使用し、常に新しい面で拭う拭う。(汚れた面で拭くと、汚れをただのばしているだけになってしまします。)
(1枚の布で前端だけ溶剤を含ませ、後半分は乾いた状態で、一方向に拭くのは良い方法です。)
※ 拭き取り方は一方向とし、往復や丸く拭かない。
※ 拭き取る紙や布は汚れの無い物を使用し、常に新しい面で拭う拭う。(汚れた面で拭くと、汚れをただのばしているだけになってしまします。)
ご注意下さい
ボディコーティングがされている場合
ボディコーティングされていると、上述の脱脂処理では不十分で、粘着材がしっかりと貼り付きません。コーティング被膜を研摩材で磨き落とすなどの作業が必要となります。 また、最近の洗車用シャンプーの中には、ワックス成分やコーティング成分が配合されていて、汚れを落とすのと同時にボディに艶を出してくれる製品があります。ワックス成分やコーティング成分が残っておりますと、しっかりとテープが貼り付きません。貼り付け面を確実に下処理するために、コンパウンド(ノンシリコンタイプがお勧めです)や1200~1500番くらいの耐水ペーパーや研磨スポンジで磨き落とします(キッチンなどで使うメラニンスポンジでも研磨できます)。貼り付け面だけを磨き落とせるように、貼り付け面以外の箇所をマスキング処理をしてから磨き作業をされることをお勧めします。
下画像では ガムテープでマスキングをしておいて、研磨スポンジ(3M マイクロファイン)で 貼り付け面を 軽く磨いています。

各種のクリーナーを使って作業する場合
ガラスクリーナーやプラスチッククリーナーなどには、汚れを落とす成分の他に、汚れが再度付着することを防止する成分が含まれている場合が多いです。この汚れ付着防止成分(シリコンやワックス等)が表面に残っていると粘着材がしっかりと貼り付いてくれません。また 汚れ付着防止成分(シリコンやワックスなど)が残っている部分に一度貼り付けてしまいますと、汚れ付着防止成分が粘着材側にも移行しますので、再使用することができません。新しい粘着テープを使う必要があります。各種のクリーナーなどを使って作業をされた場合には 汚れ付着防止成分が表面に残らないよう、クリーナーを使用後に入念な脱脂処理してください。
ボディコーティングされていると、上述の脱脂処理では不十分で、粘着材がしっかりと貼り付きません。コーティング被膜を研摩材で磨き落とすなどの作業が必要となります。 また、最近の洗車用シャンプーの中には、ワックス成分やコーティング成分が配合されていて、汚れを落とすのと同時にボディに艶を出してくれる製品があります。ワックス成分やコーティング成分が残っておりますと、しっかりとテープが貼り付きません。貼り付け面を確実に下処理するために、コンパウンド(ノンシリコンタイプがお勧めです)や1200~1500番くらいの耐水ペーパーや研磨スポンジで磨き落とします(キッチンなどで使うメラニンスポンジでも研磨できます)。貼り付け面だけを磨き落とせるように、貼り付け面以外の箇所をマスキング処理をしてから磨き作業をされることをお勧めします。
下画像では ガムテープでマスキングをしておいて、研磨スポンジ(3M マイクロファイン)で 貼り付け面を 軽く磨いています。

各種のクリーナーを使って作業する場合
ガラスクリーナーやプラスチッククリーナーなどには、汚れを落とす成分の他に、汚れが再度付着することを防止する成分が含まれている場合が多いです。この汚れ付着防止成分(シリコンやワックス等)が表面に残っていると粘着材がしっかりと貼り付いてくれません。また 汚れ付着防止成分(シリコンやワックスなど)が残っている部分に一度貼り付けてしまいますと、汚れ付着防止成分が粘着材側にも移行しますので、再使用することができません。新しい粘着テープを使う必要があります。各種のクリーナーなどを使って作業をされた場合には 汚れ付着防止成分が表面に残らないよう、クリーナーを使用後に入念な脱脂処理してください。
1-2.脱脂状態を確認する
脱脂作業が終りましたら、ホールドテープを貼る前に脱脂が十分にできているかの確認をしてください。脱脂作業をした箇所に、テストピース(小さな試し貼りテープ)を貼ってみてください。
▼貼った上から強く指圧をするくらいの力で数秒間加圧してください。
5分ほど経過させたのち剥がそうとしてみてください。
▼ガムテープを貼ったときのように、剥がすのに抵抗感があるようでしたらOKです。
▼さほどの抵抗感なく剥がれてくるようですと、脱脂が十分にできていませんので、再度脱脂作業を行ってください。
2. 貼り付け面にプライマー処理をする
貼り付け部周辺に付属のプライマーを必ず塗ってください。
プライマーによる下地処理をすることで、テープをより強固に接着させることができます。
下画像の車は別車種ですが、作業内容は同じです。ご了承ください。
小さく折りたたんだ(3~4cm四方)テッシュに、小瓶に入っているプライマー液を浸み込ませながら、

脱脂済みの貼り付け面を拭くようにして プライマー液を塗布します。

プライマー液を こぼさないようにご注意ください。


続けて反対側(助手席側)にもプライマーを塗ってください。10分ほど乾燥させたのちに次の「手順3」へ進んでください。

3.バックドア側アンカーとバックドア側ホールドテープを貼り付ける
作業の前準備として、テープやアンカーを貼り付ける位置を今一度ご確認ください。
テープの貼り直しはできませんのでご注意ください。

3-1.バックドア側アンカーを貼り付ける
まず、バックドア下部に、バックドア側アンカーを貼り付けます。アンカーの貼り付け強度はとても重要です。
この部分だけでもドライヤーで、貼り付け面と粘着材の両方を十分に暖めながら貼り付けるようにしてください。
貼り付け位置は、下の図を参考にしてください。位置は厳密でなくとも、おおむね画像と同じような位置でかまいません。
下画像は全て運転席側です。助手席側も同様に貼ってください。
下画像の「× 印」をつけたあたりを向く角度にアンカーを傾けて貼ります。


↓2024年8月23日出荷以前の「磁石タイプアンカー」の注意点です

貼り付けた後で、空気を抜くようにシッカリと圧着させてください。指圧をするイメージです。
画像は全て運転席側です。助手席側も同様に貼ってください。
失敗してしまった場合の対処方法
貼り付け後、数秒~数十秒経過すると まともには剥がせません。
※貼り直しをする場合、貼り付けたテープは とても強力に接着されていて剥がしとるにも大変ですが、石油系溶剤を用いると剥がしやすいです。下記blogを参考にしてください。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9665705.html
鉄板にアンカーをビス止めする方法もあります。
磁石真ん中の黒色部品を外すとクリップ金具が外せますので、ビス止めができます。
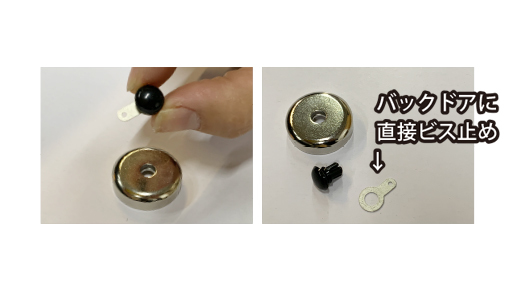
ビス止めの際は、こちらのブログを参考にしてください
↓↓↓
https://aizurv2.hamazo.tv/e9815961.html
※貼り直しをする場合、貼り付けたテープは とても強力に接着されていて剥がしとるにも大変ですが、石油系溶剤を用いると剥がしやすいです。下記blogを参考にしてください。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9665705.html
鉄板にアンカーをビス止めする方法もあります。
磁石真ん中の黒色部品を外すとクリップ金具が外せますので、ビス止めができます。
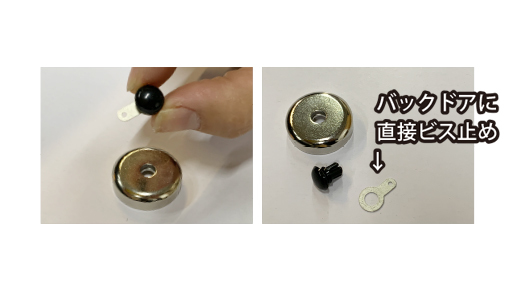
ビス止めの際は、こちらのブログを参考にしてください
↓↓↓
https://aizurv2.hamazo.tv/e9815961.html
3-2.バックドア側ホールドテープを貼り付ける
テープは、ウェザーストリップモールがバックドア側に当たる部分の内側に貼り付けます。※手順1をご参照下さい。
テープも貼り直しはできません、ほぼ一発勝負ですので貼り付け作業の前準備として、テープを貼り付ける位置を 今一度確認したうえで貼り始めてください。
貼り付けてから、数秒経過すると まともには剥がせませんので ご注意ください もし、貼り直しをせざるを得ない場合には、元の粘着材は、使えない状態になっているかと思います。その場合は、いったん使えない状態部分の粘着材をはがし取っていただき(石油系溶剤を用いると剥がしやすいです)市販の両面テープ(高耐熱仕様のテープが少量で販売されています)を貼り直してから、再度貼り付けていただくか、弊社ホームページで販売中の補修用のテープをお使いください。https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/653
作業のポイント
寒い日や、雨の日には ドライヤーを使いながらの作業をお勧めします。貼り付け面と粘着材の両方を温めながら(40~50℃)貼り付けていきます。


ホールドテープは、バックドア側アンカーのすぐそばから貼り始めます。曲線部分はシワ(ひだ)になっても問題ありません。(テープの上にタープ布が接合されるのでシワは隠れます)

プレスラインの内側に沿って貼り進めていきます

テープの長さ分、全部を貼ってください。あとから 余った部分をハサミで切り落とすこともできます。なお、切らずにそのまま残しても機能的には問題ありません。
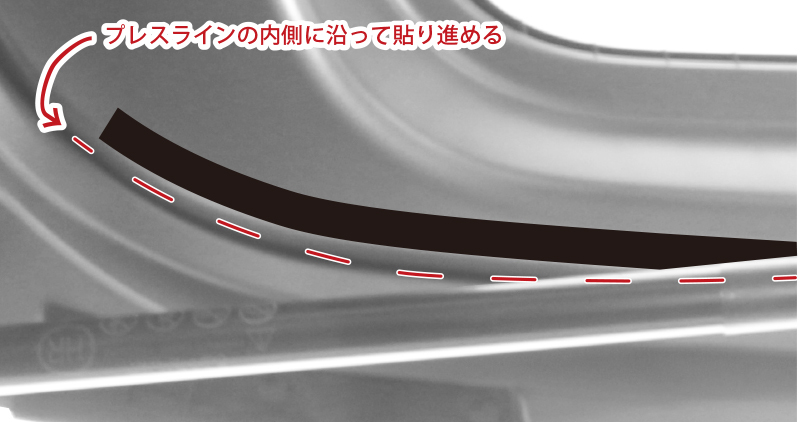
貼り終えた全体図です↓

3-3 十分に加圧する
上から しっかりとテープを押し付けてください。
「貼り付けたテープが剥がれてきてしまった・・・」 の原因には、この加圧が 不十分だった ことによる場合が 少なくありません。業者さんでも、「貼り付けて おしまい」 にしてしまう場合もあります・・・粘着テープは「感圧接着剤」とも呼ばれていて、圧力を加えないと 十分な接着力(粘着力)を発揮しません。高性能なテープほど しっかりと圧力を加える必要があります。テープの上から 1㎝ごとに 指圧をするつもりで加圧していってください。特に アンカーと、ホールドテープの一番下側のアンカー付近と、一番上側の端部付近は、入念に押し付けてください。
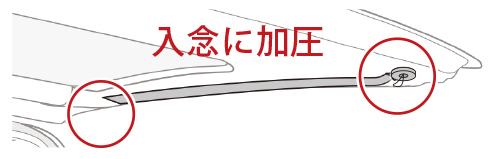

繰り返しになりますが、「テープを単に貼っただけでは、剥がれてきてしまいます。しっかりと押し付けてください」
4.ボディー側アンカーを取り付ける

4-1.ウェザーストリップモールの取り外し
まず、ウェザーストリップモールを後方に引き出して外します。

下部はこの辺りから

上部はこの辺りまで外しておきます。

4-2.取り付け位置の確認
次に、車体中央を基準にボディー側アンカーを取り付けますので位置を確認してください。ドアロック金具の中央から、爪付きクリップの内側までが57cmあたりの位置に取り付けます。


4-3.アンカーの打ち込み
※画像は違う車種のものですが、行う作業内容と手順は同じです。
ループ紐の付いた短いテープを、爪付きクリップを使って鉄板に固定します。テープの端と鉄板の端を合わせるようにします。

先に、テープを爪付きクリップに差し込んでから
この時アンカーの端を、車外側へ5ミリほどはみ出させて固定してください↓

ハンマーを使って奥までしっかりと打ち込みます。引っ張っても抜けてこなければOKです。

5. ボディー側ホールドテープを装着する
まず動画をご覧いただき、装着イメージをつかんでください。
下の動画では、キャンピング架装されている車に、付属の「爪付きクリップ」を利用ながら、ホールドテープと網戸も一緒に装着しています。ホールドテープだけを装着する場合にありましても、付属の「爪付きクリップ」を利用することで、確実な装着ができます。
その1、
その2、下側付近は、引き出されようとする力がより強く働きます。「爪付きクリップ」を細かく打ち込んで、入念に固定しています
その3 市販されている、網戸のファスナーを開閉する際に、網戸の下部が モールから抜け出さないように「爪付きクリップ」で補強しています。
動画内で使っている「爪付きアンカー」は、製品に10個 付属させています。追加でお求めいただくこともできます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport
↑
アイズ-ブロッカーのタブをクリックし、表示されたメーカー一覧から車種をご選択ください
作業前に ウェザーストリップの鉄芯の状態を確認してください。
CHECK!
ウェザーストリップの鉄芯が開いている(溝に隙間ができている状態)場合は(布地を内張りしているキャンピングカーや、バックドアに網戸を付けている車などに 多く見受けられます)
手で鉄芯を閉じて、溝に隙間がない状態にしてから、ボディ側ホールドテープを差し込んでください。鉄芯(溝)が開いたままだと、ウェザーストリップモールが外れやすいです。
特に、ボディー側アンカー付近は、ウェザーストリップモールが外れる方向に力が、他の部位よりも加わりますので、しっかりと鉄芯が閉じている状態(溝の隙間がない状態)で 元通りに戻し入れてください。
◎ 鉄芯が閉じている(溝の隙間がない状態)

✖ 鉄芯が開いている(溝に隙間ができている状態)

鉄芯を手で閉じて、溝に隙間がない状態にしてから 装着してください。

なお、布地を内張りしているキャンピングカーなどでは、鉄芯(溝)を閉じた状態で、戻し入れるのが困難だったりします。その場合には、鉄芯(溝)を開いた状態で ホールドテープを差し入れながら ウェザーストリップモールをボディ側に元通りに戻し入れ、戻し入れた後から、プライヤーなどを使って しっかりと鉄芯を締めて、ウェザーストリップモールが抜けてこないようにします。
手で鉄芯を閉じて、溝に隙間がない状態にしてから、ボディ側ホールドテープを差し込んでください。鉄芯(溝)が開いたままだと、ウェザーストリップモールが外れやすいです。
特に、ボディー側アンカー付近は、ウェザーストリップモールが外れる方向に力が、他の部位よりも加わりますので、しっかりと鉄芯が閉じている状態(溝の隙間がない状態)で 元通りに戻し入れてください。
◎ 鉄芯が閉じている(溝の隙間がない状態)

✖ 鉄芯が開いている(溝に隙間ができている状態)

鉄芯を手で閉じて、溝に隙間がない状態にしてから 装着してください。

なお、布地を内張りしているキャンピングカーなどでは、鉄芯(溝)を閉じた状態で、戻し入れるのが困難だったりします。その場合には、鉄芯(溝)を開いた状態で ホールドテープを差し入れながら ウェザーストリップモールをボディ側に元通りに戻し入れ、戻し入れた後から、プライヤーなどを使って しっかりと鉄芯を締めて、ウェザーストリップモールが抜けてこないようにします。
それでは、ボディ側ホールドテープを装着していきます。テープは長さが異なる2種類のテープが付属されています。
5-1.長いホールドテープを取り付ける起点を決める
まず長いテープから装着を行います。装着は装着は、上側曲線部の中央付近から装着し始めます。厳密でなくても、おおよそで大丈夫です。

テープの装着始点部分に 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定します。

5-2.下側に向かってホールドテープを装着していく
■ 装着要領■
①ウェザーストリップモールの溝にボディー側ホールドテープの幅の狭いほうを差し込みます。

②テープを差し込んだ状態のまま、元通りにボディーの鉄板へ はめ込みます。

この作業をすこしずつ繰り返して装着していきます。
※所々に、テープの装着始点部分で使った 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定することで、テープがズレるのを防いで装着がしやすくなります。
上の動画でも使っていますので ご確認ください。
お間違いのないように注意
※注意1:テープはV字に折ってあり、折り幅の狭い方をウェザーストリップモールの溝に差し込みます
※注意2:テープを差し込む場所を間違えないように気を付けてください ↓

※注意2:テープを差し込む場所を間違えないように気を付けてください ↓

下側へ向かってテープ全てを装着していってください。
差し込んだら…

しっかりと手のひらで叩き込む

ウェザーストリップモールを車外側から見てみると、シッカリ奥まで入っているかの判断がつきます。
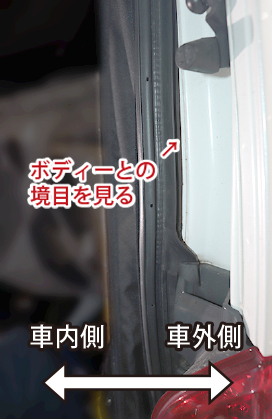
画像のようにベロ(ひだ)が付いている場合はめくって確認します。

↓ 隙間があるので、モールが奥まで入っておらずダメです。モールがシッカリ奥まで入っていれば隙間はありません。

5-3.長いテープにつなげて、短いホールドテープを取り付ける
※以下の画像は違う車種のものですが、行う作業内容と手順は同じです。
長いテープの下端に、短いテープの端を5ミリほど重ねてから、


重ねた部分を「爪付きクリップ」で固定します。


短いテープの中間あたりも「爪付きクリップ」で固定します

ボディー側アンカーに5ミリほど重なるようにカットし…


重ねた付近を「爪付きクリップ」で固定します

5-4.ウェザーストリップモールをハンマーで打ち込む
ウェザーストリップモールの上から ハンマーで 奥いっぱいまで打ちこみます。この作業が大事です。
軽い力で奥まで打ち込めるのですが、一部でも打ち込みが甘いと、ウェザーストリップモールが浮き上がっていることで バックドアの閉まりが悪くなってしまいます。
しっかりと打ち込まれているかの判断は、目視では難しいので 打ち込んでいるときに出る音や、感触で判断します。
★鈍い音・柔らかな感触 → 高い音・硬い感触 になっていればOKです
アイズ-ブロッカーを装着後「バックドアの閉まりが固くなった」感じがする場合には上記のウェザーストリップモールの浮き上がりを再度確認してください。
※特に上側あたりに浮き上がりがあると 閉まり具合への影響が大きいですので、上側は入念にチェックしてください。
6. タープ布を取り付ける
=================================
養生時間を経過させてください。
ホールドテープを装着後、1時間以上、できれば3時間ほど養生時間が経過していることを確認してください。その間に バックドア側に貼ったテープの接着力が増し、本来の性能の80%ほどの接着力になります。
夏場の晴れた日の作業でしたら、テープを貼って シッカリと加圧ができていれば 1時間後には大丈夫な接着強度になっていたりしますが、できるだけ上記の養生時間を経てから タープ布を装着してください。特に寒冷時や雨の日の作業では 十分な養生時間を経過させてください。
=================================
6-1.タープ布の判別
タープ布の車外側になる面には撥水加工処理を行っていますので、以下の方法で車外側を判別し、間違えないように装着してください。
▼タープ布の 運転席側/助手席側 の判別方法▼
運転席側の車内側だけに緑色のAizuのタグがついています。

※最新のタグはコチラ

▼装着時の目印▼
左右のタープ布とも、車内側になる面には薄茶色の面ファスナーが付いています。
これがバックドアの上部(首元)へ来るように装着してください。
(装着終了後は取り外してください)

6-2.ショックコードの接合
タープ布の「袖口(上側)」と「足元(下側)」から出ているショックコードの端部に付いているフックをバックドア側アンカーとボディー側アンカーのそれぞれに接合します。
▼ボディー側アンカーへ▼
アンカーから出ている紐をループ状に広げておき、接合します。接合後はフックの開きを閉じ、タグを取り外してください。先の細いプライヤーで作業するとつなげやすいです。


▼バックドア側アンカーへ▼
☆2024年8月23日以降に出荷した製品の場合
さきほどの反対側から出ているフックを、紐につなげてからフックの開きを閉じてください。


☆2024年8月23日以前に出荷した製品の場合
さきほどの反対側から出ているフックを、リップ(薄い板)の穴につなげてからフックの開きを閉じてください。


ショックコードを接合し終えバックドアを全開にすると、このような状態になり ます。

6-3.タープ布の接合
タープ布をホールドテープに接合していきます。①~⑩の順に取り付けを行ってください。
▼まず①~⑤です▼
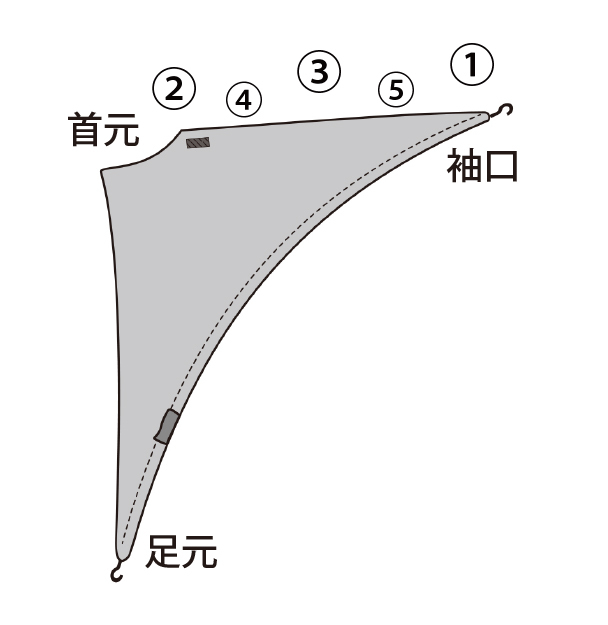
①.アンカー側端部(袖口)を接合します。
端部から15cmほど接合します。

②.反対側の端部(首元)を接合します。
15cmほど接合します。タープ布は伸縮性の高い生地ですので1.2倍ほどに伸びます。
強く引き伸ばしていただいても大丈夫です。

③.次に真ん中あたりを接合します。
5cmほど接合します。この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの④と⑤の辺りを、シワが無いように接合します。
▼次に⑥~⑩です▼

⑥.ボディー側の端部(首元)を接合します。
15cmほど接合します。
バックドア側と同様に、生地を引き伸ばして接合します。
その際に、首元ありのタープ布に張り感が出るように、なおかつあまり張りすぎない程度に接合してください。
ホールドテープの終端部とタープ布の終端部は、一致しません。テープの方が少し(1~2cm)余り気味になるはずです。余ったテープはのちほど切り取れますし、そのまま残しても問題ありません。

この辺りに適度な張り感
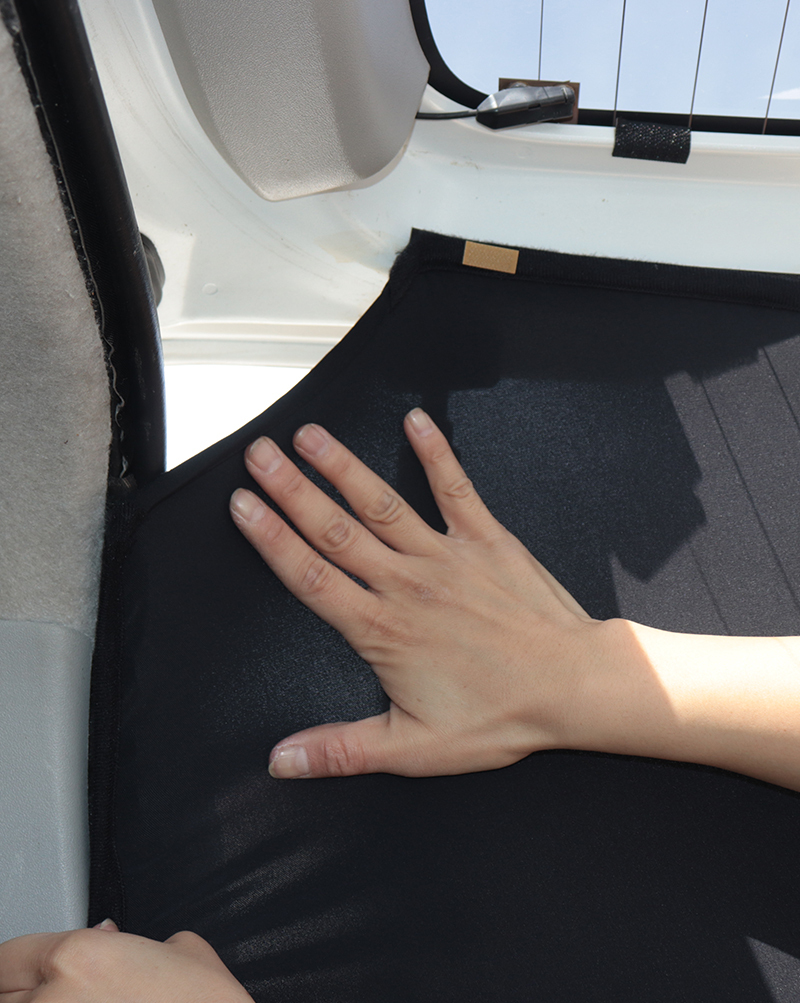
↑※この部分の張りが強すぎますと、バックドアを引き下げる力が強く働き ドアが全開位置に保持しずらくなります。張りが強すぎる場合には、上側方向に装着位置をずらしていく(ボディ側とバックドア側との距離を縮める)ことで 張り具合を 弱めることができます。
⑦.下側端部(足元)を接合します。
端部から15cmほど接合します。

⑧.次に真ん中あたりを接合します。
5cmほど接合します。
この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの⑨と⑩の辺りを、シワが無いように接合します。
※もしこの時点でシワが無くキレイに張れていれば、次の「手順7-1」は飛ばしてもらっても構いません※
7. 貼り具合を調整します
7-1.タープ布の調整
装着シワが出ないようにするコツとしては、生地の一部分だけに たるみが出ないように タープ布の接合部全体にわたって、 同じような引っ張り加減にすることです。
シワっ気が 残るようでしたら、何度も 剥がしては接合を繰り返して 貼り直してみてください。
テープ接合を剥がすには、タープ布の内側と外側の両方から 行うとやりやすいです。
おおむね シワが取れました。

7-2.タープ布を強く接合する
具合よく張っている状態が確認できたら、タープ布とバックドア側、タープ布とボディー側の 各ホールドテープとの接合部を しっかりと押さえて、接合を強くします


7-3.はみ出しているテープの処理
もし 上側端部のホールドテープが余っているようでしたら、ハサミで切り取って整えて下さい。なお、切らなくても機能的には問題ありません。
↓バックドア側(まっすぐ切ります)

↓ボディー側(角の部分は丸く切っておくと安全です)

8. バックドアの閉まり具合をご確認ください
バックドアを閉めてみてください。
閉まり具合が 装着前よりも固く感じるようでしたら、5-4 の「ウェザーストリップモールの浮き上がり」を 再度 確認してください。
パッと見では浮き上がりがないように見えても、ハンマーでたたいてみると 鈍い音がする場合もあります。
特に上部はわずかな浮きでも閉まり具合に影響します。(下部はさほどの影響はありません)
タープ布が はさまれないか を ご確認ください。
バックドアを勢いよく閉めようとすると、車内の空気が車外側へと流される際にタープ布も外側に出されてしまい、タープ布がドアに挟まれやすくなります。特に、バックドアに網戸を装着していたり、キャンピング架装車などで 後端部に収納棚等が装備されていたりすると、車内空気を排出する為のダクトの通気量が少なくなっている(あるいはなくなっている)ことで その作用が出やすいです。バックドアをゆっくり閉めるようにしてみてください。あるいは 少しご面倒ですが、スライドドアや小窓等を開けた状態でバックドアを閉めると、空気の逃げ道ができることでタープ布が挟まれにくいだけでなく、バックドアの閉まり具合が劇的に軽くなります。ぜひ お試しください。
バックドアが元通りの全開状態になるかどうかを、ご確認ください。
・バックドアダンパーが経年劣化で反力が弱まっていると、アイズ-ブロッカーを装着されたことで、ドアが全開しなくなる場合もありますし、もし「強化ダンパー」などに交換されていると、ドアの開口具合が純正状態よりも、より開く仕様になっている場合もあります。
・バックドアを開けた後端の高さが、純正状態よりも10cmほどの高さまでは、タープ布は追随できるようになっていますが、張りが強すぎる部分があると、全開にならなかったり、ウェザーストリップモールが引き出される場合があります。
★タープ布に、張りすぎ感があるようでしたら、タープ布の上部付近を上側方向に移動させてみて下さい。
取り付け方法のご案内は、以上となります。
============================
■バックドア側のホールドテープが剥がれてきてしまう場合について
バックドア側のホールドテープは 最下部の曲線部が一番 剥がれようとする力が働きます。 「この部分だけが剥がれてしまった・・・」場合には、剥がれた部分だけを貼り直すことで補修ができます。20cm+20cm(合計40cm)の長さのホールドテープ と、下地処理用のプライマーを、補修用品として用意しています。
他にも、各種補修部品を下記ページにて ご購入いただけます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/653
============================
■そのほかの ご使用上のご注意につきましては こちら をご確認ください。
============================
最後になりますが、
ご使用上で 気になることが ございましたら ご報告いただけますと
今後の改良などへと つなげることができて、ありがたく存じます。
弊社レビュー投稿ページはコチラにあります。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/reviewlist
どうぞ よろしくお願いいたします。
株式会社 アイズ
アイズ-ブロッカー 開発・製作担当者 一同
TEL 053-422-7608
FAX 053-422-7178
info@aizu-rv.co.jp
============================
アイズ-ブロッカーは、 特許取得済です(特許第6862023)
また、上記説明書の営利目的利用はご遠慮下さい。(©aizu2021)
よろしくお願いいたします。
2024年03月04日
ボディ側アンカーの補修方法 につきまして。
ボディ側アンカーの補修方法 をご案内申し上げます。
アイズ-ブロッカーのショックコード(ゴム紐)は、ボディ側アンカーの紐部分に固定されている状態です。
(下画像では、ウェザーストリップモール’(ゴムクッション材)を外した状態で撮影しています)

タープ布が強く押される(あるいは引っ張る)ようなことがあると、内臓されているショックコード(ゴム紐)が伸び切ってしまいます。
伸び切ってしまったあとは、ボディ側あるいはドア側のアンカー部分に直接の力が働くこととなり、ボディ側アンカーのループ紐が切れてしまったり、爪付きクリップが抜けたりの支障につながることがあります。
(下画像では、ループ紐が切れてしまった状態です)

そんな場合には、強めの糸を使うことで補修が可能です。

==========
補修方法のご案内です。
1)まず、ボディ側アンカーを固定している爪付きクリップ を抜き出して、ボディ側アンカーを外してしまいます。

2)画像のような 釣り糸など(PEラインですと十分な強度があります。100均ショップでも販売されています)を 輪っか状態を作ります。

3)輪っか状にした釣り糸を、爪付きクリップを再利用して固定します。


4)下画像のように、輪っか部分に ショックコード端部のフックをつないで、タープ布を元どうりに接合していただければ補修完了です。



===============
ショックコードがタープ布の中に入ってしまっている場合は、一度引き出してから、ゴム通しなどを使って タープ布の中に入れ直す必要があります。ショックコードを 通し直す作業は、下記のブログを参考にして下さい。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9265016.html
ショックコードを通し直す作業では、ゴム通しのようなものが必要なのですが、下記のブログにありますように 色々なもので代用できます。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9263942.html
====================
なお、ボディ側アンカーは、

下記のサポート商品販売ページでも ご購入いただけます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/haab#support_goods
●ボディ側アンカー(2個)セット
アイズ-ブロッカーのショックコード(ゴム紐)は、ボディ側アンカーの紐部分に固定されている状態です。
(下画像では、ウェザーストリップモール’(ゴムクッション材)を外した状態で撮影しています)

タープ布が強く押される(あるいは引っ張る)ようなことがあると、内臓されているショックコード(ゴム紐)が伸び切ってしまいます。
伸び切ってしまったあとは、ボディ側あるいはドア側のアンカー部分に直接の力が働くこととなり、ボディ側アンカーのループ紐が切れてしまったり、爪付きクリップが抜けたりの支障につながることがあります。
(下画像では、ループ紐が切れてしまった状態です)

そんな場合には、強めの糸を使うことで補修が可能です。

==========
補修方法のご案内です。
1)まず、ボディ側アンカーを固定している爪付きクリップ を抜き出して、ボディ側アンカーを外してしまいます。

2)画像のような 釣り糸など(PEラインですと十分な強度があります。100均ショップでも販売されています)を 輪っか状態を作ります。

3)輪っか状にした釣り糸を、爪付きクリップを再利用して固定します。


4)下画像のように、輪っか部分に ショックコード端部のフックをつないで、タープ布を元どうりに接合していただければ補修完了です。



===============
ショックコードがタープ布の中に入ってしまっている場合は、一度引き出してから、ゴム通しなどを使って タープ布の中に入れ直す必要があります。ショックコードを 通し直す作業は、下記のブログを参考にして下さい。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9265016.html
ショックコードを通し直す作業では、ゴム通しのようなものが必要なのですが、下記のブログにありますように 色々なもので代用できます。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9263942.html
====================
なお、ボディ側アンカーは、

下記のサポート商品販売ページでも ご購入いただけます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/haab#support_goods
●ボディ側アンカー(2個)セット
2024年03月02日
磁石式アンカーの補修方法です。
磁石式バックドア側アンカーのタブが折れてしまった場合の補修方法を ご案内申し上げます。
正常な状態

タブが折れてしまった状態

↓
折れてしまったタブに代えて、穴の中に 強めの糸を固定することで補修ができます。

==============
補修の手順を ご案内します。
1)磁石タイプのバックドア側アンカーは、磁石の真ん中の穴に タブが樹脂リベットで固定されていて、
裏面に貼ってある粘着材で 鉄板部分に貼り付けられた状態にあります。
樹脂リベットは センターピンが押し込まれることで固定されています。
磁石アンカーの分解図

2)まず、磁石から樹脂リベットを外します。
樹脂リベットは、上イラスト図のように 2つの部品で構成されています。2つの部品のあいだにカッターナイフの刃などを挿入して、センターピンを浮かすことで 2つの部品を分離できて 樹脂リベットを磁石から抜き出すことができます。

カッターナイフの刃をこじるようにして、少しづつセンターピンを浮かしていきます。

ニッパーなどを使いますと より外しやすいです。

樹脂リベットを抜き出すことができました。

3)強めの糸(釣り糸のPEラインなどが良いです。100均ショップにもあります)を輪っかにしてから、端をコブ玉状にしたものを用意しておきます。輪っかの大きさは まっすぐにした状態で1~2cm程度の大きさにしておきます。

4)コブ玉状にした部分を 磁石の穴の中に入れてから、小さくしたしたティッシュを つまようじなどで 押し入れていくと、 輪っかにした糸を仮固定状態にできます。

5)詰めたティッシュやコブ玉部分に瞬間接着剤を染み込ませます。

磁石の裏側から見た画像です。磁石の穴は内側で広がっています。

実際には 磁石の裏面全体に粘着材が貼られていますので、瞬間接着剤が裏側から漏れ出てしまうことはありません。

6)さらに 穴の中に テッシュを押し入れて 瞬間接着剤を染み込ませていきます。

7)染み込ませた瞬間接着剤が 完全に固まってから、輪っかにした糸を強く引っ張ってみて 抜け出てこないことを確認してください。

=====================
別の補修方法も ご案内いたします。
磁石の穴に フック部分をビス止めしてしまう方法もあります。
ドリルビス(ピアスビス、テックスビス)を使って 充電ドライバーで固定してしまうのが 簡単です。


ドリルビスは、先端がドリル状になっていて、鉄板に下穴を開けながらビスをねじ込むことができます。
==============================================
補修したアンカーに ショックコード(ゴム紐)を つなぎ直す手順や、
ショックコード(ゴム紐) 切れてしまっている場合の ご案内です。
こちらのブログを参考にしてください。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9790842.html
https://aizurv2.hamazo.tv/e9265016.html
==============================================
既設の磁石アンカーを剥がす方法をご案内します。
ショックコード(ゴム紐)の 磁石側フックを外してから、袋状の中に入ってしまわないようにフック部分に 2重リングや紐などをつなげておくか、ガムテープなどを巻いておきます。
1)石油系溶剤をご用意ください(ベンジン、キャンプなどで使うホワイトガソリン、灯油、ガソリン、軽油、シリコンオフ など・・・)
磁石の粘着材のところに カッターナイフの刃を少しづつ入れていきます。その際 ナイフの刃に石油系溶剤で湿らせながら刃を入れていくと 切り進めやすいです。
(細い糸を使って 粘着材部分を切って取り除く方法もありますが、その場合でも 糸を石油系溶剤で湿らせながら行うと 切り進めやすいです )
なお、ラッカーシンナーなどの溶剤は塗装を痛めてしまいますので 使わない方がベターです。
カッター刃を入れている画像
2)磁石を剥がし取った後の まだ残ってしまっている粘着材は、石油系溶剤を使って 溶解させることで 簡単・キレイに取り除けます。
(ヘヤードライヤーなどで 適度に温めながら剥がしていく方法もあります)
なお、ラッカーシンナーなどの溶剤は塗装を痛めてしまいますので 使わない方がベターです。
まず、残ている粘着材の上にテッシュペーパーを数枚重ね置きます。次にテッシュペーパーに石油系溶剤を湿らせて テープで1時間ほど密閉しておきますと、粘着材が溶解されて キレイにはがれてくれます。
溶剤を湿らす前に テッシュペーパーの周辺にテープを貼っておいて、 溶剤を湿らしたあとで しっかりと密閉状態を作ることがコツです。
覆っている画像
石油系溶剤を使って 粘着材を 簡単・キレイに取り除く方法は、こちらのブログでもご案内しております。参考にしていただければと存じます。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9665705.html
なお、ブログ内でもご案内しておりますが、「粘着材剥がし」などを使われる方法は、剥がし取った後で 再び粘着材を貼り付ける際に不具合の元になる可能性がありますのでご注意ください。
正常な状態

タブが折れてしまった状態

↓
折れてしまったタブに代えて、穴の中に 強めの糸を固定することで補修ができます。

==============
補修の手順を ご案内します。
1)磁石タイプのバックドア側アンカーは、磁石の真ん中の穴に タブが樹脂リベットで固定されていて、
裏面に貼ってある粘着材で 鉄板部分に貼り付けられた状態にあります。
樹脂リベットは センターピンが押し込まれることで固定されています。
磁石アンカーの分解図

2)まず、磁石から樹脂リベットを外します。
樹脂リベットは、上イラスト図のように 2つの部品で構成されています。2つの部品のあいだにカッターナイフの刃などを挿入して、センターピンを浮かすことで 2つの部品を分離できて 樹脂リベットを磁石から抜き出すことができます。

カッターナイフの刃をこじるようにして、少しづつセンターピンを浮かしていきます。

ニッパーなどを使いますと より外しやすいです。

樹脂リベットを抜き出すことができました。

3)強めの糸(釣り糸のPEラインなどが良いです。100均ショップにもあります)を輪っかにしてから、端をコブ玉状にしたものを用意しておきます。輪っかの大きさは まっすぐにした状態で1~2cm程度の大きさにしておきます。

4)コブ玉状にした部分を 磁石の穴の中に入れてから、小さくしたしたティッシュを つまようじなどで 押し入れていくと、 輪っかにした糸を仮固定状態にできます。

5)詰めたティッシュやコブ玉部分に瞬間接着剤を染み込ませます。

磁石の裏側から見た画像です。磁石の穴は内側で広がっています。

実際には 磁石の裏面全体に粘着材が貼られていますので、瞬間接着剤が裏側から漏れ出てしまうことはありません。

6)さらに 穴の中に テッシュを押し入れて 瞬間接着剤を染み込ませていきます。

7)染み込ませた瞬間接着剤が 完全に固まってから、輪っかにした糸を強く引っ張ってみて 抜け出てこないことを確認してください。

=====================
別の補修方法も ご案内いたします。
磁石の穴に フック部分をビス止めしてしまう方法もあります。
ドリルビス(ピアスビス、テックスビス)を使って 充電ドライバーで固定してしまうのが 簡単です。


ドリルビスは、先端がドリル状になっていて、鉄板に下穴を開けながらビスをねじ込むことができます。
==============================================
補修したアンカーに ショックコード(ゴム紐)を つなぎ直す手順や、
ショックコード(ゴム紐) 切れてしまっている場合の ご案内です。
こちらのブログを参考にしてください。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9790842.html
https://aizurv2.hamazo.tv/e9265016.html
==============================================
既設の磁石アンカーを剥がす方法をご案内します。
ショックコード(ゴム紐)の 磁石側フックを外してから、袋状の中に入ってしまわないようにフック部分に 2重リングや紐などをつなげておくか、ガムテープなどを巻いておきます。
1)石油系溶剤をご用意ください(ベンジン、キャンプなどで使うホワイトガソリン、灯油、ガソリン、軽油、シリコンオフ など・・・)
磁石の粘着材のところに カッターナイフの刃を少しづつ入れていきます。その際 ナイフの刃に石油系溶剤で湿らせながら刃を入れていくと 切り進めやすいです。
(細い糸を使って 粘着材部分を切って取り除く方法もありますが、その場合でも 糸を石油系溶剤で湿らせながら行うと 切り進めやすいです )
なお、ラッカーシンナーなどの溶剤は塗装を痛めてしまいますので 使わない方がベターです。
カッター刃を入れている画像
2)磁石を剥がし取った後の まだ残ってしまっている粘着材は、石油系溶剤を使って 溶解させることで 簡単・キレイに取り除けます。
(ヘヤードライヤーなどで 適度に温めながら剥がしていく方法もあります)
なお、ラッカーシンナーなどの溶剤は塗装を痛めてしまいますので 使わない方がベターです。
まず、残ている粘着材の上にテッシュペーパーを数枚重ね置きます。次にテッシュペーパーに石油系溶剤を湿らせて テープで1時間ほど密閉しておきますと、粘着材が溶解されて キレイにはがれてくれます。
溶剤を湿らす前に テッシュペーパーの周辺にテープを貼っておいて、 溶剤を湿らしたあとで しっかりと密閉状態を作ることがコツです。
覆っている画像
石油系溶剤を使って 粘着材を 簡単・キレイに取り除く方法は、こちらのブログでもご案内しております。参考にしていただければと存じます。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9665705.html
なお、ブログ内でもご案内しておりますが、「粘着材剥がし」などを使われる方法は、剥がし取った後で 再び粘着材を貼り付ける際に不具合の元になる可能性がありますのでご注意ください。
2024年01月29日
弱くなったダンパーを交換してみると・・・
エブリィのダンパー交換のようすです。
弊社スタッフが乗っているエブリィは、新車登録から6年目です。
アイズブロッカーを装着していることもあり、寒いときには、こんな位置で止まってしまいます・・・全開しません・・・トホホ

バックドアのガスダンパーの反力が弱くなってしまっているためです。ちなみに アイズブロッカーを装着しても ドアが全開してくれるためには、装着前の状態で ドアの先端に2リットルボトルを吊り下げても ドアは全開位置で止まっていてくれるほどの余力が必要です。(アイズブロッカーを装着することで 2リットルボトルを吊り下げる場合と同じくらいに ドアを引き下ろす力が働きます)
「ダンパーストッパー」なる道具(1000円くらいで販売されています。自作する方々も多いです)を使えば、ドアを全開位置に保持することができますが、いちいち付け外しをする面倒さがあります。
(なお、この部品を使えば、ドアを降りてこないように止めることはできますが、ドアが開いて行かないように止めることはできません・・・)

「ダンパーストッパー」は、バックドアにハシゴや自転車キャリアなどを装着していて、ドアが随分と重くなっている場合などでは 重宝したりします。

(なお、 重くなっているドアを 全開位置に無理やり固定することには 注意が必要です。
アイズ-ストッパー 装着ブログ https://aizurv2.hamazo.tv/e9727167.html の一番最後にある「ご使用方法・ご注意 」を参照ください。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
バックドアが全開してくれるように、ダンパーを交換することにします。 アマゾンで販売している 反力が強いタイプ(増圧20kgだとか・・・)にしてみました。

左右2本分(左右兼用の同じ物が2本です)で 購入当時6900円(税込み)です。 口コミを見ると 当たりハズレがありそうですが、大丈夫かなぁ・・・
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0BGGDH14B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&th=1
まずは ロッド部分へのオイルのしみ出しを確認した 左側ダンパーだけを交換してみます。
●交換作業は、ドアを全開位置にした状態で行います。
つっかえ棒で支えておきます。 エブリィは、ハイエースなどに比べれば、ドアの重さはたいしたことないので こんな簡単な支えにしてますが、もし支えが外れると痛い思いをしますので、支えが 絶対に外れないような注意が必要です。

ドア側の取り付け部は、12mmスパナで簡単に外れましたが、

ボディ側は固着気味になってしまっています。 スパナで外すのは心もとないので、ボールジョイント部分を外してから(マイナスドライバーで簡単に分離できます)、

念のためメガネレンチを使って(スパナだとなめる可能性が・・・)、力ずくで外しました。

新しいダンパーの方は、12mmスパナで簡単に取り付けができました。

使用工具は、●支え棒 ●12mmメガネ(あるいはスパナ) ●マイナスドライバー だけです。

左側ダンパー1本を交換しただけで、ドアは全開位置で しっかりと止まってくれるようになりました。
さすが増圧タイプ(^^♪ 当たりの1本でした(o^。^o)

作業時間は30分ほどでした。
==========
左右とも交換してしまうと、十分すぎる反力となって 夏場には引き下ろすのに大変そうですので、左側1本だけの交換にとどめておくことにしました。
使う必要のなかった もう1本のダンパーは、今後のために 保管しておくことにしますが、ダンパーの保管は、必ず正立状態で保管する必要があります。

ダンパーのシリンダー(チューブ)部分には 窒素ガスが100気圧を優に超える高圧で 封入されている状態です。
ちなみに、縮まった際にも 同じ気圧です。詳しくは LAMP印のスガツネ工業様で https://cont.sugatsune.co.jp/motion/jp/tips/toolview_gasspring
高圧ガスは シリンダーとロッドとの隙間から どうしても少しづつ抜け出ていってしまいます。窒素ガスの他にオイルも入っていて、そのオイルがガス抜けを防ぐシール材の役目をしています。(もしロッドが オイルで濡れているようでしたら そのダンパーはガス抜けが進んでしまっているものと思われます)
オイルがシール材として機能するためには、オイルがシリンダーとロッドとの隙間をふさいでいる必要がありますので、オイルが下側にあるようにするために、ダンパー保管は、必ず正立状態(シリンダーが上側で ロッドが下側)で保管する必要があるそうです。また ロッドにキズが付かないようにも注意します。 https://faq.sugatsune.co.jp/faq/show/1527?site_domain=tecf
(なお 正立保管でなくても良いタイプのダンパーもあるようです。ちなみにハイエース用のダンパーをバラしてみると 正立保管でないとよろしくないtypeでした・・・)
バックドアのガスダンパー(高圧ガススプリング)はどうしても経年劣化していきます。個体差や使われ方で違いがあるでしょうが、おおむね5年くらいで交換したくなるように思います。
また、交換の際は、左右同時交換が基本のようですが、今回のように(反力が弱まっている)片側だけを交換する方法もあります。片側だけ交換ですと 反力が左右でアンバランスにはなりますが、通常なら ドアの立て付けをゆがめてしまうほどの支障は出ませんから、今回のように(反力が弱まっている)片側だけを交換する方法も 反力具合の調節が出来て よろしいかと存じます。
ガス抜けは、左右アンバランスで抜けていく場合が多いです。片側だけを交換する場合には 反力がより弱い片側を交換する方がよろしいかと存じます。
(なので、今回の作業では ロッド部分へのオイルのしみ出しを確認した左側ダンパーを交換しました)
左右の反力具合を確認してみる方法を ご案内申し上げます。
ちなみに 伸び切っているダンパーを60kgほどの全体重をかけて押し下げるくらいでは びくともしないです・・・(その程度で 押し下がるようでしたら、反力が ものすごく弱くなっている状況です)
反力具合を比較確認してみる方法としては、
1)まず車体に1本だけを残した状態にします。 支えを外すと ドアは下がってきてしまいますが、ドアを持ち上げてみた際の重さ感を 覚えておきます。
2)外したダンパーを元どうりに車体に取り付け直してから、今度は、反対側のダンパーを 同様に 1本だけを残した状態にして、ドアを持ち上げてみた際の重さ感を 覚えておきます。
3) 1)と 2)の重さ感を比べて見て、重さ感の大きい方(反力がより弱くなっている方)のダンパーを交換します。
なお、左右のダンパーを2本とも交換する場合にありましては、
左右2本ともを同時に外してしまうと、バックドアを全開状態にまで押し上げて なおかつ 支え棒で支えるのは 一人作業では危険を伴います。
2本を交換する場合でも、必ず 片側1本づつ 交換のが安全です。
ハイエースの場合では、伸縮式のタープポール と、 ジャッキスタンド を使っています。
ドアが重いので ヘルメットをかぶりたいくらいです(笑)
どうぞ ご安全に・・・

弊社スタッフが乗っているエブリィは、新車登録から6年目です。
アイズブロッカーを装着していることもあり、寒いときには、こんな位置で止まってしまいます・・・全開しません・・・トホホ

バックドアのガスダンパーの反力が弱くなってしまっているためです。ちなみに アイズブロッカーを装着しても ドアが全開してくれるためには、装着前の状態で ドアの先端に2リットルボトルを吊り下げても ドアは全開位置で止まっていてくれるほどの余力が必要です。(アイズブロッカーを装着することで 2リットルボトルを吊り下げる場合と同じくらいに ドアを引き下ろす力が働きます)
「ダンパーストッパー」なる道具(1000円くらいで販売されています。自作する方々も多いです)を使えば、ドアを全開位置に保持することができますが、いちいち付け外しをする面倒さがあります。
(なお、この部品を使えば、ドアを降りてこないように止めることはできますが、ドアが開いて行かないように止めることはできません・・・)

「ダンパーストッパー」は、バックドアにハシゴや自転車キャリアなどを装着していて、ドアが随分と重くなっている場合などでは 重宝したりします。

(なお、 重くなっているドアを 全開位置に無理やり固定することには 注意が必要です。
アイズ-ストッパー 装着ブログ https://aizurv2.hamazo.tv/e9727167.html の一番最後にある「ご使用方法・ご注意 」を参照ください。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
バックドアが全開してくれるように、ダンパーを交換することにします。 アマゾンで販売している 反力が強いタイプ(増圧20kgだとか・・・)にしてみました。

左右2本分(左右兼用の同じ物が2本です)で 購入当時6900円(税込み)です。 口コミを見ると 当たりハズレがありそうですが、大丈夫かなぁ・・・
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0BGGDH14B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&th=1
まずは ロッド部分へのオイルのしみ出しを確認した 左側ダンパーだけを交換してみます。
●交換作業は、ドアを全開位置にした状態で行います。
つっかえ棒で支えておきます。 エブリィは、ハイエースなどに比べれば、ドアの重さはたいしたことないので こんな簡単な支えにしてますが、もし支えが外れると痛い思いをしますので、支えが 絶対に外れないような注意が必要です。

ドア側の取り付け部は、12mmスパナで簡単に外れましたが、

ボディ側は固着気味になってしまっています。 スパナで外すのは心もとないので、ボールジョイント部分を外してから(マイナスドライバーで簡単に分離できます)、

念のためメガネレンチを使って(スパナだとなめる可能性が・・・)、力ずくで外しました。

新しいダンパーの方は、12mmスパナで簡単に取り付けができました。

使用工具は、●支え棒 ●12mmメガネ(あるいはスパナ) ●マイナスドライバー だけです。

左側ダンパー1本を交換しただけで、ドアは全開位置で しっかりと止まってくれるようになりました。
さすが増圧タイプ(^^♪ 当たりの1本でした(o^。^o)

作業時間は30分ほどでした。
==========
左右とも交換してしまうと、十分すぎる反力となって 夏場には引き下ろすのに大変そうですので、左側1本だけの交換にとどめておくことにしました。
使う必要のなかった もう1本のダンパーは、今後のために 保管しておくことにしますが、ダンパーの保管は、必ず正立状態で保管する必要があります。

ダンパーのシリンダー(チューブ)部分には 窒素ガスが100気圧を優に超える高圧で 封入されている状態です。
ちなみに、縮まった際にも 同じ気圧です。詳しくは LAMP印のスガツネ工業様で https://cont.sugatsune.co.jp/motion/jp/tips/toolview_gasspring
高圧ガスは シリンダーとロッドとの隙間から どうしても少しづつ抜け出ていってしまいます。窒素ガスの他にオイルも入っていて、そのオイルがガス抜けを防ぐシール材の役目をしています。(もしロッドが オイルで濡れているようでしたら そのダンパーはガス抜けが進んでしまっているものと思われます)
オイルがシール材として機能するためには、オイルがシリンダーとロッドとの隙間をふさいでいる必要がありますので、オイルが下側にあるようにするために、ダンパー保管は、必ず正立状態(シリンダーが上側で ロッドが下側)で保管する必要があるそうです。また ロッドにキズが付かないようにも注意します。 https://faq.sugatsune.co.jp/faq/show/1527?site_domain=tecf
(なお 正立保管でなくても良いタイプのダンパーもあるようです。ちなみにハイエース用のダンパーをバラしてみると 正立保管でないとよろしくないtypeでした・・・)
バックドアのガスダンパー(高圧ガススプリング)はどうしても経年劣化していきます。個体差や使われ方で違いがあるでしょうが、おおむね5年くらいで交換したくなるように思います。
また、交換の際は、左右同時交換が基本のようですが、今回のように(反力が弱まっている)片側だけを交換する方法もあります。片側だけ交換ですと 反力が左右でアンバランスにはなりますが、通常なら ドアの立て付けをゆがめてしまうほどの支障は出ませんから、今回のように(反力が弱まっている)片側だけを交換する方法も 反力具合の調節が出来て よろしいかと存じます。
ガス抜けは、左右アンバランスで抜けていく場合が多いです。片側だけを交換する場合には 反力がより弱い片側を交換する方がよろしいかと存じます。
(なので、今回の作業では ロッド部分へのオイルのしみ出しを確認した左側ダンパーを交換しました)
左右の反力具合を確認してみる方法を ご案内申し上げます。
ちなみに 伸び切っているダンパーを60kgほどの全体重をかけて押し下げるくらいでは びくともしないです・・・(その程度で 押し下がるようでしたら、反力が ものすごく弱くなっている状況です)
反力具合を比較確認してみる方法としては、
1)まず車体に1本だけを残した状態にします。 支えを外すと ドアは下がってきてしまいますが、ドアを持ち上げてみた際の重さ感を 覚えておきます。
2)外したダンパーを元どうりに車体に取り付け直してから、今度は、反対側のダンパーを 同様に 1本だけを残した状態にして、ドアを持ち上げてみた際の重さ感を 覚えておきます。
3) 1)と 2)の重さ感を比べて見て、重さ感の大きい方(反力がより弱くなっている方)のダンパーを交換します。
なお、左右のダンパーを2本とも交換する場合にありましては、
左右2本ともを同時に外してしまうと、バックドアを全開状態にまで押し上げて なおかつ 支え棒で支えるのは 一人作業では危険を伴います。
2本を交換する場合でも、必ず 片側1本づつ 交換のが安全です。
ハイエースの場合では、伸縮式のタープポール と、 ジャッキスタンド を使っています。
ドアが重いので ヘルメットをかぶりたいくらいです(笑)
どうぞ ご安全に・・・

2024年01月15日
デリカD:5用 アイズ-ブロッカー取付説明書
ミツビシ デリカD:5 用 アイズ-ブロッカー取付説明書
(特許第6862023)
2024年1月1日以降に出荷した製品の装着方法となります。

===================
【必要工具類】
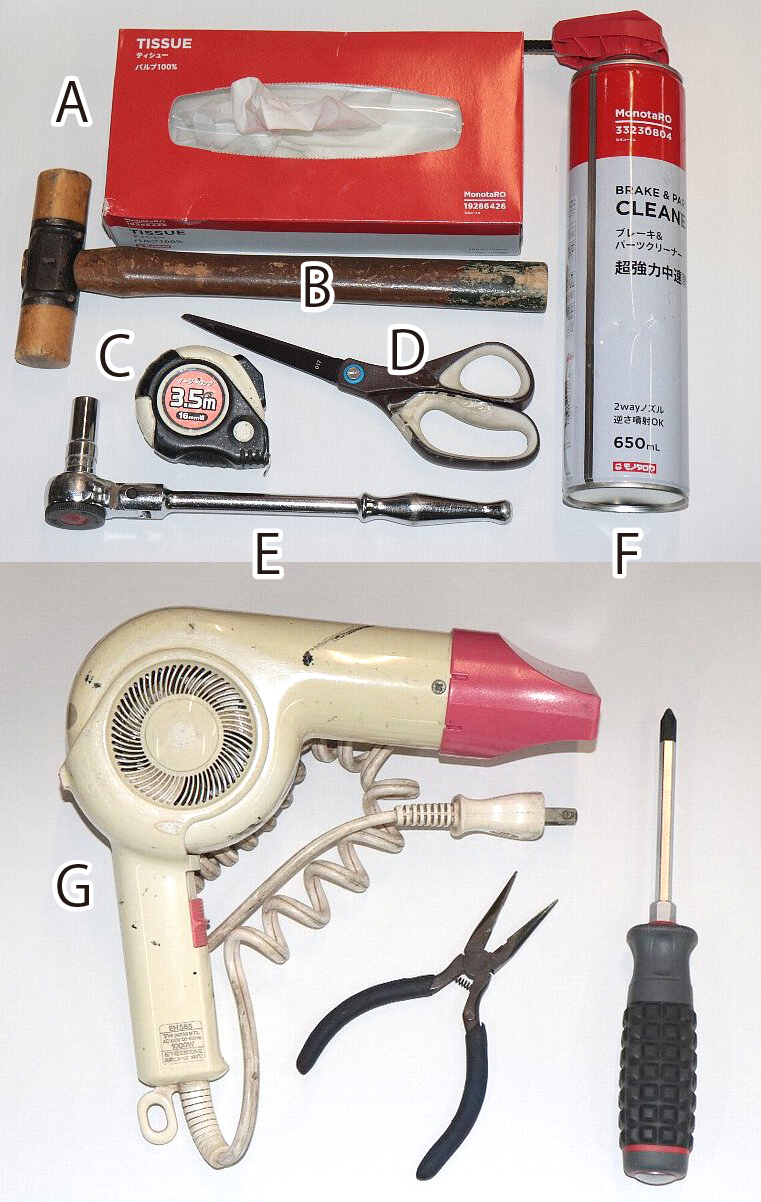
A:テッシュ
B:ハンマーの類(フツーのトンカチでokです)
C:メジャー
D:ハサミ
E:ソケットレンチ(10mm)
F:パーツクリーナーの類(脱脂処理に使用します。ベンジンなどの石油系溶剤がお勧めです。シンナーなどの溶剤は塗装面を痛めます)
G:ドライヤー(寒冷時や多湿の場合に使用)
※先の細いプライヤーやペンチの類
※水性ペン
※踏み台
があると便利です。
===================
【商品内容】を ご確認ください。

①:アイズ-ブロッカー本体タープ布:左右2枚(ショックコード付き)
※運転席側のタープ布には、緑色の「Aizuのタグ」が縫い付けています。助手席側にはタグはありません。
②:ボディー側ホールドテープ:2本
③:バックドア側ホールドテープ:2本
④:ボディー側アンカー
紐付きの短いテープ状のもの:2個 + 爪付きクリップ小2個付き
⑤:バックドア側アンカー :2個(丸ワッシャーに紐付き)
⑥:黒色テープ:2枚(タープ布接合時に使用)
⑦:バックドア側ホールドテープ用プライマー液:1 個
⑧:ボディー側ホールドテープ固定用 爪付きクリップ:10個
以上、8点です
===================
《各部の名称》 です。

【装着作業の流れ】
1. バックドア側ホールドテープを貼り付ける面をしっかりと脱脂します
↓
2. 貼り付け面にプライマーを塗ります
↓
3. バックドア側ホールドテープを貼り付け、しっかりと圧着します
4. バックドア側アンカーを取り付けます(ソケットレンチ(10mm)が必要です)
↓
5. ボディー側アンカーを装着します
↓
6. ボディー側ホールドテープを装着します。
↓
最低1時間、できれば半日間ほど放置してください。その間にテープの粘着材の接着力が増します
↓
7. タープ布を取り付けます
↓
8. 貼り具合を調整して終了
★下記の取り付け説明書を 熟読、ご理解いただいたうえでの作業を お願い申し上げます。
作業時間自体は、1時間ほどですが、後述をする 粘着材の養生時間 が必要なことから、アイズ-ブロッカーの装着作業は、終了までに 半日ほど 時間がかかってしまいますことを ご承知くださいますよう お願いいたします。
寒冷時にドライヤーをお使いになれない環境の場合には、バックドアを閉めた状態で車のヒーターを稼働させて、バックドアの表面温度が、できれば20℃以上になっている状態にしてから 作業されることをお勧めします。
==========================
1.バックドア側のホールドテープの貼り付け面付近をしっかりと脱脂する
下画像のように、白色テープ部分に 粘着材付きのホールドテープを貼り付けます。画像は運転席側です。

1-1
パーツクリーナー(プラスチックへの使用がOKなもの)やテッシュ・布などを使って、ホールドテープの貼り付け面付近を しっかりと脱脂処理してください。
貼り付ける部分に、プラスチック保護剤などの成分が残っていると、粘着材はしっかりと貼りつきません。粘着材を貼り付ける際の脱脂処理は とても重要な作業となります。



脱脂作業のコツとしては
※ 拭き取る紙や布は汚れの無い物を使用し、常に新しい面で拭う。
(汚れた面で拭くと、汚れをただのばしているだけになってしまします。)
※ 拭き取り方は一方向とし、往復や丸く拭かない。
※ 溶剤で濡らしてから乾かないうちに乾いた布で拭くことが基本です。
(1枚の布で前端だけ溶剤を含ませ、後半分は乾いた状態で、一方向に拭くのは良い方法です。)
運転席側と助手席側とを 脱脂処理してください。
===================================
2. 貼り付け面にプライマーを塗ります。
2-1
テープを貼り付ける部分に プライマーを塗ってください。 必ずプライマー処理をしてください。プライマーでの下地処理がないと シッカリと貼りつきません
小さく折りたたんだ(3~4cm四方)テッシュに、小瓶に入っているプライマー液を浸み込ませながら、

脱脂済みの貼り付け面を拭くようにして プライマー液を塗布します。 テープ貼り付け部分よりも 広めの面積を塗ってください。


プライマー液を こぼさないようにご注意ください。
続けて 助手席側の貼り付け面も 同様にプライマー処理してください。
============================
3. バックドア側ホールドテープを貼り付ける
プライマーを塗ってから 10分ほど乾燥させたのちに、ホールドテープを貼り付けます。
※ 基本的には 貼り直しができません。
テープの貼り付け位置を しっかりと確認していただいて 一発勝負で貼りつけてください。
(貼り付け直後だと 剥がして再貼り付けできますが、数十秒経過すると まともには剥がせませんので ご注意ください)
貼り付け作業の前に、今一度 貼り付け位置をご確認ください。
下画像の白色テープ付近に貼ってください。 貼り付け位置は厳密でなくとも、おおむね画像と同じような位置でかまいません。




3-1 一番下のマルチユースフックのすぐそばから貼り始めます。


ドアの中ほどにあるマルチユースフックのあたりで、テープを曲げますので、いったんハサミで切ってから 曲がり部から続けて貼る方法が作業しやすいです。


3-2 続けて貼っていきます。


テープの長さ分 全部を貼ってください。

運転席側が終わりましたら、助手席側も同様にホールドテープを貼ってください。
3-3
テープを貼り終えましたら、テープの上から しっかりと押し付けて 十分に加圧してください。

粘着テープは「感圧接着剤」とも呼ばれていて、圧力を加えないと 十分な接着力(粘着力)を発揮しません。高性能なテープほど しっかりと圧力を加える必要があります。テープの上から 1㎝ごとに 指圧をするつもりで加圧していってください。特に 一番下側付近と、一番上側の端部付近は 入念に押し付けてください。
繰り返しになりますが、「テープを単に貼っただけでは、剥がれてきてしまいます。しっかりと押し付けてください」
貼り付け後の画像です。


============================
4. バックドア側にアンカーを取りり付けます。
4-1
まず、ソケットレンチ(10mm)を使って、一番下のマルチユースフックを取り外します。

4-2
アンカーをフックの裏側に入れて、アンカーから出ている紐が、貼ってあるホールドテープの方向に出した状態で フックを取り付け直します。




運転席側 取り付け後の画像です。マルチユースフックから紐が テープ側に出ています。

============================
5. ボディー側アンカーを取り付ける
※ところどころ画像は他車種のものになりますが作業内容は同じです。
5-1
まず、ボディー側ウェザーストリップ(黒色のゴムモール)を後方に引き出して 外します。


5-2
車体中央を基準にボディー側アンカーを取り付けますので位置を確認してください。ドアロック金具の中央から、爪付きクリップの内側までが47cmあたりの位置に取り付けます。

5-3
ループ紐の付いた短いテープを、爪付きクリップを使って鉄板に固定します。テープの端と鉄板の端を合わせるようにします。

先に、テープを爪付きクリップに差し込んでから

ハンマーを使って奥までしっかりと打ち込みます。引っ張っても抜けてこなければOKです。
この時アンカーの端を、車外側へ5ミリほどはみ出させて固定してください↓


助手席側にも 同様にしてアンカーを取り付けます。
============================
6. ボディー側ホールドテープを装着する
ウェザーストリップモールの溝の中に ボディー側ホールドテープを差し込みながら 装着していきます。

作業前に ウェザーストリップの鉄芯の状態を確認してください。
まず動画をご覧いただき、装着イメージをつかんでください。
※この動画の車種はD:5ではありませんが、作業内容、要領は同じです。なお、動画では下側から上側に向かって装着していますが、D:5では 上側から下側に向かって装着していきます。
また、下の動画では、キャンピング架装されている車に、付属の「爪付きクリップ」を利用ながら、ホールドテープと網戸も一緒に装着しています。ホールドテープだけを装着する場合にありましても、付属の「爪付きクリップ」を利用することで、確実な装着ができます。
その1、
その2、下側付近は、引き出されようとする力がより強く働きます。「爪付きクリップ」を細かく打ち込んで、入念に固定しています
その3 市販されている、網戸のファスナーを開閉する際に、網戸の下部が モールから抜け出さないように「爪付きクリップ」で補強しています。
動画内で使っている「爪付きアンカー」は、製品に10個 付属させています。追加でお求めいただくこともできます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport
↑
アイズ-ブロッカーのタブをクリックし、表示されたメーカー一覧から車種をご選択ください
■ 装着要領■
①ウェザーストリップモールの溝にボディー側ホールドテープの幅の狭いほうを差し込みます。

②テープを差し込んだ状態のまま、元通りにボディーの鉄板へ はめ込みます。

この作業をすこしずつ繰り返して装着していきます。
※所々に、テープの装着始点部分で使った 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定することで、テープがズレるのを防いで装着がしやすくなります。
上の動画でも使っていますので ご確認ください。
下側へ向かってテープ全てを装着していってください。
6-1
まず、ウェザーストリップモールを持って、車の後ろ方向に引き出します。

6-2
ボディー側ホールドテープを上から下側に向かって装着していきます。
装着開始位置は、画像のようにサイドカバーの上端から70~80mm上側の位置から装着しはじめます。(なお、画像では開始位置が分かりやすいように黄色テープを貼っています)
ホールドテープの折り幅の少ない方を ウェザーストリップモールの溝に差し込みながら、

テープがズレるのを防いで装着をしやすくするため、付属の爪付きクリップで止めておきます。爪付きクリップの上からウェザーストリップモールを被せてしまってOKです。

「爪付きアンカー」は、製品に10個 付属させています。追加でお求めいただくこともできます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport
↑
アイズ-ブロッカーのタブをクリックし、表示されたメーカー一覧から車種をご選択ください
ホールドテープとウェザーストリップモールとをボディ側に戻し入れて、手のひらで押し込んでいきます。

※ホールドテープの 裏・表に ご注意ください!!
下画像の指が触れている面は、布地になります(ザラザラ面ではありません)

テープを裏返すとザラザラ面です(このザラザラ面にタープ布が接合されます)

6-3
下側に向かって 装着を繰り返していきます。

※ウェザーストリップモールを車外側から見てみると、シッカリ奥まで入っているかの判断がつきます。
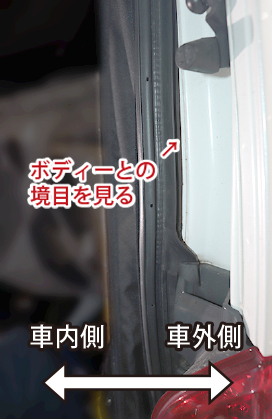
画像のようにベロ(ひだ)が付いている場合はめくって確認します。

↓ 隙間があるので、モールが奥まで入っておらずダメです。モールがシッカリ奥まで入っていれば隙間はありません。

ストップランプの付近の曲線部は、ハサミで 数カ所に切り込みを入れながら装着してください。

テープの下端は、ボディ側アンカーの上まで 装着してください。

下端の曲線部をハサミで 数カ所に切り込みを入れながら装着を進め、ボディー側ホールドテープの端を、ボディー側アンカーに5ミリほど重なるようにカットし…※画像は他車種のものになりますが作業内容は同じです。

重ねた付近を爪付きクリップで固定します


6-4
ホールドテープを装着し終った後で、ウェザーストリップモールの上から ハンマーでモールを打ち込みます。

この作業が大事です。
ホールドテープが装着イメージのイラストと同じ状態で正常に装着されていれば、軽く打ち込むだけでモールは奥まで打ち込めるハズです。打ち込み具合の判断は目視だけでは難しいので、打ち込んでいるときに出る、音や感触で判断します。 高い音・硬い感触になっていればOKです。★鈍い音・柔らかな感触だと モールが奥まで入っていない可能性があります。 一部でもウェザーストリップが浮き上がっていると バックドアの閉まりが悪くなってしまいます。★鈍い音・柔らかな感触のある箇所のモールを 一度引き出して ホールドテープが装着イメージのイラストと同じ状態になっていることを 再度確認してから ハンマーでモールを打ち込んでください。★鈍い音・柔らかな感触から→高い音・硬い感触になっていればOKです。
左右のホールドテープを装着し終えてから バックドアを閉めてみてください。「ドアの閉まりが固くなった感じ」や「ドアが開けにくくなった感じ」がする場合や半ドアになりやすくなった場合には、上記のウェザーストリップの浮き上がりを 再度 確認してみてください。
(特に上側付近に浮き上がりがあると影響が大きいですので、上側付近を入念にチェックしてみてください)
=================================
ここまでの作業が終わった状態で 1時間以上、できれば5時間ほど放置してください(ドアは開放されていても 閉めていてもOKです)。その間にバックドアに貼ったテープの接着力が増し、本来の性能の70%ほどの接着力になります。
夏場の晴れた日の作業でしたら、テープを貼って1時間後には 大丈夫な接着強度になっていたりしますが、できるだけ上記の養生時間を経てから タープ布を装着してください。特に寒冷時や雨の日の作業では 十分な養生時間を経過させてください。
=================================
7. タープ布を取り付ける
7-1
タープ布の車外側になる面には撥水加工処理を行っていますので、以下の方法で車外側を判別し、間違えないように装着してください。
▼タープ布の 運転席側/助手席側 の判別方法▼
運転席側の車内側だけに緑色のAizuのタグがついています。

※最新のタグはコチラ

▼装着時の目印▼
左右のタープ布とも、車内側になる面には薄茶色の面ファスナーが付いています。
これがバックドアの上部(首元)へ来るように装着してください。
(装着終了後は取り外してください)

7-2
タープ布の「袖口(上側)」と「足元(下側)」から出ているショックコードの端部に付いているフックをバックドア側アンカーとボディー側アンカーのそれぞれに接合します。
▼ボディー側アンカーへ▼
アンカーから出ている紐をループ状に広げておき、接合します。接合後はフックの開きを閉じ、タグを取り外してください。先の細いプライヤーで作業するとつなげやすいです。


▼バックドア側アンカーへ▼
さきほどの反対側から出ているフックを、バックドア側アンカーから出ている紐につなげてからフックの開きを閉じてください。

ここまでの作業を行うと運転席側タープ布は、下画像のような状態になります。

7-3
タープ布をホールドテープに接合していきます。①~⑩の順に取り付けを行ってください。
▼取付動画です。(2分42秒)ミツビシD:5ではありませんが、作業の要領は同じです。
▼まず①~⑤です▼
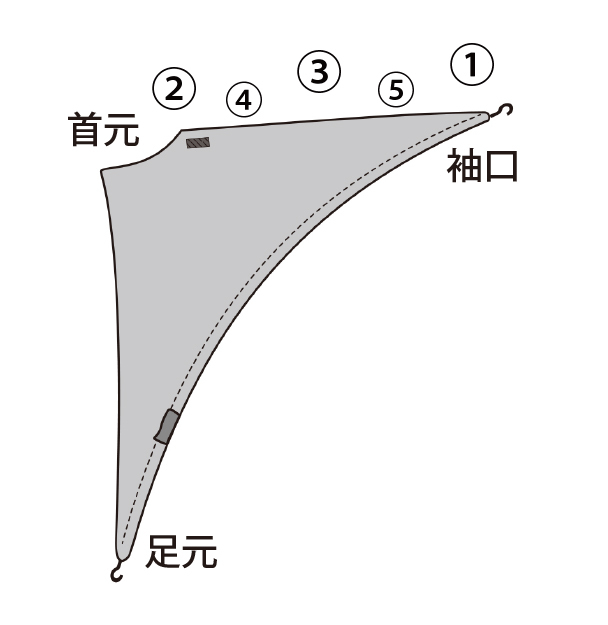
①.アンカー側端部(袖口)を接合します。
まず、端部から15cmほど接合しますが、その際に、小さな黒色テープを取り付けてください。両面がザラザラ面になっている 2cmほどの長さの小さな黒色テープ(2枚)です。
①-1.小さなテープを 下画像のように タープ布の端部を2センチほどを残して ザラザラ面で接合します。

①-2. 2センチほどを残した端部を フック金具を包み込むように折り返して ザラザラ面でに接合します。

①-3.下画像のように、できるだけ固く フック金具を包み込んでください。フック金具とタープ布とが一体になる(ズレ動かない)ようになっていればOKです。

端部の15センチほどを接合します。

車外側から見ると 下画像のようになっています。

②.反対側の端部(首元)を接合します。
15cmほど接合します。タープ布は伸縮性の高い生地ですので1.2倍ほどに伸びます。
強く引き伸ばしていただいても大丈夫です。

③.次に真ん中あたりを接合します。
5cmほど接合します。この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの④と⑤の辺りを、シワが無いように接合します。

▼次に⑥~⑩です▼

⑥.ボディー側の端部(首元)を接合します。
15cmほど接合します。
バックドア側と同様に、生地を引き伸ばして接合します。
その際に、首元ありのタープ布に張り感が出るように、なおかつあまり張りすぎない程度に接合してください。
ホールドテープの終端部とタープ布の終端部は、一致しません。テープの方が少し(1~2cm)余り気味になるはずです。余ったテープはのちほど切り取れますし、そのまま残しても問題ありません。

この辺りに適度な張り感
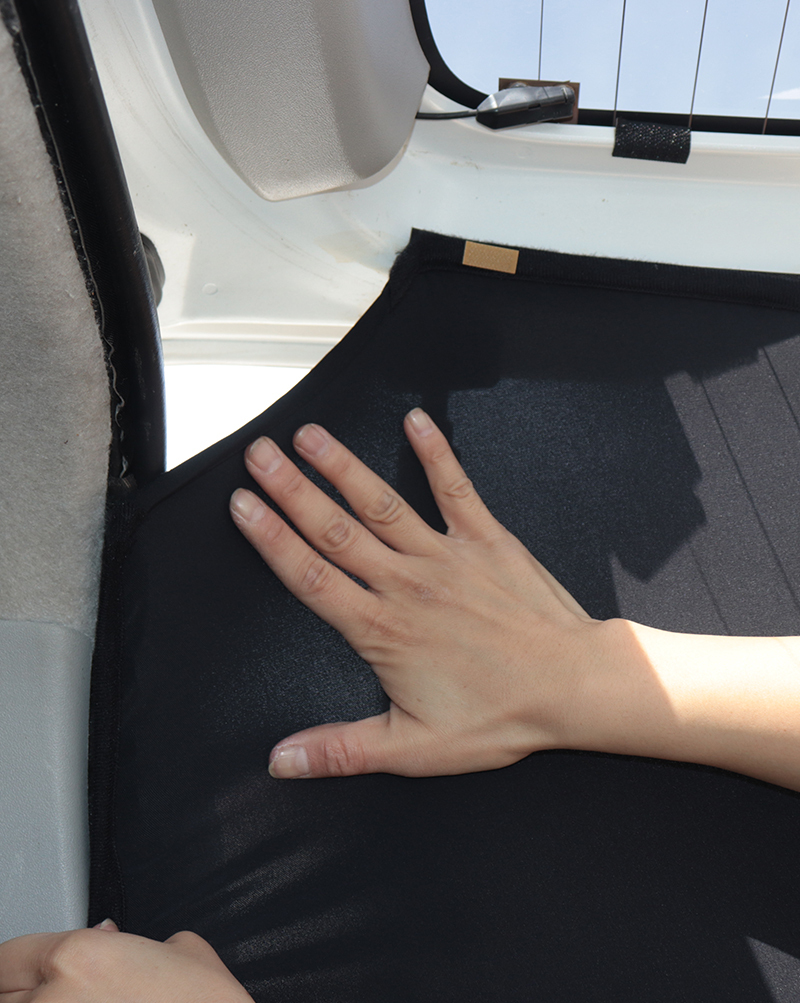
↑※この部分の張りが強すぎますと、バックドアを引き下げる力が強く働き ドアが全開位置に保持しずらくなります。張りが強すぎる場合には、上側方向に装着位置をずらしていく(ボディ側とバックドア側との距離を縮める)ことで 張り具合を 弱めることができます。
⑦.下側端部(足元)を接合します。
端部から15cmほど接合します。

⑧.次に真ん中あたりを接合します。
5cmほど接合します。
この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。

残りの⑨と⑩の辺りを、シワが無いように接合します。
※もしこの時点でシワが無くキレイに張れていれば、次の「手順8-1」は飛ばしてもらっても構いません※
=================================
8. 貼り具合を調整します
8-1
シワっ気が 残るようでしたら、何度も 剥がしては接合を繰り返して 貼り直してみてください。以下の画像の車両はD:5ではありませんが、作業内容は同じです。

テープ接合を剥がすには、タープ布の内側と外側の両方から 行うとやりやすいです。


シワが出ないようにするコツとしては、生地の一部に たるみが出ないように タープ布の接合部全体にわたって、 同じような引っ張り加減にすることです。
おおむね シワが取れました。

8-2
具合よく張っている状態が確認できたら、タープ布とバックドア側、タープ布とボディー側の 各ホールドテープとの接合部を しっかりと押さえて、接合を強くします





8-3
もし 上側端部のホールドテープが余っているようでしたら ハサミで切り取って整えて下さい。切らなくても性能的には支障はございません。


=================================
9. バックドアの閉まり具合をご確認ください
バックドアを閉めてみてください。
ドアの閉まり具合が固くなった感じがする場合や、半ドアになりやすくなってしまった場合には、6-4 の「ウェザーストリップモールの浮き上がり」を 再度 確認してください。パッと見では浮き上がりがないように見えても、ハンマーでたたいてみると 鈍い音がする場合もあります。
特に上部はわずかな浮きでも閉まり具合に影響します。(下部の浮きは さほどの影響はありません)

バックドアが元通りの全開状態になるかどうかを、ご確認ください。
・アイズ-ブロッカーを装着されたことで、ドアが全開位置に止まらなくなる場合もあります。タープ布の上部付近を上側方向に移動させてみて下さい( ⑥.ボディー側の端部(首元)を接合します。 を参照ください)。
・バックドアを開くガスダンパーが経年劣化で反力が弱まっておりますと、アイズ-ブロッカーを装着されたことで、ドアが全開位置に止まらなくなる場合もあります。
ダンパーを交換される場合には、より反力が強いタイプの「強化ダンパー」などに交換される方が、スキー場などの寒冷化でも また ドアに付加物を装着していて重くなっている場合などでも ドアが全開してくれやすく アイズ-ブロッカーとの相性が良いです。
バックドアを力強く押し上げるための部品は、「D5 強化ダンパー」「D5 補助ステー」などのワード検索でお探しできます。
・ドアが純正よりも より大きく開くダンパーに交換されている場合にありましては、純正状態よりも+7cmほどの高さまでは、タープ布やショックコードは追随できるようになっていますが、張りが強すぎる部分があると、全開位置までにならなかったり、ウェザーストリップモールが引き出される場合があります。ご注意ください。
バックドアを閉めた際に、タープ布がドアに挟まれないかをご確認してみてください。
バックドアを 勢いよく閉めようとするほど タープ布が はさまれやすいです。どこかの窓ガラスやドアを開けた状態で バックドアを閉めていただくと、タープ布が挟まれにくいです。 ドアをゆっくりと閉めていく方法も有効です。
D:5用のアイズ-ブロッカーは、タープ布が挟まれやすい車種になります。ストップランプ横のあたりが 一番挟まれやすいです。
挟まれにくい装着のコツなどを 下記ブログでご案内しています。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9759614.html

取り付け方法のご案内は、以上となります
■ ご使用上の注意点などは こちら でご案内しております。ぜひ一度お読みくださいませ。
============================
■補修部品につきまして。
バックドア側のホールドテープは 最下部の曲線部が一番 剥がれようとする力が働きます。 「この部分だけが剥がれてしまった・・・」場合には、剥がれた部分だけを貼り直すことで補修ができます。20cm+20cm(合計40cm)の長さのホールドテープ と、下地処理用のプライマーを、補修用品として用意しています。
他にも、各種補修部品を下記ページにて ご購入いただけます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/577
============================
最後になりますが、
ご使用上で 気になることが ございましたら ご報告いただけますと
今後の改良などへと つなげることができて、ありがたく存じます。
弊社レビュー投稿ページはコチラにあります。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/reviewlist
どうぞ よろしくお願いいたします。
株式会社 アイズ
アイズ-ブロッカー 開発・製作担当者 一同
TEL 053-422-7608
FAX 053-422-7178
info@aizu-rv.co.jp
===================
アイズ-ブロッカーは、 特許取得済です(特許第6862023)
また、上記説明書の営利目的利用はご遠慮下さい。(©aizu2021)
よろしくお願いいたします。
(特許第6862023)
2024年1月1日以降に出荷した製品の装着方法となります。
===================
【必要工具類】
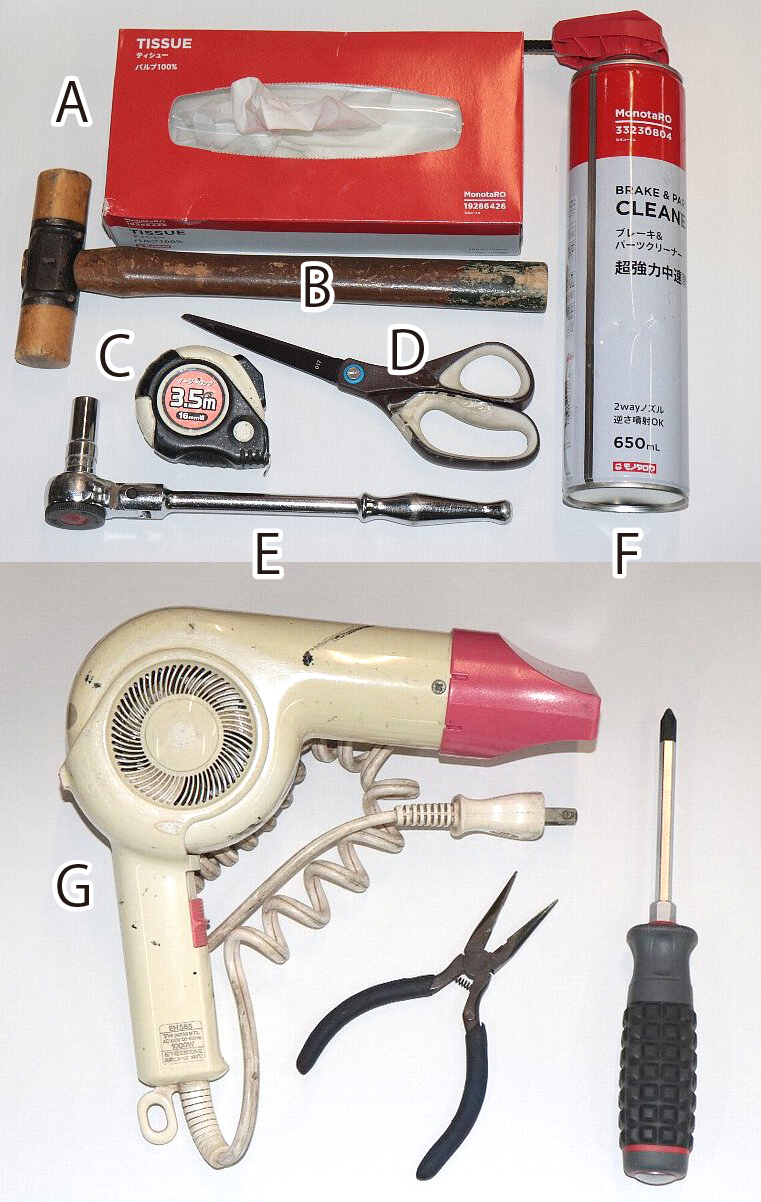
A:テッシュ
B:ハンマーの類(フツーのトンカチでokです)
C:メジャー
D:ハサミ
E:ソケットレンチ(10mm)
F:パーツクリーナーの類(脱脂処理に使用します。ベンジンなどの石油系溶剤がお勧めです。シンナーなどの溶剤は塗装面を痛めます)
G:ドライヤー(寒冷時や多湿の場合に使用)
※先の細いプライヤーやペンチの類
※水性ペン
※踏み台
があると便利です。
===================
【商品内容】を ご確認ください。

①:アイズ-ブロッカー本体タープ布:左右2枚(ショックコード付き)
※運転席側のタープ布には、緑色の「Aizuのタグ」が縫い付けています。助手席側にはタグはありません。
②:ボディー側ホールドテープ:2本
③:バックドア側ホールドテープ:2本
④:ボディー側アンカー
紐付きの短いテープ状のもの:2個 + 爪付きクリップ小2個付き
⑤:バックドア側アンカー :2個(丸ワッシャーに紐付き)
⑥:黒色テープ:2枚(タープ布接合時に使用)
⑦:バックドア側ホールドテープ用プライマー液:1 個
⑧:ボディー側ホールドテープ固定用 爪付きクリップ:10個
以上、8点です
===================
《各部の名称》 です。

【装着作業の流れ】
1. バックドア側ホールドテープを貼り付ける面をしっかりと脱脂します
↓
2. 貼り付け面にプライマーを塗ります
↓
3. バックドア側ホールドテープを貼り付け、しっかりと圧着します
4. バックドア側アンカーを取り付けます(ソケットレンチ(10mm)が必要です)
↓
5. ボディー側アンカーを装着します
↓
6. ボディー側ホールドテープを装着します。
↓
最低1時間、できれば半日間ほど放置してください。その間にテープの粘着材の接着力が増します
↓
7. タープ布を取り付けます
↓
8. 貼り具合を調整して終了
★下記の取り付け説明書を 熟読、ご理解いただいたうえでの作業を お願い申し上げます。
作業時間自体は、1時間ほどですが、後述をする 粘着材の養生時間 が必要なことから、アイズ-ブロッカーの装着作業は、終了までに 半日ほど 時間がかかってしまいますことを ご承知くださいますよう お願いいたします。
重要!!
▼使用している粘着テープについて
ホールドテープの粘着材の材質は、高性能な粘着テープですが、その性能を発揮させるには、
・接着面の十分な脱脂
・十分な加圧(5kgf/㎠) 強い指圧をするくらいの押し付け力が必要です。
・十分な養生時間→(1~5時間)
が必要です。
スリーエムジャパン株式会社様が公開している
「3M VHB 接着マニュアル」
をできればご一読ください。
▼施工時の温度・湿度について
気温が20℃以上あり、乾燥した状況下での作業が望ましいです。
※寒冷時や多湿時等は、ドライヤーを使用してください。ドライヤーで貼り付ける所とテープの粘着面を温めながら(50℃程度)取り付けることで、強力に貼り付けることができます。
↓↓
雨天時はどうしても、貼り付け面が湿ってしまいます。ドライヤーを使用できない場合は、晴れた日に作業を行ってください。
ホールドテープの粘着材の材質は、高性能な粘着テープですが、その性能を発揮させるには、
・接着面の十分な脱脂
・十分な加圧(5kgf/㎠) 強い指圧をするくらいの押し付け力が必要です。
・十分な養生時間→(1~5時間)
が必要です。
スリーエムジャパン株式会社様が公開している
「3M VHB 接着マニュアル」
をできればご一読ください。
▼施工時の温度・湿度について
気温が20℃以上あり、乾燥した状況下での作業が望ましいです。
※寒冷時や多湿時等は、ドライヤーを使用してください。ドライヤーで貼り付ける所とテープの粘着面を温めながら(50℃程度)取り付けることで、強力に貼り付けることができます。
↓↓
雨天時はどうしても、貼り付け面が湿ってしまいます。ドライヤーを使用できない場合は、晴れた日に作業を行ってください。
寒冷時にドライヤーをお使いになれない環境の場合には、バックドアを閉めた状態で車のヒーターを稼働させて、バックドアの表面温度が、できれば20℃以上になっている状態にしてから 作業されることをお勧めします。
==========================
1.バックドア側のホールドテープの貼り付け面付近をしっかりと脱脂する
下画像のように、白色テープ部分に 粘着材付きのホールドテープを貼り付けます。画像は運転席側です。
1-1
パーツクリーナー(プラスチックへの使用がOKなもの)やテッシュ・布などを使って、ホールドテープの貼り付け面付近を しっかりと脱脂処理してください。
貼り付ける部分に、プラスチック保護剤などの成分が残っていると、粘着材はしっかりと貼りつきません。粘着材を貼り付ける際の脱脂処理は とても重要な作業となります。
脱脂作業のコツとしては
※ 拭き取る紙や布は汚れの無い物を使用し、常に新しい面で拭う。
(汚れた面で拭くと、汚れをただのばしているだけになってしまします。)
※ 拭き取り方は一方向とし、往復や丸く拭かない。
※ 溶剤で濡らしてから乾かないうちに乾いた布で拭くことが基本です。
(1枚の布で前端だけ溶剤を含ませ、後半分は乾いた状態で、一方向に拭くのは良い方法です。)
運転席側と助手席側とを 脱脂処理してください。
ご注意下さい
ボディコーティングがされている場合
ボディコーティングされていると、通常の脱脂処理をしただけでは 粘着材がしっかりと貼り付きません。コーティング被膜をコンパウンドで磨き落とすなどの作業が必要となります。 また、最近の洗車用シャンプーの中には、ワックス成分やコーティング成分が配合されていて、汚れを落とすのと同時にボディに艶を出してくれる製品があります。ワックス成分やコーティング成分が残っておりますと、しっかりとテープが貼り付きません。コーティング被膜を磨き落とす方法は、1200~1500番くらいの耐水ペーパーや 研磨スポンジで磨き落とします。貼り付け面だけを磨き落とせるように、貼り付け面以外の箇所をマスキング処理をしてから磨き作業をされることをお勧めします。
各種のクリーナーを使って作業する場合
ガラスクリーナーやプラスチッククリーナーなどには、汚れを落とす成分の他に、汚れが再度付着することを防止する成分が含まれている場合が多いです。この汚れ付着防止成分(シリコンやワックス等)が表面に残っていると粘着材がしっかりと貼り付いてくれません。また 汚れ付着防止成分(シリコンやワックスなど)が残っている部分に一度貼り付けてしまった粘着材には、貼り付けることで 汚れ付着防止成分が粘着材側にも移行してしまいますので、再使用することができません。各種のクリーナーなどを使って作業をされた場合には 汚れ付着防止成分が表面に残らないよう、クリーナーを使用後に入念な脱脂処理してください。
ボディコーティングされていると、通常の脱脂処理をしただけでは 粘着材がしっかりと貼り付きません。コーティング被膜をコンパウンドで磨き落とすなどの作業が必要となります。 また、最近の洗車用シャンプーの中には、ワックス成分やコーティング成分が配合されていて、汚れを落とすのと同時にボディに艶を出してくれる製品があります。ワックス成分やコーティング成分が残っておりますと、しっかりとテープが貼り付きません。コーティング被膜を磨き落とす方法は、1200~1500番くらいの耐水ペーパーや 研磨スポンジで磨き落とします。貼り付け面だけを磨き落とせるように、貼り付け面以外の箇所をマスキング処理をしてから磨き作業をされることをお勧めします。
各種のクリーナーを使って作業する場合
ガラスクリーナーやプラスチッククリーナーなどには、汚れを落とす成分の他に、汚れが再度付着することを防止する成分が含まれている場合が多いです。この汚れ付着防止成分(シリコンやワックス等)が表面に残っていると粘着材がしっかりと貼り付いてくれません。また 汚れ付着防止成分(シリコンやワックスなど)が残っている部分に一度貼り付けてしまった粘着材には、貼り付けることで 汚れ付着防止成分が粘着材側にも移行してしまいますので、再使用することができません。各種のクリーナーなどを使って作業をされた場合には 汚れ付着防止成分が表面に残らないよう、クリーナーを使用後に入念な脱脂処理してください。
===================================
2. 貼り付け面にプライマーを塗ります。
2-1
テープを貼り付ける部分に プライマーを塗ってください。 必ずプライマー処理をしてください。プライマーでの下地処理がないと シッカリと貼りつきません
小さく折りたたんだ(3~4cm四方)テッシュに、小瓶に入っているプライマー液を浸み込ませながら、
脱脂済みの貼り付け面を拭くようにして プライマー液を塗布します。 テープ貼り付け部分よりも 広めの面積を塗ってください。
プライマー液を こぼさないようにご注意ください。
続けて 助手席側の貼り付け面も 同様にプライマー処理してください。
============================
3. バックドア側ホールドテープを貼り付ける
プライマーを塗ってから 10分ほど乾燥させたのちに、ホールドテープを貼り付けます。
※ 基本的には 貼り直しができません。
テープの貼り付け位置を しっかりと確認していただいて 一発勝負で貼りつけてください。
(貼り付け直後だと 剥がして再貼り付けできますが、数十秒経過すると まともには剥がせませんので ご注意ください)
貼り付け作業の前に、今一度 貼り付け位置をご確認ください。
下画像の白色テープ付近に貼ってください。 貼り付け位置は厳密でなくとも、おおむね画像と同じような位置でかまいません。
3-1 一番下のマルチユースフックのすぐそばから貼り始めます。
ドアの中ほどにあるマルチユースフックのあたりで、テープを曲げますので、いったんハサミで切ってから 曲がり部から続けて貼る方法が作業しやすいです。
3-2 続けて貼っていきます。
テープの長さ分 全部を貼ってください。
運転席側が終わりましたら、助手席側も同様にホールドテープを貼ってください。
3-3
テープを貼り終えましたら、テープの上から しっかりと押し付けて 十分に加圧してください。
重要!
粘着テープは「感圧接着剤」とも呼ばれていて、圧力を加えないと 十分な接着力(粘着力)を発揮しません。高性能なテープほど しっかりと圧力を加える必要があります。テープの上から 1㎝ごとに 指圧をするつもりで加圧していってください。特に 一番下側付近と、一番上側の端部付近は 入念に押し付けてください。
繰り返しになりますが、「テープを単に貼っただけでは、剥がれてきてしまいます。しっかりと押し付けてください」
貼り付け後の画像です。
============================
4. バックドア側にアンカーを取りり付けます。
4-1
まず、ソケットレンチ(10mm)を使って、一番下のマルチユースフックを取り外します。
4-2
アンカーをフックの裏側に入れて、アンカーから出ている紐が、貼ってあるホールドテープの方向に出した状態で フックを取り付け直します。
運転席側 取り付け後の画像です。マルチユースフックから紐が テープ側に出ています。
============================
5. ボディー側アンカーを取り付ける
※ところどころ画像は他車種のものになりますが作業内容は同じです。
5-1
まず、ボディー側ウェザーストリップ(黒色のゴムモール)を後方に引き出して 外します。

5-2
車体中央を基準にボディー側アンカーを取り付けますので位置を確認してください。ドアロック金具の中央から、爪付きクリップの内側までが47cmあたりの位置に取り付けます。

5-3
ループ紐の付いた短いテープを、爪付きクリップを使って鉄板に固定します。テープの端と鉄板の端を合わせるようにします。

先に、テープを爪付きクリップに差し込んでから

ハンマーを使って奥までしっかりと打ち込みます。引っ張っても抜けてこなければOKです。
この時アンカーの端を、車外側へ5ミリほどはみ出させて固定してください↓


助手席側にも 同様にしてアンカーを取り付けます。
============================
6. ボディー側ホールドテープを装着する
ウェザーストリップモールの溝の中に ボディー側ホールドテープを差し込みながら 装着していきます。
作業前に ウェザーストリップの鉄芯の状態を確認してください。
CHECK!
ウェザーストリップの鉄芯が開いている(溝に隙間ができている状態)場合は(布地を内張りしているキャンピングカーや、バックドアに網戸を付けている車などに 多く見受けられます)
手で鉄芯を閉じて、溝に隙間がない状態にしてから、ボディ側ホールドテープを差し込んでください。鉄芯(溝)が開いたままだと、ウェザーストリップモールが外れやすいです。
特に、ボディー側アンカー付近は、ウェザーストリップモールが外れる方向に力が、他の部位よりも加わりますので、しっかりと鉄芯が閉じている状態(溝の隙間がない状態)で 元通りに戻し入れてください。
◎ 鉄芯が閉じている(溝の隙間がない状態)

✖ 鉄芯が開いている(溝に隙間ができている状態)

鉄芯を手で閉じて、溝に隙間がない状態にしてから 装着してください。

なお、布地を内張りしているキャンピングカーなどでは、鉄芯(溝)を閉じた状態で、戻し入れるのが困難だったりします。その場合には、鉄芯(溝)を開いた状態で ホールドテープを差し入れながら ウェザーストリップモールをボディ側に元通りに戻し入れ、戻し入れた後から、プライヤーなどを使って しっかりと鉄芯を締めて、ウェザーストリップモールが抜けてこないようにします。
手で鉄芯を閉じて、溝に隙間がない状態にしてから、ボディ側ホールドテープを差し込んでください。鉄芯(溝)が開いたままだと、ウェザーストリップモールが外れやすいです。
特に、ボディー側アンカー付近は、ウェザーストリップモールが外れる方向に力が、他の部位よりも加わりますので、しっかりと鉄芯が閉じている状態(溝の隙間がない状態)で 元通りに戻し入れてください。
◎ 鉄芯が閉じている(溝の隙間がない状態)

✖ 鉄芯が開いている(溝に隙間ができている状態)

鉄芯を手で閉じて、溝に隙間がない状態にしてから 装着してください。

なお、布地を内張りしているキャンピングカーなどでは、鉄芯(溝)を閉じた状態で、戻し入れるのが困難だったりします。その場合には、鉄芯(溝)を開いた状態で ホールドテープを差し入れながら ウェザーストリップモールをボディ側に元通りに戻し入れ、戻し入れた後から、プライヤーなどを使って しっかりと鉄芯を締めて、ウェザーストリップモールが抜けてこないようにします。
まず動画をご覧いただき、装着イメージをつかんでください。
※この動画の車種はD:5ではありませんが、作業内容、要領は同じです。なお、動画では下側から上側に向かって装着していますが、D:5では 上側から下側に向かって装着していきます。
また、下の動画では、キャンピング架装されている車に、付属の「爪付きクリップ」を利用ながら、ホールドテープと網戸も一緒に装着しています。ホールドテープだけを装着する場合にありましても、付属の「爪付きクリップ」を利用することで、確実な装着ができます。
その1、
その2、下側付近は、引き出されようとする力がより強く働きます。「爪付きクリップ」を細かく打ち込んで、入念に固定しています
その3 市販されている、網戸のファスナーを開閉する際に、網戸の下部が モールから抜け出さないように「爪付きクリップ」で補強しています。
動画内で使っている「爪付きアンカー」は、製品に10個 付属させています。追加でお求めいただくこともできます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport
↑
アイズ-ブロッカーのタブをクリックし、表示されたメーカー一覧から車種をご選択ください
■ 装着要領■
①ウェザーストリップモールの溝にボディー側ホールドテープの幅の狭いほうを差し込みます。

②テープを差し込んだ状態のまま、元通りにボディーの鉄板へ はめ込みます。

この作業をすこしずつ繰り返して装着していきます。
※所々に、テープの装着始点部分で使った 「爪付きクリップ」を 打ち込んで固定することで、テープがズレるのを防いで装着がしやすくなります。
上の動画でも使っていますので ご確認ください。
お間違いのないように注意
※注意1:テープはV字に折ってあり、折り幅の狭い方をウェザーストリップモールの溝に差し込みます
※注意2:テープを差し込む場所を間違えないように気を付けてください ↓

※注意2:テープを差し込む場所を間違えないように気を付けてください ↓

下側へ向かってテープ全てを装着していってください。
6-1
まず、ウェザーストリップモールを持って、車の後ろ方向に引き出します。
6-2
ボディー側ホールドテープを上から下側に向かって装着していきます。
装着開始位置は、画像のようにサイドカバーの上端から70~80mm上側の位置から装着しはじめます。(なお、画像では開始位置が分かりやすいように黄色テープを貼っています)
ホールドテープの折り幅の少ない方を ウェザーストリップモールの溝に差し込みながら、

テープがズレるのを防いで装着をしやすくするため、付属の爪付きクリップで止めておきます。爪付きクリップの上からウェザーストリップモールを被せてしまってOKです。

「爪付きアンカー」は、製品に10個 付属させています。追加でお求めいただくこともできます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport
↑
アイズ-ブロッカーのタブをクリックし、表示されたメーカー一覧から車種をご選択ください
ホールドテープとウェザーストリップモールとをボディ側に戻し入れて、手のひらで押し込んでいきます。

※ホールドテープの 裏・表に ご注意ください!!
下画像の指が触れている面は、布地になります(ザラザラ面ではありません)
テープを裏返すとザラザラ面です(このザラザラ面にタープ布が接合されます)
6-3
下側に向かって 装着を繰り返していきます。
※ウェザーストリップモールを車外側から見てみると、シッカリ奥まで入っているかの判断がつきます。
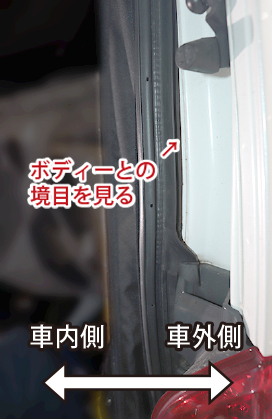
画像のようにベロ(ひだ)が付いている場合はめくって確認します。

↓ 隙間があるので、モールが奥まで入っておらずダメです。モールがシッカリ奥まで入っていれば隙間はありません。

ストップランプの付近の曲線部は、ハサミで 数カ所に切り込みを入れながら装着してください。
テープの下端は、ボディ側アンカーの上まで 装着してください。
下端の曲線部をハサミで 数カ所に切り込みを入れながら装着を進め、ボディー側ホールドテープの端を、ボディー側アンカーに5ミリほど重なるようにカットし…※画像は他車種のものになりますが作業内容は同じです。

重ねた付近を爪付きクリップで固定します


6-4
ホールドテープを装着し終った後で、ウェザーストリップモールの上から ハンマーでモールを打ち込みます。
この作業が大事です。
ホールドテープが装着イメージのイラストと同じ状態で正常に装着されていれば、軽く打ち込むだけでモールは奥まで打ち込めるハズです。打ち込み具合の判断は目視だけでは難しいので、打ち込んでいるときに出る、音や感触で判断します。 高い音・硬い感触になっていればOKです。★鈍い音・柔らかな感触だと モールが奥まで入っていない可能性があります。 一部でもウェザーストリップが浮き上がっていると バックドアの閉まりが悪くなってしまいます。★鈍い音・柔らかな感触のある箇所のモールを 一度引き出して ホールドテープが装着イメージのイラストと同じ状態になっていることを 再度確認してから ハンマーでモールを打ち込んでください。★鈍い音・柔らかな感触から→高い音・硬い感触になっていればOKです。
左右のホールドテープを装着し終えてから バックドアを閉めてみてください。「ドアの閉まりが固くなった感じ」や「ドアが開けにくくなった感じ」がする場合や半ドアになりやすくなった場合には、上記のウェザーストリップの浮き上がりを 再度 確認してみてください。
(特に上側付近に浮き上がりがあると影響が大きいですので、上側付近を入念にチェックしてみてください)
=================================
ここまでの作業が終わった状態で 1時間以上、できれば5時間ほど放置してください(ドアは開放されていても 閉めていてもOKです)。その間にバックドアに貼ったテープの接着力が増し、本来の性能の70%ほどの接着力になります。
夏場の晴れた日の作業でしたら、テープを貼って1時間後には 大丈夫な接着強度になっていたりしますが、できるだけ上記の養生時間を経てから タープ布を装着してください。特に寒冷時や雨の日の作業では 十分な養生時間を経過させてください。
=================================
7. タープ布を取り付ける
7-1
タープ布の車外側になる面には撥水加工処理を行っていますので、以下の方法で車外側を判別し、間違えないように装着してください。
▼タープ布の 運転席側/助手席側 の判別方法▼
運転席側の車内側だけに緑色のAizuのタグがついています。

※最新のタグはコチラ

▼装着時の目印▼
左右のタープ布とも、車内側になる面には薄茶色の面ファスナーが付いています。
これがバックドアの上部(首元)へ来るように装着してください。
(装着終了後は取り外してください)

7-2
タープ布の「袖口(上側)」と「足元(下側)」から出ているショックコードの端部に付いているフックをバックドア側アンカーとボディー側アンカーのそれぞれに接合します。
▼ボディー側アンカーへ▼
アンカーから出ている紐をループ状に広げておき、接合します。接合後はフックの開きを閉じ、タグを取り外してください。先の細いプライヤーで作業するとつなげやすいです。
▼バックドア側アンカーへ▼
さきほどの反対側から出ているフックを、バックドア側アンカーから出ている紐につなげてからフックの開きを閉じてください。
ここまでの作業を行うと運転席側タープ布は、下画像のような状態になります。
7-3
タープ布をホールドテープに接合していきます。①~⑩の順に取り付けを行ってください。
▼取付動画です。(2分42秒)ミツビシD:5ではありませんが、作業の要領は同じです。
▼まず①~⑤です▼
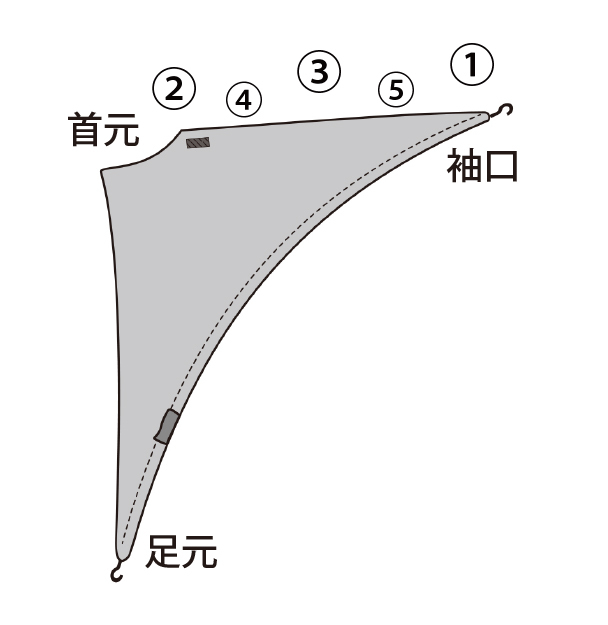
①.アンカー側端部(袖口)を接合します。
まず、端部から15cmほど接合しますが、その際に、小さな黒色テープを取り付けてください。両面がザラザラ面になっている 2cmほどの長さの小さな黒色テープ(2枚)です。
①-1.小さなテープを 下画像のように タープ布の端部を2センチほどを残して ザラザラ面で接合します。

①-2. 2センチほどを残した端部を フック金具を包み込むように折り返して ザラザラ面でに接合します。

①-3.下画像のように、できるだけ固く フック金具を包み込んでください。フック金具とタープ布とが一体になる(ズレ動かない)ようになっていればOKです。
端部の15センチほどを接合します。
車外側から見ると 下画像のようになっています。
②.反対側の端部(首元)を接合します。
15cmほど接合します。タープ布は伸縮性の高い生地ですので1.2倍ほどに伸びます。
強く引き伸ばしていただいても大丈夫です。
③.次に真ん中あたりを接合します。
5cmほど接合します。この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。
残りの④と⑤の辺りを、シワが無いように接合します。
▼次に⑥~⑩です▼

⑥.ボディー側の端部(首元)を接合します。
15cmほど接合します。
バックドア側と同様に、生地を引き伸ばして接合します。
その際に、首元ありのタープ布に張り感が出るように、なおかつあまり張りすぎない程度に接合してください。
ホールドテープの終端部とタープ布の終端部は、一致しません。テープの方が少し(1~2cm)余り気味になるはずです。余ったテープはのちほど切り取れますし、そのまま残しても問題ありません。

この辺りに適度な張り感
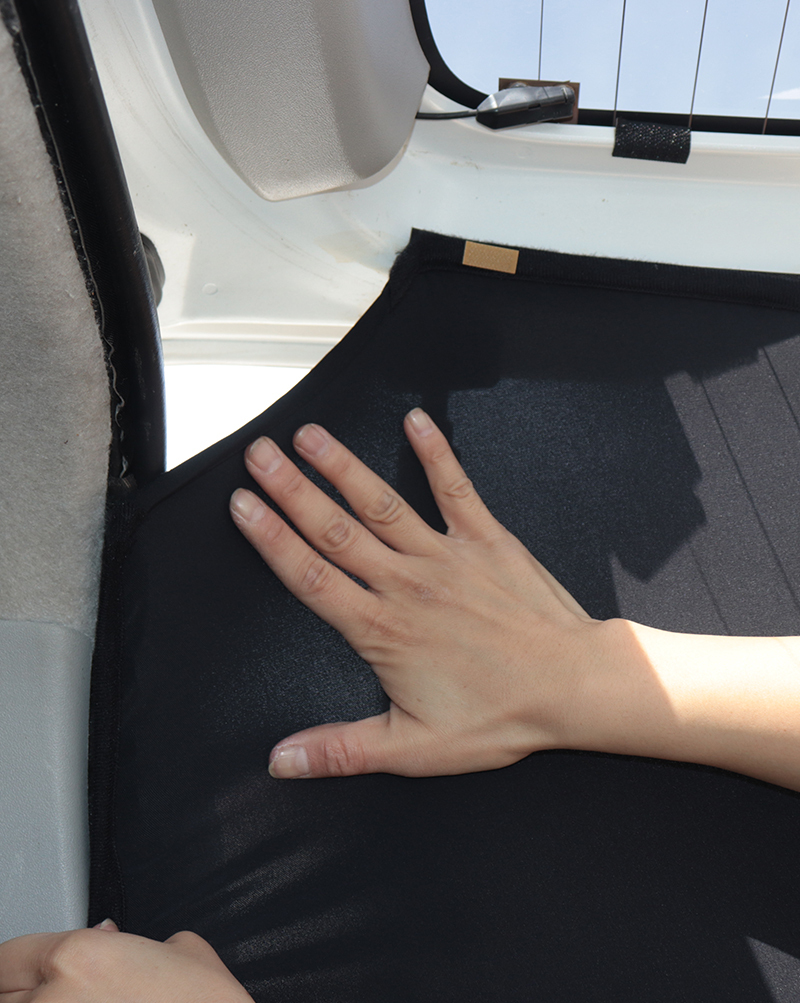
↑※この部分の張りが強すぎますと、バックドアを引き下げる力が強く働き ドアが全開位置に保持しずらくなります。張りが強すぎる場合には、上側方向に装着位置をずらしていく(ボディ側とバックドア側との距離を縮める)ことで 張り具合を 弱めることができます。
⑦.下側端部(足元)を接合します。
端部から15cmほど接合します。
⑧.次に真ん中あたりを接合します。
5cmほど接合します。
この時点では仮装着ですので、軽く付いている程度でOKです。
残りの⑨と⑩の辺りを、シワが無いように接合します。
※もしこの時点でシワが無くキレイに張れていれば、次の「手順8-1」は飛ばしてもらっても構いません※
=================================
8. 貼り具合を調整します
8-1
シワっ気が 残るようでしたら、何度も 剥がしては接合を繰り返して 貼り直してみてください。以下の画像の車両はD:5ではありませんが、作業内容は同じです。
テープ接合を剥がすには、タープ布の内側と外側の両方から 行うとやりやすいです。
シワが出ないようにするコツとしては、生地の一部に たるみが出ないように タープ布の接合部全体にわたって、 同じような引っ張り加減にすることです。
おおむね シワが取れました。
8-2
具合よく張っている状態が確認できたら、タープ布とバックドア側、タープ布とボディー側の 各ホールドテープとの接合部を しっかりと押さえて、接合を強くします
8-3
もし 上側端部のホールドテープが余っているようでしたら ハサミで切り取って整えて下さい。切らなくても性能的には支障はございません。
=================================
9. バックドアの閉まり具合をご確認ください
バックドアを閉めてみてください。
ドアの閉まり具合が固くなった感じがする場合や、半ドアになりやすくなってしまった場合には、6-4 の「ウェザーストリップモールの浮き上がり」を 再度 確認してください。パッと見では浮き上がりがないように見えても、ハンマーでたたいてみると 鈍い音がする場合もあります。
特に上部はわずかな浮きでも閉まり具合に影響します。(下部の浮きは さほどの影響はありません)
バックドアが元通りの全開状態になるかどうかを、ご確認ください。
・アイズ-ブロッカーを装着されたことで、ドアが全開位置に止まらなくなる場合もあります。タープ布の上部付近を上側方向に移動させてみて下さい( ⑥.ボディー側の端部(首元)を接合します。 を参照ください)。
・バックドアを開くガスダンパーが経年劣化で反力が弱まっておりますと、アイズ-ブロッカーを装着されたことで、ドアが全開位置に止まらなくなる場合もあります。
ダンパーを交換される場合には、より反力が強いタイプの「強化ダンパー」などに交換される方が、スキー場などの寒冷化でも また ドアに付加物を装着していて重くなっている場合などでも ドアが全開してくれやすく アイズ-ブロッカーとの相性が良いです。
バックドアを力強く押し上げるための部品は、「D5 強化ダンパー」「D5 補助ステー」などのワード検索でお探しできます。
・ドアが純正よりも より大きく開くダンパーに交換されている場合にありましては、純正状態よりも+7cmほどの高さまでは、タープ布やショックコードは追随できるようになっていますが、張りが強すぎる部分があると、全開位置までにならなかったり、ウェザーストリップモールが引き出される場合があります。ご注意ください。
バックドアを閉めた際に、タープ布がドアに挟まれないかをご確認してみてください。
バックドアを 勢いよく閉めようとするほど タープ布が はさまれやすいです。どこかの窓ガラスやドアを開けた状態で バックドアを閉めていただくと、タープ布が挟まれにくいです。 ドアをゆっくりと閉めていく方法も有効です。
D:5用のアイズ-ブロッカーは、タープ布が挟まれやすい車種になります。ストップランプ横のあたりが 一番挟まれやすいです。
挟まれにくい装着のコツなどを 下記ブログでご案内しています。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9759614.html

取り付け方法のご案内は、以上となります
■ ご使用上の注意点などは こちら でご案内しております。ぜひ一度お読みくださいませ。
============================
■補修部品につきまして。
バックドア側のホールドテープは 最下部の曲線部が一番 剥がれようとする力が働きます。 「この部分だけが剥がれてしまった・・・」場合には、剥がれた部分だけを貼り直すことで補修ができます。20cm+20cm(合計40cm)の長さのホールドテープ と、下地処理用のプライマーを、補修用品として用意しています。
他にも、各種補修部品を下記ページにて ご購入いただけます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/abdetail/577
============================
最後になりますが、
ご使用上で 気になることが ございましたら ご報告いただけますと
今後の改良などへと つなげることができて、ありがたく存じます。
弊社レビュー投稿ページはコチラにあります。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/reviewlist
どうぞ よろしくお願いいたします。
株式会社 アイズ
アイズ-ブロッカー 開発・製作担当者 一同
TEL 053-422-7608
FAX 053-422-7178
info@aizu-rv.co.jp
===================
アイズ-ブロッカーは、 特許取得済です(特許第6862023)
また、上記説明書の営利目的利用はご遠慮下さい。(©aizu2021)
よろしくお願いいたします。
2024年01月06日
ゴム(ショックコード】が切れてしまった場合の 補修方法です。
「ゴム(タープ布の中に内臓されているショックコード) が切れてしまった」 と ご報告くださる方がの多くの場合では、 ゴム自体が切れたのではなく
①ボディ側アンカーのループ紐が切れてしまっている場合 (タープ布を展開していて 大きな力が加わった際には、たいていは このループ紐部分が切れる仕様になっています)
あるいは
②ショックコード端部のフックが ショックコードから外れてしまっている場合
がほとんどです。
それぞれの場合の補修方法を ご案内申し上げます。
なお、正常な状態は下画像のように、 ボディ側アンカーのループ紐に ショックコードの端部についている金属製のフックがつながっている状態です。

アイズ-ブロッカー各部の名称につきましては、 装着ブログの 「各部の名称」 (ページ内の 上から4番目のイラスト図)を参考にしてください。
ハイエースの装着ブログは こちらですが、 https://aizurv2.hamazo.tv/e9683053.html 他の車種につきましては、該当する車種ごとの装着ブログをご覧ください。
+++++++++++++++++++++++++++++++
①ボディ側アンカーのループ紐が切れてしまっている場合
ループ紐に代えて 強めの釣糸などを結んでいただくことで、ボディ側アンカー と ショックコードを つなげることが出来ます。
釣糸は、 PEライン がしなやかで結び易く 扱いやすいです。https://amzn.to/3MWOAsP
100均ショップにもあります。 15KG以上の引張強度がある方がよろしいので、 1.5号ラインの場合には、 2重にして使われる方がベターです。
PEラインは少し滑りますので、結び目には瞬間接着剤で固めておく方法がよろしいかと存じます。
1)ます、PEラインなどで 指3本くらいの大きさのループを作っておきます。

2)作ったループを 下画像のように、ボディ側アンカーに 「ひばり結び(カウ・ヒッチ)」します。

3)ループをアンカーの後ろ側から出した状態でシッカリと締め込んでおき、ループにフックを繋げます。

なお、 抜け出てしまっている ショックコードを 通し直す作業は、下記のブログを参考にして下さい。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9265016.html
ショックコードを通し直す作業では、ゴム通しのようなものが必要なのですが、下記のブログにありますように 色々なもので代用できます。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9263942.html
②ショックコード端部のフックが ショックコードから外れてしまっている場合
1)まず、バックドア側のアンカーとショックコードとを切り離しておきます。

2)フックが外れてしまっているショックコード端部に PEラインなどを巻き付けてから瞬間接着剤を浸み込ませておきます。

3)巻き付けたPEラインを ボディ側アンカーのループ紐につなげて結びます。


4)外してあったバックドア側のアンカーとショックコードとを つなげます。

---------------------
たいていは ユーザー様ご自身で、100均ショップにもあるPEラインなどを使って 上述の方法で補修されている場合が多いですが、補修部品の「ボディ側アンカー」が ご入用でしたら 下記ページにて ご購入いただけます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/haab#support_goods
ページの中ほどにありますところの、 ボディ側アンカー(2個)セット です。
3、ショックコード と アンカーのワイヤー部分とをつないでいるフックが ショックコード端部から外れてしまった場合について。
また、交換用の ショックコード自体(ゴム紐の両端に接続用フックが付いているものを用意いたします)をお送りすることもできます。
サポート商品販売ページにて ご購入いただけます。 https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/haab
抜け出てしまっている ショックコードを 通し直す作業は、下記のブログを参考にして下さい。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9265016.html
ショックコードを通し直す作業では、ゴム通しのようなものが必要なのですが、下記のブログにありますように 色々なもので代用できます。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9263942.html
ショックコードの関連する不具合のほとんどは、前述の 1、や 2、や 3、です。
たいていは ユーザー様ご自身で、100均ショップにもあるPEラインなどを使って 上述の方法で 補修されている場合が多いですが、弊社からの 補修部品が ご入用のようでしたら お申しつけください。たいていは 翌営業日に お送りできます。
======================
アイズ-ブロッカーは、 発売開始してから 2年ほど過ぎたあたりから、「ボディ側アンカーが 切れてしまった」「ゴムが切れてしまった」 のお申し出が増えました。
アイズブロッカーは、5m/秒 ほどの風にも 大丈夫ですが、
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/reviewdetail/1014
タープ布が強く押される(あるいは引っ張る)ようなことがあると、内臓されているショックコード(ゴム紐)が伸び切ってしまいます。
伸びで追随できないほどになると、ボディ側あるいはドア側のアンカー部分に 直接の力が働くこととなり、ループ紐が切れたり アンカーが抜けたりの支障につながることがあります。ご注意いただければと存じます。
夜の暗さの中で、タープ布の存在に気づかれない方がタープ布に衝突(?)してしまって、( ユーザー様以外の場合が多いです。弊社スタッフも よくやります・・・ )ショックコードの不具合につながったりもします。夜中でもタープ布の存在に気づけるように、ショックコード(ゴム紐)部分に、蓄光性の目印 や https://onl.tw/uWC46QG、小さな ランタン https://onl.tw/EGdALBv などを吊り下げることをされているユーザー様もいらっしゃいます。
①ボディ側アンカーのループ紐が切れてしまっている場合 (タープ布を展開していて 大きな力が加わった際には、たいていは このループ紐部分が切れる仕様になっています)
あるいは
②ショックコード端部のフックが ショックコードから外れてしまっている場合
がほとんどです。
それぞれの場合の補修方法を ご案内申し上げます。
なお、正常な状態は下画像のように、 ボディ側アンカーのループ紐に ショックコードの端部についている金属製のフックがつながっている状態です。

アイズ-ブロッカー各部の名称につきましては、 装着ブログの 「各部の名称」 (ページ内の 上から4番目のイラスト図)を参考にしてください。
ハイエースの装着ブログは こちらですが、 https://aizurv2.hamazo.tv/e9683053.html 他の車種につきましては、該当する車種ごとの装着ブログをご覧ください。
+++++++++++++++++++++++++++++++
①ボディ側アンカーのループ紐が切れてしまっている場合
ループ紐に代えて 強めの釣糸などを結んでいただくことで、ボディ側アンカー と ショックコードを つなげることが出来ます。
釣糸は、 PEライン がしなやかで結び易く 扱いやすいです。https://amzn.to/3MWOAsP
100均ショップにもあります。 15KG以上の引張強度がある方がよろしいので、 1.5号ラインの場合には、 2重にして使われる方がベターです。
PEラインは少し滑りますので、結び目には瞬間接着剤で固めておく方法がよろしいかと存じます。
1)ます、PEラインなどで 指3本くらいの大きさのループを作っておきます。

2)作ったループを 下画像のように、ボディ側アンカーに 「ひばり結び(カウ・ヒッチ)」します。

3)ループをアンカーの後ろ側から出した状態でシッカリと締め込んでおき、ループにフックを繋げます。

なお、 抜け出てしまっている ショックコードを 通し直す作業は、下記のブログを参考にして下さい。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9265016.html
ショックコードを通し直す作業では、ゴム通しのようなものが必要なのですが、下記のブログにありますように 色々なもので代用できます。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9263942.html
②ショックコード端部のフックが ショックコードから外れてしまっている場合
1)まず、バックドア側のアンカーとショックコードとを切り離しておきます。

2)フックが外れてしまっているショックコード端部に PEラインなどを巻き付けてから瞬間接着剤を浸み込ませておきます。

3)巻き付けたPEラインを ボディ側アンカーのループ紐につなげて結びます。


4)外してあったバックドア側のアンカーとショックコードとを つなげます。

---------------------
たいていは ユーザー様ご自身で、100均ショップにもあるPEラインなどを使って 上述の方法で補修されている場合が多いですが、補修部品の「ボディ側アンカー」が ご入用でしたら 下記ページにて ご購入いただけます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/haab#support_goods
ページの中ほどにありますところの、 ボディ側アンカー(2個)セット です。
3、ショックコード と アンカーのワイヤー部分とをつないでいるフックが ショックコード端部から外れてしまった場合について。
また、交換用の ショックコード自体(ゴム紐の両端に接続用フックが付いているものを用意いたします)をお送りすることもできます。
サポート商品販売ページにて ご購入いただけます。 https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/haab
抜け出てしまっている ショックコードを 通し直す作業は、下記のブログを参考にして下さい。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9265016.html
ショックコードを通し直す作業では、ゴム通しのようなものが必要なのですが、下記のブログにありますように 色々なもので代用できます。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9263942.html
ショックコードの関連する不具合のほとんどは、前述の 1、や 2、や 3、です。
たいていは ユーザー様ご自身で、100均ショップにもあるPEラインなどを使って 上述の方法で 補修されている場合が多いですが、弊社からの 補修部品が ご入用のようでしたら お申しつけください。たいていは 翌営業日に お送りできます。
======================
アイズ-ブロッカーは、 発売開始してから 2年ほど過ぎたあたりから、「ボディ側アンカーが 切れてしまった」「ゴムが切れてしまった」 のお申し出が増えました。
アイズブロッカーは、5m/秒 ほどの風にも 大丈夫ですが、
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/reviewdetail/1014
タープ布が強く押される(あるいは引っ張る)ようなことがあると、内臓されているショックコード(ゴム紐)が伸び切ってしまいます。
伸びで追随できないほどになると、ボディ側あるいはドア側のアンカー部分に 直接の力が働くこととなり、ループ紐が切れたり アンカーが抜けたりの支障につながることがあります。ご注意いただければと存じます。
夜の暗さの中で、タープ布の存在に気づかれない方がタープ布に衝突(?)してしまって、( ユーザー様以外の場合が多いです。弊社スタッフも よくやります・・・ )ショックコードの不具合につながったりもします。夜中でもタープ布の存在に気づけるように、ショックコード(ゴム紐)部分に、蓄光性の目印 や https://onl.tw/uWC46QG、小さな ランタン https://onl.tw/EGdALBv などを吊り下げることをされているユーザー様もいらっしゃいます。
2023年11月09日
D:5用アイズ-ブロッカーの挟まれにくい閉め方のご案内
D:5用のアイズ-ブロッカーは、タープ布が挟まれやすい車種になります。
ストップランプ横のあたりが 一番挟まれやすいです。

ドアをゆっくりと閉めていくことで 挟まれにくくなります。
動画では 分かりやすいように とてもゆっくりと閉めていますが、最後の20センチくらい手前で 閉めるのを一度止めてから ドアの重みで閉めるようにするとイイです。そんな やさしい閉め方では 半ドア状態になってしまうから・・・と、勢いよく閉めてしまうと、たいていはタープ布が 外側に膨らんでしまって 挟み込まれてしまいます。 ドアを勢いよく閉めようとするほど タープ布が挟まれやすくなります。
●アイズブロッカーを装着したことで 半ドア状態になりやすくなった場合には、装着ブログ https://aizurv2.hamazo.tv/e9771182.html の
「9. バックドアの閉まり具合をご確認ください 」を参照ください。
また
●ドアを勢いよく閉めると、タープ布が挟まれてしまう作用につきましては こちらの「ご使用上の注意」を参照ください。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9170018.html 【タープ布の挟み込み】 を参照ください。
===
ストップランプ横のあたりが 一番挟まれやすいですが、
この付近の装着具合を調整することでも 挟まれにくくすることができます。
ボディ側ホールドテープに接合する際に、
ストップランプ横あたり(下画像の矢印の範囲)のタープ布を ほかの箇所よりも引き伸ばし気味にしながら ホールドテープに接合します。


ドアが閉まっていく際に、その部分のタープ布は 他の部分よりも縮みやすくなっていることで、タープ布はストップランプ横の凸状部分の内側へと入って行きやすくなります。その結果 凸状部分に引っかかりにくくなり、挟み込まれにくくなります。

また、挟まれた状態のままにしておくと、折りクセがついてしまうことで、同じような挟み込みになりやすいです。
タープ布を車内側に引き入れておくことで 折りクセを直せる場合があります。お試しください。
なお、ストップランプ横以外の箇所のタープ布は ゆるみ気味となり、ゆるみが 1カ所に集中すると その箇所がシワになりやすくなります。ゆるみが集中しないように 接合していってください。
接合のし直しを繰り返していって、出来るだけシワの無い張り具合に調整してください。

ストップランプ横のあたりが 一番挟まれやすいです。

ドアをゆっくりと閉めていくことで 挟まれにくくなります。
動画では 分かりやすいように とてもゆっくりと閉めていますが、最後の20センチくらい手前で 閉めるのを一度止めてから ドアの重みで閉めるようにするとイイです。そんな やさしい閉め方では 半ドア状態になってしまうから・・・と、勢いよく閉めてしまうと、たいていはタープ布が 外側に膨らんでしまって 挟み込まれてしまいます。 ドアを勢いよく閉めようとするほど タープ布が挟まれやすくなります。
●アイズブロッカーを装着したことで 半ドア状態になりやすくなった場合には、装着ブログ https://aizurv2.hamazo.tv/e9771182.html の
「9. バックドアの閉まり具合をご確認ください 」を参照ください。
また
●ドアを勢いよく閉めると、タープ布が挟まれてしまう作用につきましては こちらの「ご使用上の注意」を参照ください。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9170018.html 【タープ布の挟み込み】 を参照ください。
===
ストップランプ横のあたりが 一番挟まれやすいですが、
この付近の装着具合を調整することでも 挟まれにくくすることができます。
ボディ側ホールドテープに接合する際に、
ストップランプ横あたり(下画像の矢印の範囲)のタープ布を ほかの箇所よりも引き伸ばし気味にしながら ホールドテープに接合します。

ドアが閉まっていく際に、その部分のタープ布は 他の部分よりも縮みやすくなっていることで、タープ布はストップランプ横の凸状部分の内側へと入って行きやすくなります。その結果 凸状部分に引っかかりにくくなり、挟み込まれにくくなります。

また、挟まれた状態のままにしておくと、折りクセがついてしまうことで、同じような挟み込みになりやすいです。
タープ布を車内側に引き入れておくことで 折りクセを直せる場合があります。お試しください。
なお、ストップランプ横以外の箇所のタープ布は ゆるみ気味となり、ゆるみが 1カ所に集中すると その箇所がシワになりやすくなります。ゆるみが集中しないように 接合していってください。
接合のし直しを繰り返していって、出来るだけシワの無い張り具合に調整してください。

2023年10月30日
アイズ-ストッパー のハンドル位置調整の方法
アイズ-ストッパーをお使いいただいていると、ハンドルレバーの固定位置がだんだんと進んで行きます。
装着当初は 2時(軽い固定)~3時(強い固定)付近の固定位置だったものが

⇓
長らくお使いいただく中で、目いっぱい締め込むと 4時くらいの位置へと進んでしまう場合があります。

4時くらいまでは支障なくお使いいただけるかと存じますが、5時を過ぎてくるとハンドル固定がしづらくなりますので、以下に対策をご案内いたします。
対策1:固定ボルトの緩みの有無を確認してください。
本体Aと本体Bを固定している 2本のボルトが、緩んでいないかをご確認ください。
このボルトが緩んでいると、ハンドルを固定した際の位置が進んでしまいます
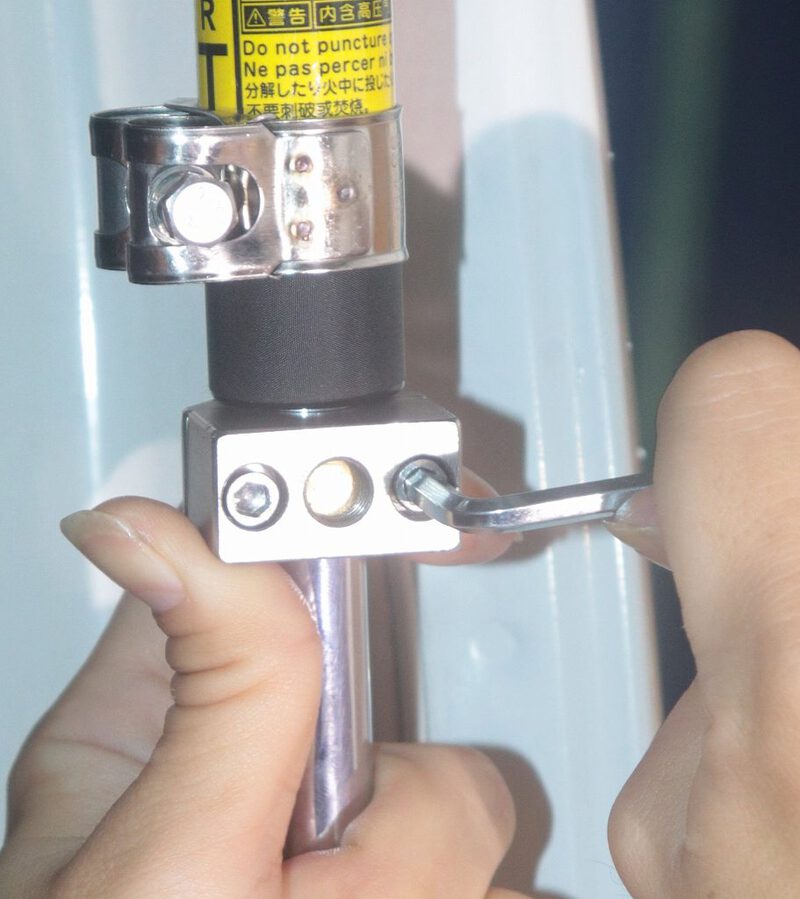
↓↓
2本のボルトがしっかりと固定されていても、ハンドル固定位置が進んでしまっている場合には対策2を実施ください。
↓↓
対策2:「調整用シム」を使用する
ハンドルボルトと真鍮スペーサーとの間に入れることで、進み過ぎた固定位置を戻すことができます。
「調整用シム」は、0.1mmの厚さのステンレス製の小さなスペーサーです。
下記のサポート商品販売ページにて お求めいただけます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport#6099
●使い方
ハンドルを外して、ハンドル穴(ナット穴)の中に「調整用シム」を入れてから、ハンドルを戻し入れるだけでOKです。
「調整用シム」には、薄い粘着材が付いています。白いシールをはがしてから 穴の中の真鍮スペーサーに貼り付けてください。


ハンドルレバーのボルトの先に貼り付けておいてから、ハンドルを戻し入れる方法でもかまいません。

⇓
4時の位置から 3時前の位置に戻すことができました。

「調整用シム」は、とても薄くて小さな部品ですが、ハンドル固定位置を戻していくことで、操作感を向上させることができます。
=================
★調整用シムの代用方法
「調整用シム(スペーサー)」は、0.1mm厚のステンレス製シートに薄い粘着材を張り付けて、直径7mmの円形状にしたものです。
他の素材で代用することもできます。
例えば
・アルミ缶(0.2㎜~0.3mm厚)
・ペットボトル(0.2㎜~0.3mm厚)
・クリアホルダー(0.2㎜厚くらい)
などを 直径7mmくらいの円形状に小さく切って使っても 上記と同様の調整ができます。

粘着材を付けなくてもOKです。アルミ缶やペットボトルは、0.2mm厚くらいありますので、ハンマーでたたいて薄くしておいてから挿入する方がアルミ板が硬く・薄くなってくれるので具合が良いです。
なお、アルミやプラスチックなどの素材よりも、真鍮やステンレスなどの硬い素材の方が、固定具合にカチッと感が出るのでベターではあります。
装着当初は 2時(軽い固定)~3時(強い固定)付近の固定位置だったものが

⇓
長らくお使いいただく中で、目いっぱい締め込むと 4時くらいの位置へと進んでしまう場合があります。

4時くらいまでは支障なくお使いいただけるかと存じますが、5時を過ぎてくるとハンドル固定がしづらくなりますので、以下に対策をご案内いたします。
対策1:固定ボルトの緩みの有無を確認してください。
本体Aと本体Bを固定している 2本のボルトが、緩んでいないかをご確認ください。
このボルトが緩んでいると、ハンドルを固定した際の位置が進んでしまいます
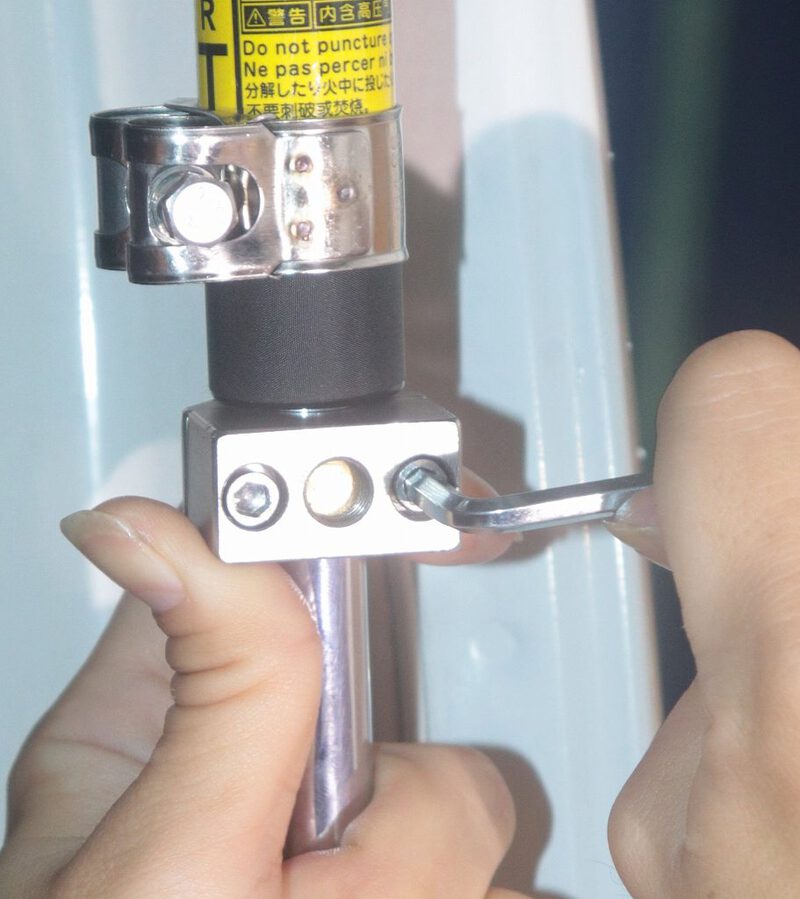
↓↓
2本のボルトがしっかりと固定されていても、ハンドル固定位置が進んでしまっている場合には対策2を実施ください。
↓↓
対策2:「調整用シム」を使用する
ハンドルボルトと真鍮スペーサーとの間に入れることで、進み過ぎた固定位置を戻すことができます。
「調整用シム」は、0.1mmの厚さのステンレス製の小さなスペーサーです。
下記のサポート商品販売ページにて お求めいただけます。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport#6099
●使い方
ハンドルを外して、ハンドル穴(ナット穴)の中に「調整用シム」を入れてから、ハンドルを戻し入れるだけでOKです。
「調整用シム」には、薄い粘着材が付いています。白いシールをはがしてから 穴の中の真鍮スペーサーに貼り付けてください。


ハンドルレバーのボルトの先に貼り付けておいてから、ハンドルを戻し入れる方法でもかまいません。

⇓
4時の位置から 3時前の位置に戻すことができました。

「調整用シム」は、とても薄くて小さな部品ですが、ハンドル固定位置を戻していくことで、操作感を向上させることができます。
=================
★調整用シムの代用方法
「調整用シム(スペーサー)」は、0.1mm厚のステンレス製シートに薄い粘着材を張り付けて、直径7mmの円形状にしたものです。
他の素材で代用することもできます。
例えば
・アルミ缶(0.2㎜~0.3mm厚)
・ペットボトル(0.2㎜~0.3mm厚)
・クリアホルダー(0.2㎜厚くらい)
などを 直径7mmくらいの円形状に小さく切って使っても 上記と同様の調整ができます。

粘着材を付けなくてもOKです。アルミ缶やペットボトルは、0.2mm厚くらいありますので、ハンマーでたたいて薄くしておいてから挿入する方がアルミ板が硬く・薄くなってくれるので具合が良いです。
なお、アルミやプラスチックなどの素材よりも、真鍮やステンレスなどの硬い素材の方が、固定具合にカチッと感が出るのでベターではあります。
2023年09月20日
アイズ-ストッパー(ハイエース用)の装着・ご使用の説明書(2023年9月19日以降)
≪はじめに≫
本コンテンツは2023年9月19日以降の生産のアイズ-ストッパー(ハイエース、標準ルーフ、ミドルルーフ、ハイルーフ 車用)の装着・ご使用の説明書です。

≪ご注意≫
※アイズ-ストッパーは、トヨタ純正のダンパー(純正強化ダンパー含む)用です。
社外品の強化ダンパーやハイリフトダンパーなどには、適合しない可能性があります。
また、ハイエースⅠ型で装着されていた仕様のダンパー(下画像参照)には、ステー部分を加工しないと装着できません。

↑
ロッドとステーのジョイント部分が車外側を向いているタイプのダンパーです。赤丸部分が干渉します。
ステー部分を 下画像のように加工(ステー部分を削っています)することで、装着が可能になります。

※バックドアの重さが10kg以上増えている状態で全開位置で固定しないで下さい。
バックドアに自転車を積載した場合など、重量が増えたドアを全開位置で固定すると、テコの原理でドアを支えるダンパーには、100kg・f 以上のとても大きな荷重が加わります。ダンパーの取り付け部分の強度が耐えられず 破損する恐れがあり大変危険です。詳細は当説明書の一番最後の「ご使用方法・ご注意」をご覧下さい。
※装着後は各箇所、ボルトが緩んでいないかなどの定期的な確認をお願いいたします。
===========================
≪商品内容≫

真鍮スペーサーの紛失にご注意ください!!
※上画像の本体Bの黄色テープの中に、ダンパーロッドを固定するための真鍮製スペーサー入っています。小さな部品ですので、紛失にご注意ください。

万一の紛失時には、補修部品としてのご用意はありますが、全ての部品をセットで弊社に返送いただき再調節する必要があります。
≪各部の名称≫

≪装着動画≫
10分弱の装着動画です。 標準ルーフ車ですが、ミドルルーフ車、ハイルーフ車も装着方法は同じです。
下記の装着説明と併せて、一度ご覧いただければと存じます。YouTubeでご覧いただくと、説明用の字幕も見れます。
==================
【装着作業に先立ちまして】
本製品は、基本的には運転席側のバックドアダンパーに装着します。
●運転席側での操作状況は 下画像のようになります。

ハンドルを車外側へ回して固定し、解除時はハンドルを上側でホールドさせます。

●助手席側への装着も可能ですが、操作状況が運転席側とは違ってきますのでご注意ください。
助手席側での操作状況は 下画像のように 2通りの操作状況があります。一般的には運転席側での操作状況の方がお勧めです。
①固定時には、ハンドルが車内側になる操作状況にする場合。解除時は上側でホールドします。

②固定時には、ハンドルが車外側になる操作状況にする場合。解除時には3/4回転させてから上側でホールドします。

下記説明書では、まず運転席側への装着をご説明しています。助手席側への装着説明は、この説明書の一番最後で、補足説明的にご案内しております。
助手席側への装着される場合には、まず 運転席側への装着説明をご一読いただいた後で、助手席側への装着の補足説明をご覧下さい。
============================================
1.シリンダー位置の回転
運転席側バックドアダンパーのシリンダーをつかんで、反時計方向(上側から見て左回転)に止まるまで回しておきます。


2.保護テープと本体固定用クランプの取り付け
2- ①
シリンダーの最下部に保護テープを貼ります。(テープの下端と、シリンダーの下端を揃えます)

保護テープの上から爪でシリンダーの溝をなぞり、しっかりと溝を作ってください。(重要)

2- ②
本体固定用クランプのボルトを付け替えます。
元から付いているボルトを外します。ボルト頭側についているスペーサーも一緒に外します。

↓
ボルトを抜く際に、受け側のナットが外れますので、落として無くさないように注意してください。


↓
六角穴付きのボルトに付け替えます。差し込んだだけだと長さが足りていませんが大丈夫です。

2- ③
本体固定用クランプを 、ロッドの部分で取付けて、その後で シリンダーの保護テープの上側付近で仮固定します。
クランプは、最終的にはシリンダーの位置で締め付けるものですが、まずはロッドの位置でハメ入れます。ハメ入れたら、クランプを握り、締め付けて癖をつけてください。
※シリンダーの位置で輪っか状態にするのは大変なので、ロッド位置で輪っかにしてからシリンダーの位置へスライドさせます。

Aとナットとの間隙を「ギュッ」として縮めておきます。広いままですと ボルトがナット側に届きません。

↓
ボルトを 右側から左側のナットへと入れて、少しだけ回してクランプを輪っか状態にしておきます。 斜めに入らないように注意しながら手で回し入れます。もし斜めに入ると数回転させた時点で固くなります。入れ直してください。

↓
クランプをシリンダーの位置へと移動させます。落ちてこないように、付属の六角レンチで軽く締め付けておきます。この時、ボルト頭の位置はシリンダーの左側(車内側)になるようにします。

※もし短いボルトでの締め付けが難しいようでしたら、元の長いボルトを 8mmレンチを使って締めこみ、ナットとⒶ(上から2枚目の画像に記載)との間隔を狭めて形状に癖を付けておいてから、六角穴付きボルトで締め付けます。
3.本体Aの仮固定
3- ①
本体Aを、本体固定用クランプで仮固定していきます。まず、本体Aの爪部分をシリンダーの溝へしっかり ハメ入れます。その際、下記注意事項を必ずご確認ください。

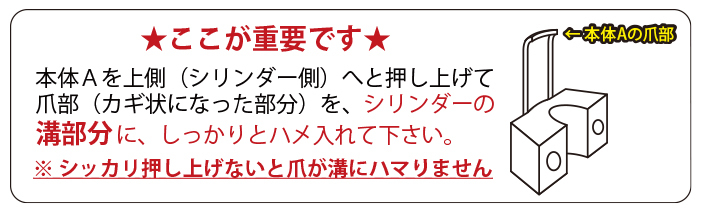
3- ②
本体Aを仮固定する際の向きは、本体Aのボルト穴や 固定用クランプのボルト頭が、車体の真後ろ~少し右側方向(車外側方向)を向いている状態にします。

↓※画像では本体Aに本体Bがすでに接合されていますが、この段階では本体Aのみの固定となります。

3- ③
本体Aを、本体固定用クランプで仮固定します。
爪部の上をクランプで固定します。左画像の赤線付近に、シリンダーの溝部分がくるようにします。
ボルト頭は、シリンダーの左(車内側)で締めます。ボルト頭が、「車体の真後ろ」を向いている状態で固定します。

下図のように必ず爪部の上をクランプで押さえている状態になるように固定してください。
爪が外れていないかいま一度、確認してください。



付属の六角レンチを使って、この段階では緩めに固定しておきます。
※本体Aが落ちてこない程度には締め付けてください。

4.本体Aに本体Bを固定
仮固定された本体Aに、本体Bを抱き合わせて、5mmボルト2本で六角レンチを使って、しっかりと固定します。

↓
【 注意 1 】真鍮スペーサーの脱落防止用に貼ってあるテープは取り除いてください。真鍮スペーサーの紛失にご注意ください!
【 注意 2 】本体Aに本体Bを合わせる際には、。必ず、本体Bの 赤いポンチ マークを下側にして、抱き合わせてください。
(運転席側へ装着する場合です)
【 注意 3 】真鍮スペーサーの凹面がダンパーロッドの凸面に必ず面で当たるように調整して固定してください。※下図参照(真鍮スペーサーは、中で回転させることができます)

上の注意事項を守りながら固定します。

5.ハンドルの取り付け
本体Bのナット穴に、ハンドルのボルト部を回し入れ右回転させていって軽く止めます。ボルト部がナット穴に対して、斜めに入らないようにご注意ください。
ハンドルの回転中心部を、下画像のように親指で押えながら回し入れていくと 斜めにならないで入ってくれやすいです。
もし 斜めに入れてしまった場合には、少し回した時点で固くなります。そのまま締めてしまうと固着してしまいますので、無理に回そうとはしないで 反回転させて ボルト部分をいったん抜き出してから、まっすぐに入れ直してください。
ボルト部を真っすぐに回し入れます

↓
ハンドルはクルクルと軽く入って行くハズです。もし 少し回した時点で固くなるようでしたら、無理に回そうとはしないで ボルト部分をいったん抜き出してから、まっすぐに入れ直してください。

↓
ハンドルの動きが止まった際の、ハンドルの傾きは下画像のようになるハズです(2時くらいの方向)。

もし、このような位置で止まらない場合は…、
①:ひとつ前の項目「手順4」の 「【 注意 2 】本体Aに本体Bを合わせる際には、必ず、本体Bの 赤いポンチマークを下側にして抱き合わせてください。」 を今一度確認して、赤いポンチマークが下側になるように付け直してください。
②:ひとつ前の項目「手順4」の 「【 注意 3 】真鍮スペーサーの凹面がダンパーロッドの凸面に必ず面で当たるように調整して固定してください。」 を今一度確認してください。
6.各部がドアに当たらないことを確認してください
アイズ-ストッパーを装着後、ドアをゆっくりと閉めていって、本体やクランプやハンドルの各部がドアに当たらないことを確認してください。
この段階では、ドアを固定しようとしないでください!! 本体がまだ仮固定の状態ですのでドアを固定できません。固定しようとすると不具合の原因となりますので、ご注意ください。
6- ①
ハンドルの黒色キャップの中には、磁石が内臓されていてハンドルを真上方向にした際には、磁石の吸着力によりハンドルを真上方向位置で仮ホールドできます。ハンドルを真上方向位置で仮ホールドした状態にしてから、ドアをゆっくりと閉めて行ってください。

6- ②
ドアが閉まり切る直前でいちど止めてみて、本体やハンドルがバックドア側の当たりそうな位置に、付属のキズ付き防止のスポンジテープを貼ります。次に、ドアを最後まで閉めてみて、各部がバックドア側に当たっていないかを確認してください。
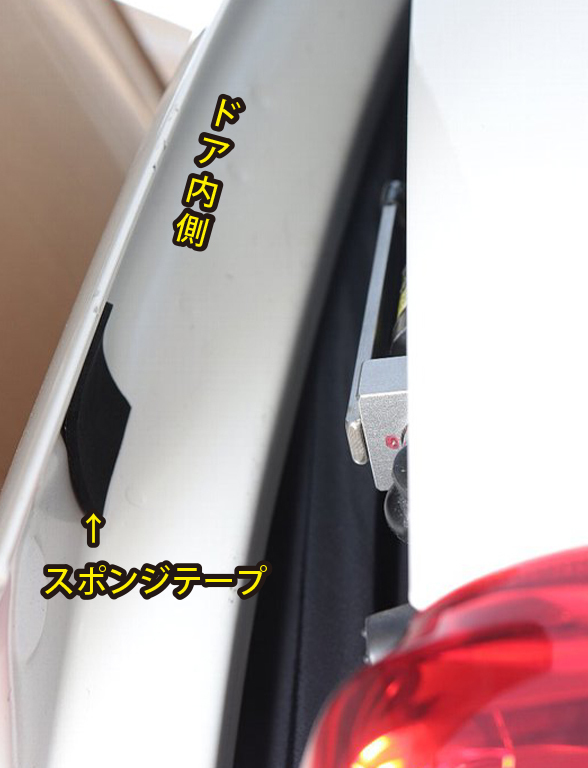
6- ③
シリンダーは、ドアの開閉に伴って、わずかに回転するようになっています。シリンダーの「ドアの開いた状態での回転位置」「ドアの閉じた状態での回転位置」それぞれに対し、ドア内側に当たらないことを確認してください。


↑
手首の角度に注目。これくらい回転するマージンがあります。
ほとんどの お車では、全開からドアを閉めていくに従い、シリンダーは時計回り(上から見て右回転)に回りますが、ハイエースの中には、閉めていくに従い、シリンダーが反時計回り(上から見て左回転)に回る お車もあります。本体やホルダーの各部がボディやドアに当たらない、車両個体差を考慮した最大公約数的な位置として、「ドア全開時に シリンダーを反時計まわりに回して止めた位置で、各ボルトの頭が車体の真後ろ~少し右側方向」と しておりますが、お車によっては、「車体の真後ろ~少し左側方向」が具合が良い場合もあります。 お車の状況に応じて本体の方向を 具合が良い位置に調節してください。
7.本体固定用クランプの本固定
7- ①
各部がボディやドアに当たらないことをご確認いただいた後に、その位置で本体固定用クランプのボルトを付属の六角レンチを使って、シッカリと本締めしてください。
※その際に、下に記載した注意2点を、今一度確認してから本固定してください。
①:シリンダーの溝部分に爪部(カギ状になった部分)が、しっかりと入っていること(手順 3 を参照ください)
②:爪部の上をクランプでしっかり締め付けている状態になっていること(手順 3-③ を参照ください)

【溝部分に爪部が入り込んでいないと、ドアを半開固定した際にズレ動いてしまします!! 】
ドアが開いていかないように アイズ-ストッパーで固定してもズレ動いてしまう場合には、溝部分に爪部が入っていないことが原因であったりします。
クランプを強力に締め付けることでは、ズレ止めはできません。必ず爪部が溝部分に入っている必要があります爪部が溝部分に入っている状態(本体をしっかりと押し上げている状態)で しっかりと力いっぱい締め付けてください。
7- ②
固定具合を 必ずご確認ください !!
ここで一度、ドアを少し開いたところで、アイズ-ストッパーのハンドルを 時計の針でいうところの 2時~3時くらいの位置まで締め込み、 ドアをしっかりと固定してみてください。

ドアを固定した状態で、ドアを開く方向に少しゆり動かしてみたときに、本体がズレ動かないことを確認してください。

下画像のように 本体とシリンダーとの間に ほとんど 隙間がないのが正常な(ズレ動いていない)状態です

下画像のように 本体とシリンダーとの間に隙間が生じていると、本体がズレ動いてしまっている状況です!!!
なお、シリンダーの溝部分に爪部が、しっかりと入っている状態でしたら、2mmくらいの隙間があっても大丈夫です。

もし、ドアを開く方向に少しゆり動かしてみたときに 隙間が2mm以上に広がっていくようでしたら、、シリンダーの溝部分から爪部が出てしまっています。
それ以上 ドアを開くことを止めて、もう一度本体Aを上側(シリンダー側)へとしっかりと押し上げて爪部(カギ状になった部分)がシリンダの溝部分に確実に入っている状態で、ボルトを強く締めあげてください。


7- ③
ドアを半開状態に固定した際に外側に突き出ているハンドルがボディー側に当たらないかを確認してください。

支障があるようなら本体固定用クランプを緩めて、本体の方向を修正してください。


8.上側ホルダー用磁石の貼付け
8-1
ハンドルの黒色キャップの中には、磁石が入っています。その磁石に対して、付属の「上側ホルダー用磁石」を吸着させます。
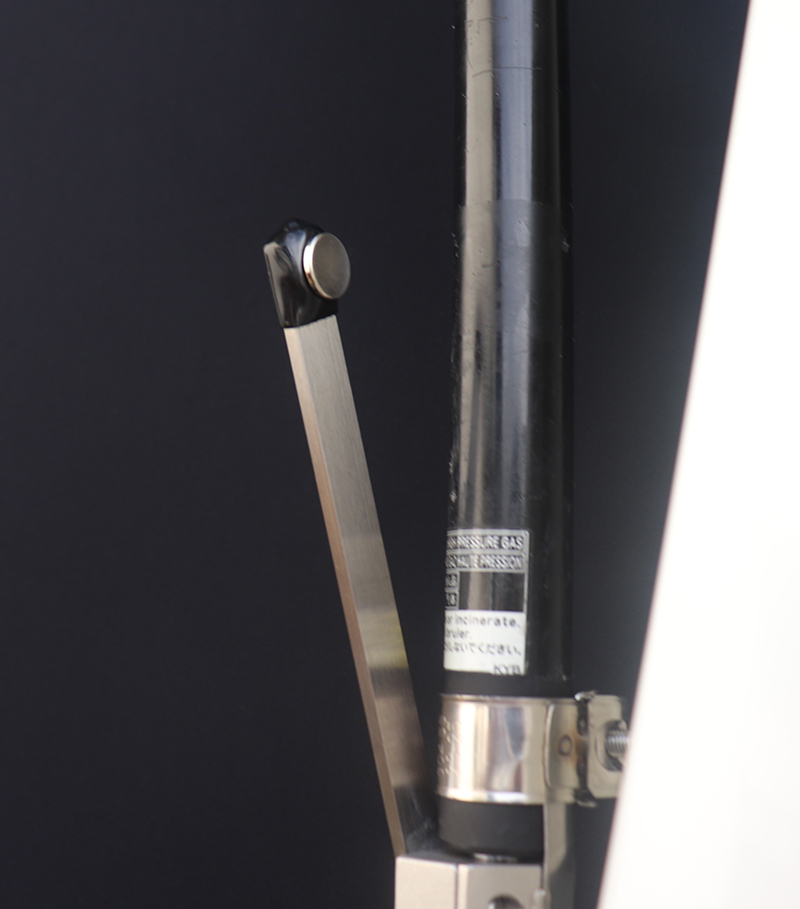
8-2
ハンドルを真上方向にした位置で、ハンドル側に吸着させている「上側ホルダー用磁石」を、シリンダー側へと吸着替えします。
「上側ホルダー用磁石」を ハンドルの黒色キャップ側から シリンダー側へと移し替えます(磁力でシリンダーに貼りつかせます)


8-3
ハンドルは左回転させて下側に垂らしておき、シリンダーに貼りつかせている磁石の上から、「上側ホルダー用テープ」を貼ります。

※もし貼るのを失敗してしまったり、紫外線等で痛んできてしまった場合は、ビニールテープで代用して下さい。
8-4
「黒色キャップの中の磁石」と、「上側ホルダー用磁石」とが引き合う磁力により、ハンドルを真上方向にホールドすることができます。
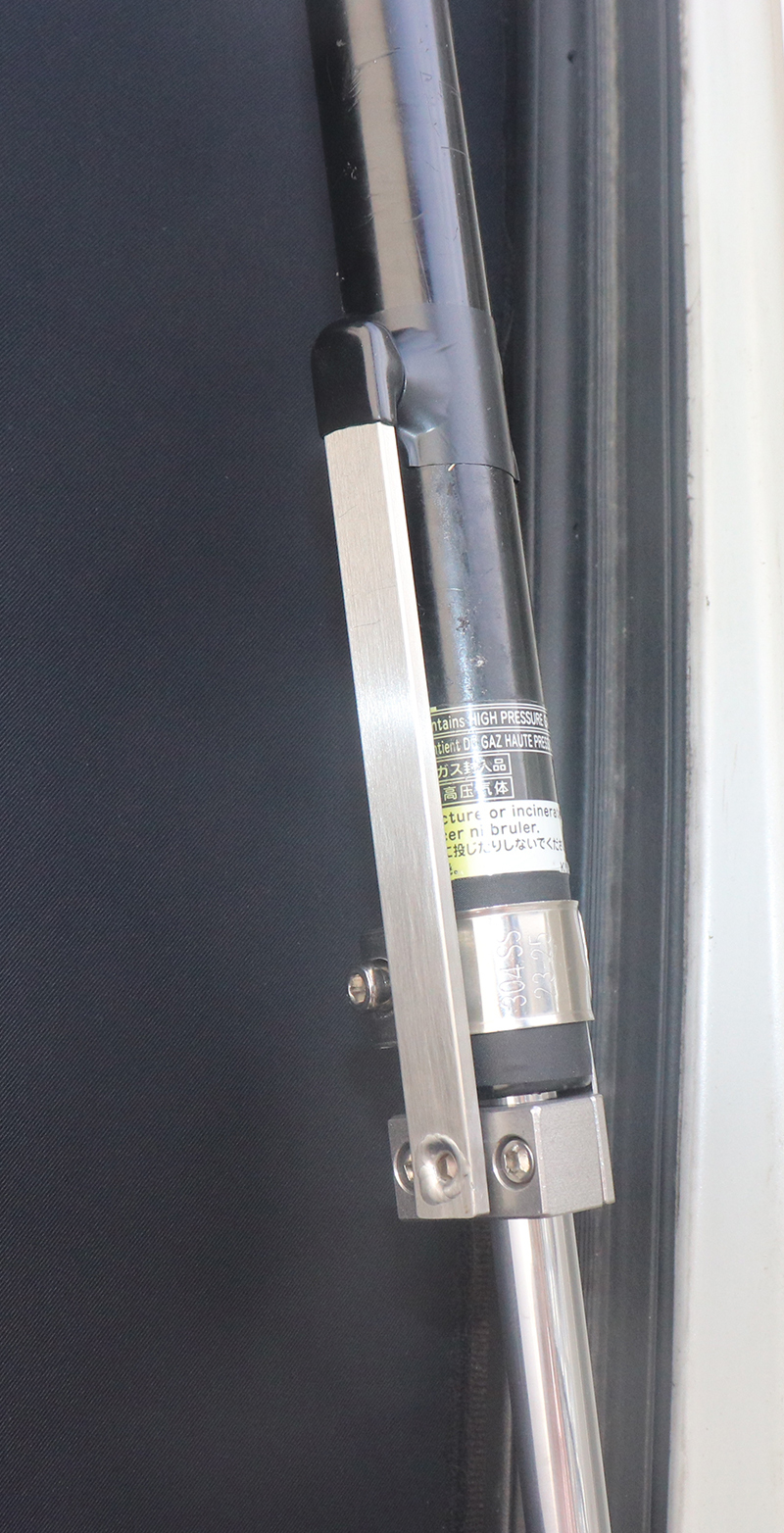
※2023.7.21以降に出荷したアイズ-ストッパーにつきましては、本体をよりコンパクトにした関係で、ハンドルとシリンダーの距離が近くなっております。調整が必要な際はコチラをご覧ください。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9695149.html
≪装着動画≫
10分弱の動画です。YouTubeでご覧いただくと、説明用の字幕も見れます。
操作具合の動画
上側ホルダーは 従来の仕様のものですが、操作具合は 磁石式の最新仕様のものと 同じになります。
YouTubeでご覧いただくと、説明用の字幕も見れます。
運転席側への装着のご説明は以上です。
補足.助手席側へ装着する場合
なお、この説明書の冒頭にある【装着作業に先立ちまして】 で ご説明したように、操作状況が運転席側とは違ってきます。【装着作業に先立ちまして】 の内容をご覧いただき、 助手席側への装着をご検討ください。
1.シリンダー位置の回転
運転席側バックドアダンパーのシリンダーをつかんで、時計方向(上側から見て右回転)に止まるまで回しておきます。


2.保護テープと本体固定用クランプの取り付け
シリンダーの最下部に保護テープを貼ってから、

保護テープの上付近に本体固定用クランプを仮固定しておきます。クランプは、ロッド部分で装着してから、シリンダー部分へ移動させて六角レンチを使って仮固定しておきます。
ボルト頭は、画像のように車内側(シリンダーの右側)で締めます。

3.本体Aの仮固定
本体Aを、本体固定用クランプで仮固定します。詳細は 運転席装着の「3.本体Aの仮固定」 を参照ください。
本体Aの向きは、ボルト穴が 車体の真後ろ~少し左側方向を向いている状態で仮固定してください。


4.本体Aに本体B固定
以下のように、2種類の操作状況のいずれかを選んで 抱き合わせ固定をしてください。
①本体Bの赤いポンチマークを下側にして抱き合わせると、ドアを固定時には ハンドルが車内側になります

下画像は 固定した際のハンドル位置です。

②赤いポンチマークを、上側にして抱き合わせると、ドア固定時には ハンドルが車外側になります

下画像は 固定した際のハンドル位置です。

①、②、 いずれにありましても、ハンドル固定を解除した際のホールドは、運転席側と同様に 上方向にホールドします。
①の場合では、1/4回転ほど左回しをして、②の場合では、3/4回転ほど左回しをしてから 上方向に磁石でホールドすることになります。

5.ハンドルの取り付け
6.各部がボディやドアに当たらないことを確認
7.本体固定用クランプの本固定
8.上側ホルダー用磁石の貼付け
の、 5、~ 8、 につきましては、運転席側装着の説明内容を参考にしてください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ご使用方法・ご注意
【 ご使用方法 】
バックドアの開き位置を決めて押さえておき、アイズストッパーのハンドルを締め込んで固定します。
ハンドルの締め込み具合は、ドアを固定できる必要最低限の締め込み具合を心がけてくださいドアは動かないけど、押せば動く状態(がっちりと固定され過ぎていていない状態)が望ましい状態です。
ハンドルを強力に締め込むことで、ドアが強固に固定されていますと、下記に説明している危険が生じます!
【 ハンドルは軽めに固定してご使用ください 】
下画像では、全開位置のドア先端部に12kgほどを 吊り下げた状態で固定しています。バックドアにリヤキャリアや、はしごなどの重量物が取り付けられていたりして、バックドアの重さが10kg以上重くなっていると、アイズ-ストッパーでがっちりと固定することは危険を伴います。

もし、10kg以上重くなっているバックドアを(例えばリアキャリアに自転車を積載している場合など)、全開位置で固定したとすると、純正ダンパーの付け根部分が破壊してしまう可能性があり、とても危険です。
ダンパーの付け根部分には、テコの原理と同じ作用により、ドア先端部に加えた荷重の10倍以上の力が働きます。バックドアが10kg以上重くなっている場合では、ダンパー付け根部分には 300kg・f 近い 大きな力が掛かることになります。トヨタ純正のダンパー付け根部分の強度は、300kg・f 以上の力に耐えることを想定していません。
試しに、 ドアを全開位置に ガチッと固定した状態にして、少し力を加えて(あまり大きな力は加えないで) ドアを押し下げようとしてみてください。ダンパーの付け根部分 や バックドアのルーフ側にあるヒンジ を注視していただくと、ボディの鉄板部分が歪んできて、とても大きな力が加わっている様子を 実感していただけると思います。
自転車を積載しているなど 10kg以上重くなっている場合では、半開位置での固定にとどめてください。その場合にありましても、ドアを押せば、動いてしまう程度の必要最低限の固定具合にしてお使いください。押せば動く状態(がっちりと固定されていない状態)が望ましい状態です。ドアを押しても動かないほどに ガッチリと固定し過ぎることは危険です!!
アイズ-ストッパーでドアを軽く固定されている限りでは、ドアに大きな力が加わった際でも、ドアがズレ動いてくれることで、ダンパーの付け根部分が破壊されることはありませんが、ドアを強力に固定して、大きな力が加わった際にも、ドアがガッチリと動かないほどに固定されていると、ダンパーの付け根部分が破壊してしまう可能性があります。十分にご注意ください。
そのような危険性を回避するためにも、必要最低限の軽めの固定でお使い下さい。 ユーザー様以外の方がドアを固定される場合でも、ご注意してもらってください。
ガチッと固定されているドアを、 他のどなたか や お子さんだとか が 強く押したり、引いたり、ぶら下がったり されることの無いように、十分にご注意いただけますよう お願い申し上げます。
【 ドア全閉から30センチほどまでの半開状態につきまして】
バックドア全閉から30センチほどまでの、わずかな開き位置ではグラグラした固定状況になります。どれほど強く固定をしたとしても、ダンパー付け根部分の遊びがあるため、かっちりとした固定具合にはなりませんことを ご了承ください。
【 定期的に、本体がズレ動いていないかを 確認ください】
バックドアを全開位置に保持しておく際(降りてこないようにする)には たいした固定力を必要としません。バックドアを半開位置から開いていかないように保持する際に 強力な固定力が必要になります。また半開位置に固定しているバックドアを、どなたかが無理矢理 開こうとした場合には、とても大きな力が働きますので、本体がズレ動いてしまう可能性があります。爪部が溝部分から出てしまうようなことがありますと、爪部分の形状が外側に曲がってしまいます。 爪部分の形状が外側に曲がってしまいますと、シリンダーの溝部分から外れやすい状態になりますことから、再装着をし直しても しっかりと固定ができなくなります。
定期的に 本体がズレ動いていないかを 確認されること(シリンダーと本体との隙間の具合で確認できます)を お勧めいたします。
なお、以前に出荷した製品で、爪部分の形状が外側に曲がってしまった場合の対策として、「強力タイプのクランプ」を用意しております。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9706824.html
【固定しづらい場合につきまして】
5型以降の寒冷地仕様車では、寒冷時でも強い反力が出る強化されたダンパーが付いています。逆に夏場にはガスダンパーの反力は とても強くなります。
夏場に、ドア全開時には ハンドルを軽く締め込んで固定ができても、開き具合が中間位置では 強めに締め込まないとしっかりと固定できない場合があります。
また、ロッド部分に潤滑剤などの油分やワックス成分などが残っていると、しっかりと固定できない場合があります。ロッド部分ならびに真鍮スペーサー部分を脱脂してみてください。
【 ハンドルの位置にご注意ください 】
ドアを固定している際には、ハンドルは車外側に飛び出ている状態になります。
適度に固定をした状態では、強めの力でドアを閉めていくこともできてしまいますが、バックドアが閉まりきるより前に、ハンドルがドアの内側面に当たってしまうことになります。 特にユーザー様以外の方が バックドアを開閉される場合などには、半固定状態に気付かない場合もありますのでご注意ください。

【 ハンドルの外し方について 】
ハンドルは左回転させていくと、外すことができます。ハンドルを外した状態でも、中にある部品(真鍮スペーサー)が出てくることはありません。
ユーザー様以外の方がバックドアを開閉される機会が多いような場合などでは平素はハンドルを外しておくといった使い方もありますが、ハンドルの紛失にはご注意ください。
ハンドルのボルト部分の長さは、個別に調整して組んでいます。もしハンドルを紛失された場合、補修部品としてのご用意はありますが、調整が必要ですので弊社までご連絡ください。
【 ドア半開状態の際の、排気ガス流入の危険性について 】
バックドアを半開状態にしている際に、エンジンがかかっておりますと、排気ガスが車内に流入しやすい状況となり、排気ガス中毒の危険性があります。十分にご注意ください。
フロントエアコンを外気導入にして稼働させると、室内側から常にバックドア側へと空気が流れることで、室内側への排気ガスの流入を避けることが出来ます。なお、リヤエアコンやリヤヒーターを稼働させても、車内循環空気ですので排気ガスの流入を防ぐ効果がありません。
【 ボルトのゆるみについて 】
装着して1か月ほどしてから、「爪の上を固定しているクランプのボルト」(7.本体固定用クランプの本固定 を参照) と 「本体AとBを抱き合わせ固定している ボルト」 を増し締めしてください。特に、「爪の上を固定しているクランプのボルト」の増し締めを 必ず行ってください。
固定力が弱くなったように感じられた場合には、
本体AとBを抱き合わせ固定しているボルトが緩んでしまっている可能性があります。付属の4mm六角レンチを使って、しつかりと固定し直してください。
頻繁にそのボルトが緩んでしまうようでしたら、いったん外して、ボルトの先に「ボルト緩み防止剤」を塗付してから 固定されることをお勧めします。
「ボルト緩み防止剤」の代わりに瞬間接着剤でも代用できますが、強く固定されすぎますので、ボルトを外す際には 本体を小型バーナーなどで熱しながら外すことになります。
【 固定した際のハンドル位置が、装着当初よりも進んでしまった場合の調整方法 】
このブログ https://aizurv2.hamazo.tv/e9754207.html を参照してください。
最後になりますが、ご使用上で気になることがあれば、ご報告いただけると 今後の改良などへとつなげることができて、ありがたく存じます。
弊社レビュー投稿ページは下記URLからアクセスできます。どうぞよろしくお願いいたします。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/reviewlist
===============
本 取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。ご了承ください。
なお、この説明書につきましては、個人様の非営利目的以外の使用は ご遠慮くださいますよう お願い申し上げます。
また、アイズ-ストッパー は、特許出願中です(特願2021-142319) ご留意の程 お願い申し上げます。
本コンテンツは2023年9月19日以降の生産のアイズ-ストッパー(ハイエース、標準ルーフ、ミドルルーフ、ハイルーフ 車用)の装着・ご使用の説明書です。

≪ご注意≫
※アイズ-ストッパーは、トヨタ純正のダンパー(純正強化ダンパー含む)用です。
社外品の強化ダンパーやハイリフトダンパーなどには、適合しない可能性があります。
また、ハイエースⅠ型で装着されていた仕様のダンパー(下画像参照)には、ステー部分を加工しないと装着できません。

↑
ロッドとステーのジョイント部分が車外側を向いているタイプのダンパーです。赤丸部分が干渉します。
ステー部分を 下画像のように加工(ステー部分を削っています)することで、装着が可能になります。

※バックドアの重さが10kg以上増えている状態で全開位置で固定しないで下さい。
バックドアに自転車を積載した場合など、重量が増えたドアを全開位置で固定すると、テコの原理でドアを支えるダンパーには、100kg・f 以上のとても大きな荷重が加わります。ダンパーの取り付け部分の強度が耐えられず 破損する恐れがあり大変危険です。詳細は当説明書の一番最後の「ご使用方法・ご注意」をご覧下さい。
※装着後は各箇所、ボルトが緩んでいないかなどの定期的な確認をお願いいたします。
===========================
≪商品内容≫

真鍮スペーサーの紛失にご注意ください!!
※上画像の本体Bの黄色テープの中に、ダンパーロッドを固定するための真鍮製スペーサー入っています。小さな部品ですので、紛失にご注意ください。

万一の紛失時には、補修部品としてのご用意はありますが、全ての部品をセットで弊社に返送いただき再調節する必要があります。
≪各部の名称≫

≪装着動画≫
10分弱の装着動画です。 標準ルーフ車ですが、ミドルルーフ車、ハイルーフ車も装着方法は同じです。
下記の装着説明と併せて、一度ご覧いただければと存じます。YouTubeでご覧いただくと、説明用の字幕も見れます。
==================
【装着作業に先立ちまして】
本製品は、基本的には運転席側のバックドアダンパーに装着します。
●運転席側での操作状況は 下画像のようになります。

ハンドルを車外側へ回して固定し、解除時はハンドルを上側でホールドさせます。

●助手席側への装着も可能ですが、操作状況が運転席側とは違ってきますのでご注意ください。
助手席側での操作状況は 下画像のように 2通りの操作状況があります。一般的には運転席側での操作状況の方がお勧めです。
①固定時には、ハンドルが車内側になる操作状況にする場合。解除時は上側でホールドします。

②固定時には、ハンドルが車外側になる操作状況にする場合。解除時には3/4回転させてから上側でホールドします。

下記説明書では、まず運転席側への装着をご説明しています。助手席側への装着説明は、この説明書の一番最後で、補足説明的にご案内しております。
助手席側への装着される場合には、まず 運転席側への装着説明をご一読いただいた後で、助手席側への装着の補足説明をご覧下さい。
============================================
1.シリンダー位置の回転
運転席側バックドアダンパーのシリンダーをつかんで、反時計方向(上側から見て左回転)に止まるまで回しておきます。


2.保護テープと本体固定用クランプの取り付け
2- ①
シリンダーの最下部に保護テープを貼ります。(テープの下端と、シリンダーの下端を揃えます)
保護テープの上から爪でシリンダーの溝をなぞり、しっかりと溝を作ってください。(重要)

2- ②
本体固定用クランプのボルトを付け替えます。
元から付いているボルトを外します。ボルト頭側についているスペーサーも一緒に外します。

↓
ボルトを抜く際に、受け側のナットが外れますので、落として無くさないように注意してください。


↓
六角穴付きのボルトに付け替えます。差し込んだだけだと長さが足りていませんが大丈夫です。

2- ③
本体固定用クランプを 、ロッドの部分で取付けて、その後で シリンダーの保護テープの上側付近で仮固定します。
クランプは、最終的にはシリンダーの位置で締め付けるものですが、まずはロッドの位置でハメ入れます。ハメ入れたら、クランプを握り、締め付けて癖をつけてください。
※シリンダーの位置で輪っか状態にするのは大変なので、ロッド位置で輪っかにしてからシリンダーの位置へスライドさせます。

Aとナットとの間隙を「ギュッ」として縮めておきます。広いままですと ボルトがナット側に届きません。

↓
ボルトを 右側から左側のナットへと入れて、少しだけ回してクランプを輪っか状態にしておきます。 斜めに入らないように注意しながら手で回し入れます。もし斜めに入ると数回転させた時点で固くなります。入れ直してください。

↓
クランプをシリンダーの位置へと移動させます。落ちてこないように、付属の六角レンチで軽く締め付けておきます。この時、ボルト頭の位置はシリンダーの左側(車内側)になるようにします。

※もし短いボルトでの締め付けが難しいようでしたら、元の長いボルトを 8mmレンチを使って締めこみ、ナットとⒶ(上から2枚目の画像に記載)との間隔を狭めて形状に癖を付けておいてから、六角穴付きボルトで締め付けます。
3.本体Aの仮固定
3- ①
本体Aを、本体固定用クランプで仮固定していきます。まず、本体Aの爪部分をシリンダーの溝へしっかり ハメ入れます。その際、下記注意事項を必ずご確認ください。

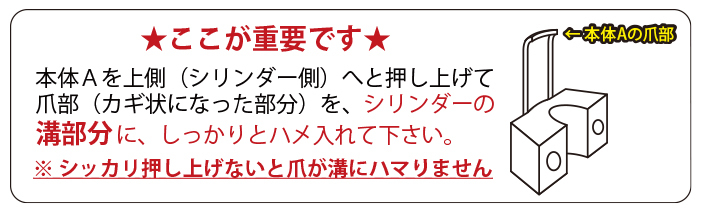
3- ②
本体Aを仮固定する際の向きは、本体Aのボルト穴や 固定用クランプのボルト頭が、車体の真後ろ~少し右側方向(車外側方向)を向いている状態にします。

↓※画像では本体Aに本体Bがすでに接合されていますが、この段階では本体Aのみの固定となります。

3- ③
本体Aを、本体固定用クランプで仮固定します。
爪部の上をクランプで固定します。左画像の赤線付近に、シリンダーの溝部分がくるようにします。
ボルト頭は、シリンダーの左(車内側)で締めます。ボルト頭が、「車体の真後ろ」を向いている状態で固定します。

下図のように必ず爪部の上をクランプで押さえている状態になるように固定してください。
爪が外れていないかいま一度、確認してください。

固定時の注意(ダメな例)


付属の六角レンチを使って、この段階では緩めに固定しておきます。
※本体Aが落ちてこない程度には締め付けてください。

4.本体Aに本体Bを固定
仮固定された本体Aに、本体Bを抱き合わせて、5mmボルト2本で六角レンチを使って、しっかりと固定します。

↓
固定時の注意事項
【 注意 1 】真鍮スペーサーの脱落防止用に貼ってあるテープは取り除いてください。真鍮スペーサーの紛失にご注意ください!
【 注意 2 】本体Aに本体Bを合わせる際には、。必ず、本体Bの 赤いポンチ マークを下側にして、抱き合わせてください。
(運転席側へ装着する場合です)
【 注意 3 】真鍮スペーサーの凹面がダンパーロッドの凸面に必ず面で当たるように調整して固定してください。※下図参照(真鍮スペーサーは、中で回転させることができます)

上の注意事項を守りながら固定します。

5.ハンドルの取り付け
本体Bのナット穴に、ハンドルのボルト部を回し入れ右回転させていって軽く止めます。ボルト部がナット穴に対して、斜めに入らないようにご注意ください。
ハンドルの回転中心部を、下画像のように親指で押えながら回し入れていくと 斜めにならないで入ってくれやすいです。
もし 斜めに入れてしまった場合には、少し回した時点で固くなります。そのまま締めてしまうと固着してしまいますので、無理に回そうとはしないで 反回転させて ボルト部分をいったん抜き出してから、まっすぐに入れ直してください。
ボルト部を真っすぐに回し入れます

↓
ハンドルはクルクルと軽く入って行くハズです。もし 少し回した時点で固くなるようでしたら、無理に回そうとはしないで ボルト部分をいったん抜き出してから、まっすぐに入れ直してください。

↓
ハンドルの動きが止まった際の、ハンドルの傾きは下画像のようになるハズです(2時くらいの方向)。

もし、このような位置で止まらない場合は…、
①:ひとつ前の項目「手順4」の 「【 注意 2 】本体Aに本体Bを合わせる際には、必ず、本体Bの 赤いポンチマークを下側にして抱き合わせてください。」 を今一度確認して、赤いポンチマークが下側になるように付け直してください。
②:ひとつ前の項目「手順4」の 「【 注意 3 】真鍮スペーサーの凹面がダンパーロッドの凸面に必ず面で当たるように調整して固定してください。」 を今一度確認してください。
6.各部がドアに当たらないことを確認してください
アイズ-ストッパーを装着後、ドアをゆっくりと閉めていって、本体やクランプやハンドルの各部がドアに当たらないことを確認してください。
まず始めに確認
まずドアを全開にして、シリンダーを反時計方向(上側から見て左回転)に止まるまで回した時に…
※「1.シリンダー位置の回転」でもご説明したように


↓↓↓
各ボルトの頭が車体の真後ろ~少し右側方向を向いている状態になっていることを、今一度確認願います。
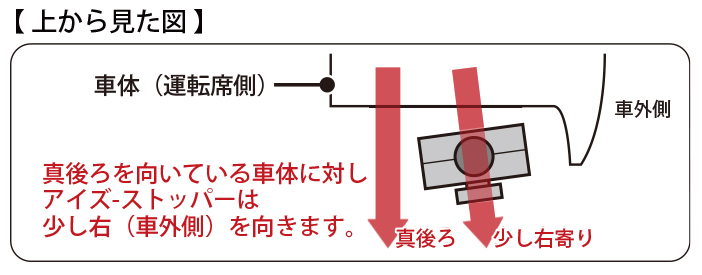

※「1.シリンダー位置の回転」でもご説明したように


↓↓↓
各ボルトの頭が車体の真後ろ~少し右側方向を向いている状態になっていることを、今一度確認願います。
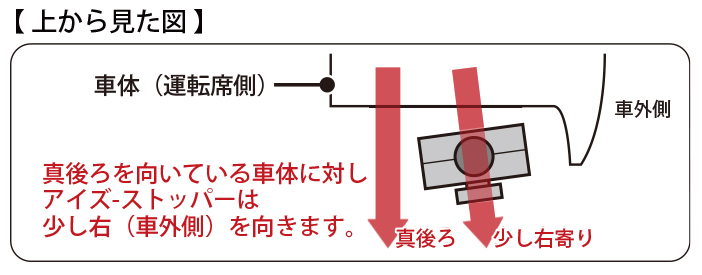

この段階では、ドアを固定しようとしないでください!! 本体がまだ仮固定の状態ですのでドアを固定できません。固定しようとすると不具合の原因となりますので、ご注意ください。
6- ①
ハンドルの黒色キャップの中には、磁石が内臓されていてハンドルを真上方向にした際には、磁石の吸着力によりハンドルを真上方向位置で仮ホールドできます。ハンドルを真上方向位置で仮ホールドした状態にしてから、ドアをゆっくりと閉めて行ってください。

6- ②
ドアが閉まり切る直前でいちど止めてみて、本体やハンドルがバックドア側の当たりそうな位置に、付属のキズ付き防止のスポンジテープを貼ります。次に、ドアを最後まで閉めてみて、各部がバックドア側に当たっていないかを確認してください。
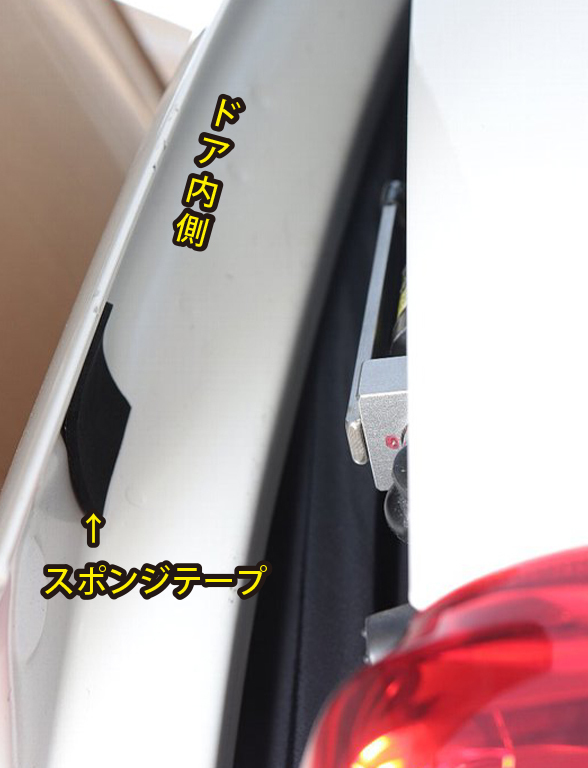
6- ③
シリンダーは、ドアの開閉に伴って、わずかに回転するようになっています。シリンダーの「ドアの開いた状態での回転位置」「ドアの閉じた状態での回転位置」それぞれに対し、ドア内側に当たらないことを確認してください。


↑
手首の角度に注目。これくらい回転するマージンがあります。
ほとんどの お車では、全開からドアを閉めていくに従い、シリンダーは時計回り(上から見て右回転)に回りますが、ハイエースの中には、閉めていくに従い、シリンダーが反時計回り(上から見て左回転)に回る お車もあります。本体やホルダーの各部がボディやドアに当たらない、車両個体差を考慮した最大公約数的な位置として、「ドア全開時に シリンダーを反時計まわりに回して止めた位置で、各ボルトの頭が車体の真後ろ~少し右側方向」と しておりますが、お車によっては、「車体の真後ろ~少し左側方向」が具合が良い場合もあります。 お車の状況に応じて本体の方向を 具合が良い位置に調節してください。
ご確認下さい
※お車によっては、ドア側に貼ったスポンジテープが凹んでしまう状況になります。特に、ミドルルーフ(ロング・ワイドボディ)車では、ハンドル部分がドアの内側に当たってしまうというご報告があります。アイズ-ストッパーを装着しても ドア側の塗装をキズ付けるなどの問題が出ないかどうかは ドアの内側に貼った キズ付き防止スポンジの凹み具合でご判断ください。本体を回転させて調整することで ドアに当たらないようにできる場合が多いですが、装着を断念される場合には、ご返品・ご返金を承りますので お申し出くださいますよう お願い申し上げます。
スポンジが凹んだ状態(本体がバックドア側に接触している)のまま走行をされますと、接触部分がスポンジを突き破ってドア側の塗装面をキズ付ける状態になる場合もあります。ご留意ください。なお、装着作業に起因する塗装面へのキズなどの支障につきましては、免責とさせていただいております。ご了承のほど お願い申し上げます。
スポンジが凹んだ状態(本体がバックドア側に接触している)のまま走行をされますと、接触部分がスポンジを突き破ってドア側の塗装面をキズ付ける状態になる場合もあります。ご留意ください。なお、装着作業に起因する塗装面へのキズなどの支障につきましては、免責とさせていただいております。ご了承のほど お願い申し上げます。
7.本体固定用クランプの本固定
7- ①
各部がボディやドアに当たらないことをご確認いただいた後に、その位置で本体固定用クランプのボルトを付属の六角レンチを使って、シッカリと本締めしてください。
※その際に、下に記載した注意2点を、今一度確認してから本固定してください。
①:シリンダーの溝部分に爪部(カギ状になった部分)が、しっかりと入っていること(手順 3 を参照ください)
②:爪部の上をクランプでしっかり締め付けている状態になっていること(手順 3-③ を参照ください)

【溝部分に爪部が入り込んでいないと、ドアを半開固定した際にズレ動いてしまします!! 】
ドアが開いていかないように アイズ-ストッパーで固定してもズレ動いてしまう場合には、溝部分に爪部が入っていないことが原因であったりします。
クランプを強力に締め付けることでは、ズレ止めはできません。必ず爪部が溝部分に入っている必要があります爪部が溝部分に入っている状態(本体をしっかりと押し上げている状態)で しっかりと力いっぱい締め付けてください。
7- ②
固定具合を 必ずご確認ください !!
ここで一度、ドアを少し開いたところで、アイズ-ストッパーのハンドルを 時計の針でいうところの 2時~3時くらいの位置まで締め込み、 ドアをしっかりと固定してみてください。

ドアを固定した状態で、ドアを開く方向に少しゆり動かしてみたときに、本体がズレ動かないことを確認してください。

下画像のように 本体とシリンダーとの間に ほとんど 隙間がないのが正常な(ズレ動いていない)状態です

下画像のように 本体とシリンダーとの間に隙間が生じていると、本体がズレ動いてしまっている状況です!!!
なお、シリンダーの溝部分に爪部が、しっかりと入っている状態でしたら、2mmくらいの隙間があっても大丈夫です。

もし、ドアを開く方向に少しゆり動かしてみたときに 隙間が2mm以上に広がっていくようでしたら、、シリンダーの溝部分から爪部が出てしまっています。
それ以上 ドアを開くことを止めて、もう一度本体Aを上側(シリンダー側)へとしっかりと押し上げて爪部(カギ状になった部分)がシリンダの溝部分に確実に入っている状態で、ボルトを強く締めあげてください。


7- ③
ドアを半開状態に固定した際に外側に突き出ているハンドルがボディー側に当たらないかを確認してください。

支障があるようなら本体固定用クランプを緩めて、本体の方向を修正してください。


定期的な確認をお願いします
装着して1か月ほどしてから、本体やクランプの各ボルトの増し締めを行ってください。
また、また、各箇所やボルトなど、緩みが無いかを定期的にご確認下さい。気温の低い時期では、ドアを問題無く固定できていたとしても、気温が上昇して ダンパーの反力が強くなることで ドアを固定しきれなくなるケースもあります。
締め付け具合が不十分なことで、本体がズレ動いてしまって 爪部がシリンダーの溝部分から外れてしまいますと、爪部の形状が変形してしまいます。
下画像は、正常な状態の爪部の形状です。

下画像は、爪部が変形してしまっている画像です。

上画像のような状態に変形してしまいますと、 固定具合がさらに悪化してしまいますので、再度装着をし直しても ドアをしっかりと固定できなくなります。クランプのボルトの緩みに ご注意ください。
なお、変形してしまった爪部の補修を承ることが出来ます。
サポート商品販売ページ https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport の 一番下から3番目の 「変形した爪部分の修正」をご購入ください。
また、また、各箇所やボルトなど、緩みが無いかを定期的にご確認下さい。気温の低い時期では、ドアを問題無く固定できていたとしても、気温が上昇して ダンパーの反力が強くなることで ドアを固定しきれなくなるケースもあります。
締め付け具合が不十分なことで、本体がズレ動いてしまって 爪部がシリンダーの溝部分から外れてしまいますと、爪部の形状が変形してしまいます。
下画像は、正常な状態の爪部の形状です。

下画像は、爪部が変形してしまっている画像です。
上画像のような状態に変形してしまいますと、 固定具合がさらに悪化してしまいますので、再度装着をし直しても ドアをしっかりと固定できなくなります。クランプのボルトの緩みに ご注意ください。
なお、変形してしまった爪部の補修を承ることが出来ます。
サポート商品販売ページ https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/mssupport の 一番下から3番目の 「変形した爪部分の修正」をご購入ください。
8.上側ホルダー用磁石の貼付け
8-1
ハンドルの黒色キャップの中には、磁石が入っています。その磁石に対して、付属の「上側ホルダー用磁石」を吸着させます。
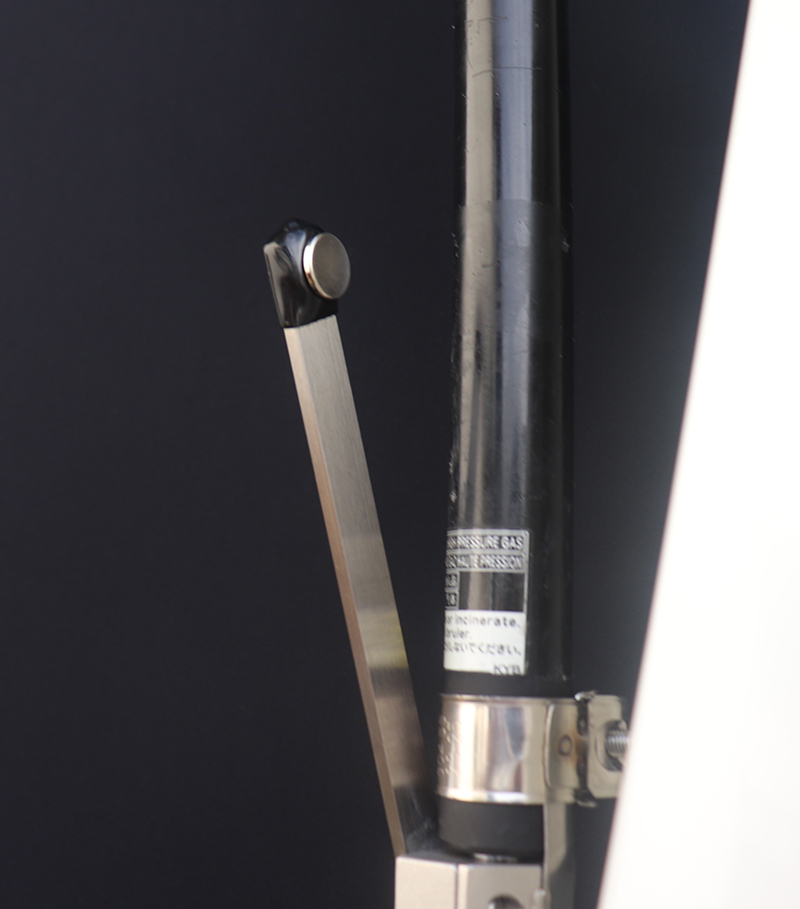
8-2
ハンドルを真上方向にした位置で、ハンドル側に吸着させている「上側ホルダー用磁石」を、シリンダー側へと吸着替えします。
「上側ホルダー用磁石」を ハンドルの黒色キャップ側から シリンダー側へと移し替えます(磁力でシリンダーに貼りつかせます)


8-3
ハンドルは左回転させて下側に垂らしておき、シリンダーに貼りつかせている磁石の上から、「上側ホルダー用テープ」を貼ります。

※もし貼るのを失敗してしまったり、紫外線等で痛んできてしまった場合は、ビニールテープで代用して下さい。
8-4
「黒色キャップの中の磁石」と、「上側ホルダー用磁石」とが引き合う磁力により、ハンドルを真上方向にホールドすることができます。
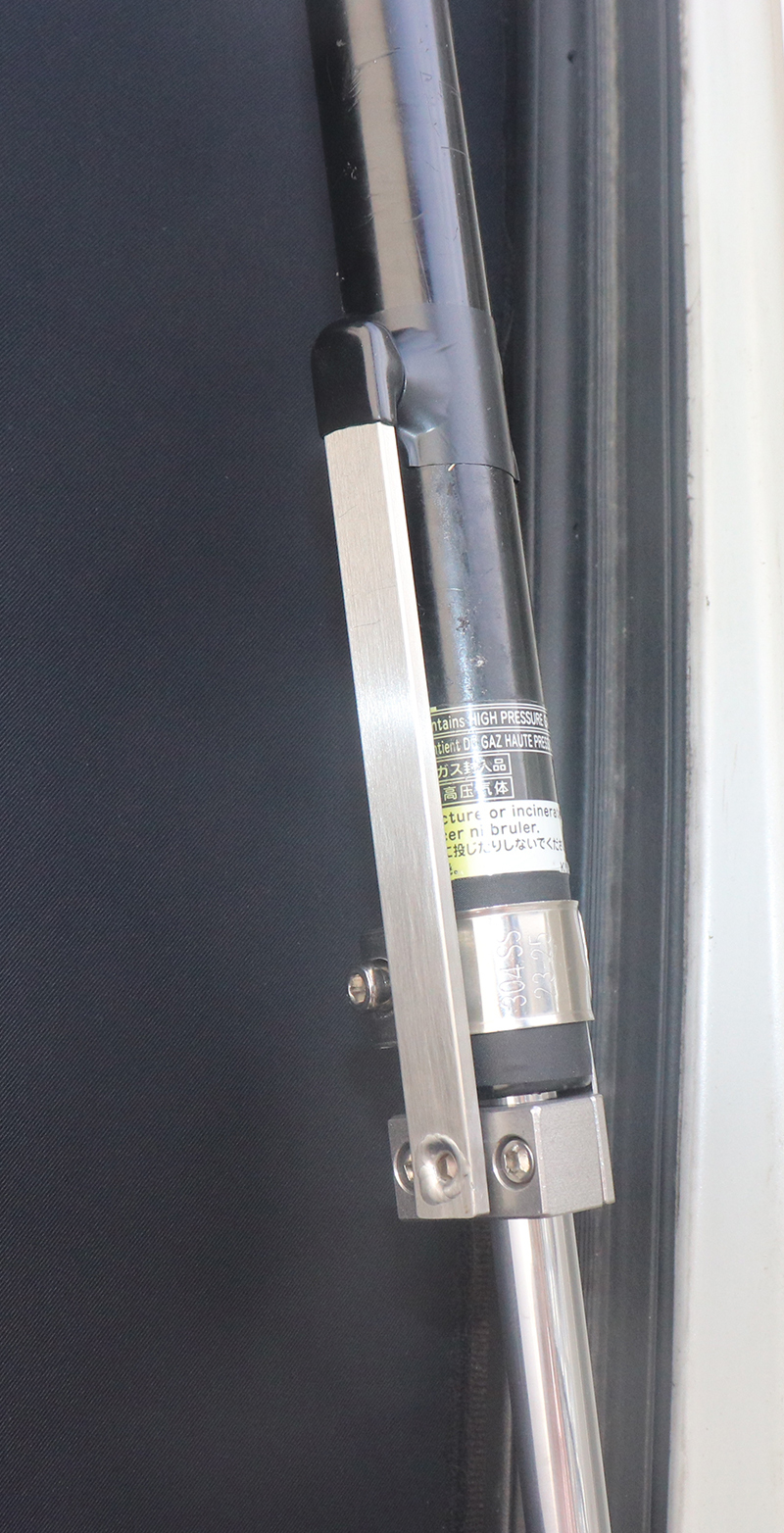
※2023.7.21以降に出荷したアイズ-ストッパーにつきましては、本体をよりコンパクトにした関係で、ハンドルとシリンダーの距離が近くなっております。調整が必要な際はコチラをご覧ください。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9695149.html
≪装着動画≫
10分弱の動画です。YouTubeでご覧いただくと、説明用の字幕も見れます。
操作具合の動画
上側ホルダーは 従来の仕様のものですが、操作具合は 磁石式の最新仕様のものと 同じになります。
YouTubeでご覧いただくと、説明用の字幕も見れます。
運転席側への装着のご説明は以上です。
補足.助手席側へ装着する場合
なお、この説明書の冒頭にある【装着作業に先立ちまして】 で ご説明したように、操作状況が運転席側とは違ってきます。【装着作業に先立ちまして】 の内容をご覧いただき、 助手席側への装着をご検討ください。
1.シリンダー位置の回転
運転席側バックドアダンパーのシリンダーをつかんで、時計方向(上側から見て右回転)に止まるまで回しておきます。

2.保護テープと本体固定用クランプの取り付け
シリンダーの最下部に保護テープを貼ってから、
保護テープの上付近に本体固定用クランプを仮固定しておきます。クランプは、ロッド部分で装着してから、シリンダー部分へ移動させて六角レンチを使って仮固定しておきます。
ボルト頭は、画像のように車内側(シリンダーの右側)で締めます。

3.本体Aの仮固定
本体Aを、本体固定用クランプで仮固定します。詳細は 運転席装着の「3.本体Aの仮固定」 を参照ください。
本体Aの向きは、ボルト穴が 車体の真後ろ~少し左側方向を向いている状態で仮固定してください。


4.本体Aに本体B固定
以下のように、2種類の操作状況のいずれかを選んで 抱き合わせ固定をしてください。
①本体Bの赤いポンチマークを下側にして抱き合わせると、ドアを固定時には ハンドルが車内側になります

下画像は 固定した際のハンドル位置です。

②赤いポンチマークを、上側にして抱き合わせると、ドア固定時には ハンドルが車外側になります

下画像は 固定した際のハンドル位置です。

①、②、 いずれにありましても、ハンドル固定を解除した際のホールドは、運転席側と同様に 上方向にホールドします。
①の場合では、1/4回転ほど左回しをして、②の場合では、3/4回転ほど左回しをしてから 上方向に磁石でホールドすることになります。

5.ハンドルの取り付け
6.各部がボディやドアに当たらないことを確認
7.本体固定用クランプの本固定
8.上側ホルダー用磁石の貼付け
の、 5、~ 8、 につきましては、運転席側装着の説明内容を参考にしてください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ご使用方法・ご注意
【 ご使用方法 】
バックドアの開き位置を決めて押さえておき、アイズストッパーのハンドルを締め込んで固定します。
ハンドルの締め込み具合は、ドアを固定できる必要最低限の締め込み具合を心がけてくださいドアは動かないけど、押せば動く状態(がっちりと固定され過ぎていていない状態)が望ましい状態です。
ハンドルを強力に締め込むことで、ドアが強固に固定されていますと、下記に説明している危険が生じます!
【 ハンドルは軽めに固定してご使用ください 】
下画像では、全開位置のドア先端部に12kgほどを 吊り下げた状態で固定しています。バックドアにリヤキャリアや、はしごなどの重量物が取り付けられていたりして、バックドアの重さが10kg以上重くなっていると、アイズ-ストッパーでがっちりと固定することは危険を伴います。
もし、10kg以上重くなっているバックドアを(例えばリアキャリアに自転車を積載している場合など)、全開位置で固定したとすると、純正ダンパーの付け根部分が破壊してしまう可能性があり、とても危険です。
ダンパーの付け根部分には、テコの原理と同じ作用により、ドア先端部に加えた荷重の10倍以上の力が働きます。バックドアが10kg以上重くなっている場合では、ダンパー付け根部分には 300kg・f 近い 大きな力が掛かることになります。トヨタ純正のダンパー付け根部分の強度は、300kg・f 以上の力に耐えることを想定していません。
試しに、 ドアを全開位置に ガチッと固定した状態にして、少し力を加えて(あまり大きな力は加えないで) ドアを押し下げようとしてみてください。ダンパーの付け根部分 や バックドアのルーフ側にあるヒンジ を注視していただくと、ボディの鉄板部分が歪んできて、とても大きな力が加わっている様子を 実感していただけると思います。
自転車を積載しているなど 10kg以上重くなっている場合では、半開位置での固定にとどめてください。その場合にありましても、ドアを押せば、動いてしまう程度の必要最低限の固定具合にしてお使いください。押せば動く状態(がっちりと固定されていない状態)が望ましい状態です。ドアを押しても動かないほどに ガッチリと固定し過ぎることは危険です!!
アイズ-ストッパーでドアを軽く固定されている限りでは、ドアに大きな力が加わった際でも、ドアがズレ動いてくれることで、ダンパーの付け根部分が破壊されることはありませんが、ドアを強力に固定して、大きな力が加わった際にも、ドアがガッチリと動かないほどに固定されていると、ダンパーの付け根部分が破壊してしまう可能性があります。十分にご注意ください。
そのような危険性を回避するためにも、必要最低限の軽めの固定でお使い下さい。 ユーザー様以外の方がドアを固定される場合でも、ご注意してもらってください。
ガチッと固定されているドアを、 他のどなたか や お子さんだとか が 強く押したり、引いたり、ぶら下がったり されることの無いように、十分にご注意いただけますよう お願い申し上げます。
【 ドア全閉から30センチほどまでの半開状態につきまして】
バックドア全閉から30センチほどまでの、わずかな開き位置ではグラグラした固定状況になります。どれほど強く固定をしたとしても、ダンパー付け根部分の遊びがあるため、かっちりとした固定具合にはなりませんことを ご了承ください。
【 定期的に、本体がズレ動いていないかを 確認ください】
バックドアを全開位置に保持しておく際(降りてこないようにする)には たいした固定力を必要としません。バックドアを半開位置から開いていかないように保持する際に 強力な固定力が必要になります。また半開位置に固定しているバックドアを、どなたかが無理矢理 開こうとした場合には、とても大きな力が働きますので、本体がズレ動いてしまう可能性があります。爪部が溝部分から出てしまうようなことがありますと、爪部分の形状が外側に曲がってしまいます。 爪部分の形状が外側に曲がってしまいますと、シリンダーの溝部分から外れやすい状態になりますことから、再装着をし直しても しっかりと固定ができなくなります。
定期的に 本体がズレ動いていないかを 確認されること(シリンダーと本体との隙間の具合で確認できます)を お勧めいたします。
なお、以前に出荷した製品で、爪部分の形状が外側に曲がってしまった場合の対策として、「強力タイプのクランプ」を用意しております。
https://aizurv2.hamazo.tv/e9706824.html
【固定しづらい場合につきまして】
5型以降の寒冷地仕様車では、寒冷時でも強い反力が出る強化されたダンパーが付いています。逆に夏場にはガスダンパーの反力は とても強くなります。
夏場に、ドア全開時には ハンドルを軽く締め込んで固定ができても、開き具合が中間位置では 強めに締め込まないとしっかりと固定できない場合があります。
また、ロッド部分に潤滑剤などの油分やワックス成分などが残っていると、しっかりと固定できない場合があります。ロッド部分ならびに真鍮スペーサー部分を脱脂してみてください。
【 ハンドルの位置にご注意ください 】
ドアを固定している際には、ハンドルは車外側に飛び出ている状態になります。
適度に固定をした状態では、強めの力でドアを閉めていくこともできてしまいますが、バックドアが閉まりきるより前に、ハンドルがドアの内側面に当たってしまうことになります。 特にユーザー様以外の方が バックドアを開閉される場合などには、半固定状態に気付かない場合もありますのでご注意ください。

【 ハンドルの外し方について 】
ハンドルは左回転させていくと、外すことができます。ハンドルを外した状態でも、中にある部品(真鍮スペーサー)が出てくることはありません。
ユーザー様以外の方がバックドアを開閉される機会が多いような場合などでは平素はハンドルを外しておくといった使い方もありますが、ハンドルの紛失にはご注意ください。
ハンドルのボルト部分の長さは、個別に調整して組んでいます。もしハンドルを紛失された場合、補修部品としてのご用意はありますが、調整が必要ですので弊社までご連絡ください。
【 ドア半開状態の際の、排気ガス流入の危険性について 】
バックドアを半開状態にしている際に、エンジンがかかっておりますと、排気ガスが車内に流入しやすい状況となり、排気ガス中毒の危険性があります。十分にご注意ください。
フロントエアコンを外気導入にして稼働させると、室内側から常にバックドア側へと空気が流れることで、室内側への排気ガスの流入を避けることが出来ます。なお、リヤエアコンやリヤヒーターを稼働させても、車内循環空気ですので排気ガスの流入を防ぐ効果がありません。
【 ボルトのゆるみについて 】
装着して1か月ほどしてから、「爪の上を固定しているクランプのボルト」(7.本体固定用クランプの本固定 を参照) と 「本体AとBを抱き合わせ固定している ボルト」 を増し締めしてください。特に、「爪の上を固定しているクランプのボルト」の増し締めを 必ず行ってください。
固定力が弱くなったように感じられた場合には、
本体AとBを抱き合わせ固定しているボルトが緩んでしまっている可能性があります。付属の4mm六角レンチを使って、しつかりと固定し直してください。
頻繁にそのボルトが緩んでしまうようでしたら、いったん外して、ボルトの先に「ボルト緩み防止剤」を塗付してから 固定されることをお勧めします。
「ボルト緩み防止剤」の代わりに瞬間接着剤でも代用できますが、強く固定されすぎますので、ボルトを外す際には 本体を小型バーナーなどで熱しながら外すことになります。
【 固定した際のハンドル位置が、装着当初よりも進んでしまった場合の調整方法 】
このブログ https://aizurv2.hamazo.tv/e9754207.html を参照してください。
最後になりますが、ご使用上で気になることがあれば、ご報告いただけると 今後の改良などへとつなげることができて、ありがたく存じます。
弊社レビュー投稿ページは下記URLからアクセスできます。どうぞよろしくお願いいたします。
https://www.aizu-rv.co.jp/aizufr/reviewlist
===============
本 取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。ご了承ください。
なお、この説明書につきましては、個人様の非営利目的以外の使用は ご遠慮くださいますよう お願い申し上げます。
また、アイズ-ストッパー は、特許出願中です(特願2021-142319) ご留意の程 お願い申し上げます。